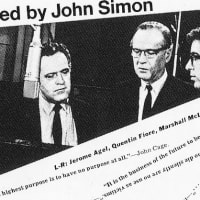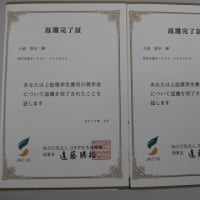松田茂樹『[続]少子化論:出生率回復と<自由な社会>』学文社, 2021.
日本の少子化の原因と対策について。学術書の体裁だが、データの議論の部分を飛ばして文字面だけを追うならば、一般の人にも論旨は分かると思う。「続」となっているが、正編に当たるのは『少子化論:なぜまだ結婚、出産しやすい国にならないのか』(勁草書房, 2013)である。著者は中京大学の教授である。
著者の議論はこう。福祉国家を維持したいならば、日本の人口数を維持する必要がある。移民による解決は社会に大きなストレスをもたらすので、現国民の出生数を増やす方向が良い。少子化の原因としては、未婚化と夫婦間の出生数の低下の二つが挙げられる。未婚化は、若年層の経済力の低下のためである。特に非正規雇用者の場合、正規雇用者と比べて出会いの機会もまた少ないため、結婚に至る確率が低くなっているという。
夫婦間の出生数の低下については、1990年代末から政府によって政策ターゲットとされ、共働き夫婦への支援となってさまざまなキャンペーンと施策がなされてきた。しかし、女性の就業率を高めても(同時に職場や育児環境の改善をすすめても)出生率は大きく回復することはなく、低下するのがトレンドとなってきた。夫婦間の子供数は夫が長く働く(おそらく専業主婦を持つ)家庭で多く、夫が家事育児に多くの時間を割いても出生数には大きな変化はみられないという。
後半は地域間比較である、まず国内の地方間の比較が行われている。国内の出生率が高い地域は、保守的な規範意識を持ち、女性の労働力率が低く、祖父母の育児支援が期待でき、雇用状況が良い(すなわち男性の働く場がある)という地域である。続いて国際比較がなされていて、教育への私的な支出が多い国の出生率が低く(東アジア)、子どもを持つ家庭への所得支援がある国(フランスなど)は日本よりは出生率が高いとのこと。
で解決策として提案されるのが、独身者や子無家庭から多くの子どもを持つ家庭への所得移転である。3人の子供を持つ家庭を全世帯の4割まで、二子の家庭を4割弱となるぐらいまで優遇すれば、出生率2.0に近づく。残りの2割となる独身者や無子世帯は多く税金を払う側で、彼らが求める生活水準および社会保障を長期に維持するうえで高い負担を求められるのは致し方ないというスタンスである。
すなわち、女性の社会進出と少子化対策は矛盾しており、後者を重視するならば専業主婦家庭を支援したほうがマシで、かつ支援をおこなうときそれは東京から地方への所得移転や移動の制限となる、こういうことだ。これはリベラルな立場からは後退に思える。個人主義と福祉国家が対立するというだけでなく、個人主義のためには福祉国家が必要だという見解が突きつけられるのだ。こういうわけで、まっとうな分析と提言ながら、明るい気分になれるものでもない。個人主義を重視すべく、福祉国家をやめるという立場はあるのだろうか。それは新自由主義というしろものになってしまうのか…。
日本の少子化の原因と対策について。学術書の体裁だが、データの議論の部分を飛ばして文字面だけを追うならば、一般の人にも論旨は分かると思う。「続」となっているが、正編に当たるのは『少子化論:なぜまだ結婚、出産しやすい国にならないのか』(勁草書房, 2013)である。著者は中京大学の教授である。
著者の議論はこう。福祉国家を維持したいならば、日本の人口数を維持する必要がある。移民による解決は社会に大きなストレスをもたらすので、現国民の出生数を増やす方向が良い。少子化の原因としては、未婚化と夫婦間の出生数の低下の二つが挙げられる。未婚化は、若年層の経済力の低下のためである。特に非正規雇用者の場合、正規雇用者と比べて出会いの機会もまた少ないため、結婚に至る確率が低くなっているという。
夫婦間の出生数の低下については、1990年代末から政府によって政策ターゲットとされ、共働き夫婦への支援となってさまざまなキャンペーンと施策がなされてきた。しかし、女性の就業率を高めても(同時に職場や育児環境の改善をすすめても)出生率は大きく回復することはなく、低下するのがトレンドとなってきた。夫婦間の子供数は夫が長く働く(おそらく専業主婦を持つ)家庭で多く、夫が家事育児に多くの時間を割いても出生数には大きな変化はみられないという。
後半は地域間比較である、まず国内の地方間の比較が行われている。国内の出生率が高い地域は、保守的な規範意識を持ち、女性の労働力率が低く、祖父母の育児支援が期待でき、雇用状況が良い(すなわち男性の働く場がある)という地域である。続いて国際比較がなされていて、教育への私的な支出が多い国の出生率が低く(東アジア)、子どもを持つ家庭への所得支援がある国(フランスなど)は日本よりは出生率が高いとのこと。
で解決策として提案されるのが、独身者や子無家庭から多くの子どもを持つ家庭への所得移転である。3人の子供を持つ家庭を全世帯の4割まで、二子の家庭を4割弱となるぐらいまで優遇すれば、出生率2.0に近づく。残りの2割となる独身者や無子世帯は多く税金を払う側で、彼らが求める生活水準および社会保障を長期に維持するうえで高い負担を求められるのは致し方ないというスタンスである。
すなわち、女性の社会進出と少子化対策は矛盾しており、後者を重視するならば専業主婦家庭を支援したほうがマシで、かつ支援をおこなうときそれは東京から地方への所得移転や移動の制限となる、こういうことだ。これはリベラルな立場からは後退に思える。個人主義と福祉国家が対立するというだけでなく、個人主義のためには福祉国家が必要だという見解が突きつけられるのだ。こういうわけで、まっとうな分析と提言ながら、明るい気分になれるものでもない。個人主義を重視すべく、福祉国家をやめるという立場はあるのだろうか。それは新自由主義というしろものになってしまうのか…。