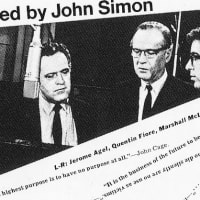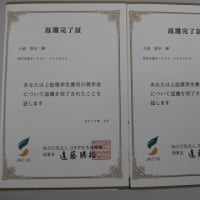河野哲也『問う方法・考える方法:「探究型の学習」のために』(ちくまプリマー新書), 筑摩書房, 2021.
高校生を対象として調べ学習の考え方・やり方を教えるという新書版。彼らを指導する高校の先生にとっても役に立つだろう。これと似たような主題の書籍に小笠原喜康・片岡則夫 『中高生からの論文入門』(講談社現代新書, 2019)がある。小笠原・片岡著が形から入る入門書だとすれば、この河野著は本質から入ろうとする内容である。著者は立教大学の哲学研究者で、著作も多い。
探究型学習とは何か、なぜ必要なのかという話から始まり、次に学習をどのように進めてゆけばよいか、さらに上手く考えてゆくにはどうしたらよいか、という順序で展開する。ここまでが全体の半分。残りの半分は、文献収集やプレゼンの仕方、レポートの書き方である。本書のオリジナリティは前半部分にあり、特に三章の「探求型の授業と哲学対話」が特徴的である。プレゼンやレポートを通じて探求を試みる主題について、どのように設定し・掘り下げ、かつどう論理展開をしたらよいか、あるいはどのような態度で挑むべきかについて、一通りのことが書かれている。一部を紹介すれば、ルールに従った対話を積み上げることが効果的となるとのことだ。
本書では、探求型学習というのが単に学習者の興味を埋めるだけの作業ではなくて、他者と情報共有を効果的に行うための作法を身に着ける目的もあるというメッセージが色濃くでている。この点で非常に倫理的である。本書で提示された心がけを授業内で守らせようとすると「小うるさい」感じになる恐れもあって、指導する教員側は生徒がアイデアを抑制したり発言に躊躇してしまわないよう気を付ける必要があるだろう。最初は形から入ったほうがよくて、生徒のスキルが上がってきたらこの河野著の段階かな。
高校生を対象として調べ学習の考え方・やり方を教えるという新書版。彼らを指導する高校の先生にとっても役に立つだろう。これと似たような主題の書籍に小笠原喜康・片岡則夫 『中高生からの論文入門』(講談社現代新書, 2019)がある。小笠原・片岡著が形から入る入門書だとすれば、この河野著は本質から入ろうとする内容である。著者は立教大学の哲学研究者で、著作も多い。
探究型学習とは何か、なぜ必要なのかという話から始まり、次に学習をどのように進めてゆけばよいか、さらに上手く考えてゆくにはどうしたらよいか、という順序で展開する。ここまでが全体の半分。残りの半分は、文献収集やプレゼンの仕方、レポートの書き方である。本書のオリジナリティは前半部分にあり、特に三章の「探求型の授業と哲学対話」が特徴的である。プレゼンやレポートを通じて探求を試みる主題について、どのように設定し・掘り下げ、かつどう論理展開をしたらよいか、あるいはどのような態度で挑むべきかについて、一通りのことが書かれている。一部を紹介すれば、ルールに従った対話を積み上げることが効果的となるとのことだ。
本書では、探求型学習というのが単に学習者の興味を埋めるだけの作業ではなくて、他者と情報共有を効果的に行うための作法を身に着ける目的もあるというメッセージが色濃くでている。この点で非常に倫理的である。本書で提示された心がけを授業内で守らせようとすると「小うるさい」感じになる恐れもあって、指導する教員側は生徒がアイデアを抑制したり発言に躊躇してしまわないよう気を付ける必要があるだろう。最初は形から入ったほうがよくて、生徒のスキルが上がってきたらこの河野著の段階かな。