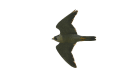■2019年2月~6月の広瀬川(ハヤブサの繁殖)【【レンズ】EF500Ⅱ,RF24-105
【観察日】2/10,3/5,3/19,3/31,4/2,4/7,4/13,5/19,5/25,6/11
【場所】広瀬川青葉山公園,評定河原橋から花壇
【種名】キジ,オシドリ,ヒドリガモ,マガモ,カルガモ,オナガガモ,コガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,カワアイサ,カイツブリ,キジバト,カワウ,アオサギ,ダイサギ,コサギ,イカルチドリ,イソシギ,ウミネコ,トビ,オオタカ,ノスリ,カワセミ,コゲラ,アカゲラ,アオゲラ,ハヤブサ,モズ,カケス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,キクイタダキ,ヤマガラ,シジュウカラ,ヒバリ,ツバメ,イワツバメ,ヒヨドリ,ウグイス,エナガ,センダイムシクイ,メジロ,オオヨシキリ,ムクドリ,シロハラ,アカハラ,ツグミ,ルリビタキ,ジョウビタキ,イソヒヨドリ,キビタキ,オオルリ,スズメ,キセキレイ,ハクセキレイ,セグロセキレイ,アトリ,カワラヒワ,マヒワ,ベニマシコ,シメ,ホオジロ,カシラダカ,ミヤマホオジロ,アオジ,ガビチョウ(32科66種)
【メモ】今シーズンのハヤブサは,2羽の巣立ちだった。やはり,3羽はいないとちょっと寂しいが,一人っ子の時もあるので,まあ,いいかという感じだ。ペアはどちらも交代していないと思うがどうだろうか。今年も桜の開花や澱橋のハクモクレンを楽しみにしていたが,ハクモクレンはやはり,一番よい日を逃してしまった。花びらはすぐ傷んで茶色くなってしまうので,毎日行ければいいがそうもいかないので,年によって写るものが違ってくる。カワアイサは5月19日まではペア一組がいたが,6月11日には見当たらなかった。桜は,開花寸前の3月31日に雪が降り,風景は美しかったが,蕾に氷がついた。こうなると,融けたからといってすぐには咲かないようだ。広瀬川の美しさの象徴と言えばやはり,ヤナギだろう。蒲生守る会の故木村フジさんのご主人で,昭和天皇の侍講も務められた故木村有香先生の研究について,学生の頃,先輩やフジさんからよく聞かされていたが,件のヤナギがこのあたりのヤナギだったという話も聞いている。東北大の植物園の研究室(今はないが)は,野鳥の会サークルの部室にもなっていて,内藤俊彦先生が顧問をしていただいた。1976年に始まる東北大野鳥の会時代から,植物園や牛越橋から評定河原橋までの一帯,特に,評定河原橋から花壇のあたりは一番好きな心安まるフィールドだ。今年も,よい自然の中を歩くことができて幸せな思いがした。
<木村有香先生について ウイキペディアより>
木村有香(きむら ありか、1900年(明治33年)3月1日 - 1996年(平成8年)9月1日)は、日本の植物学者。ヤナギ科の分類を大成した植物学者として知られているとともに、旧制第七高等学校造士館に在学中に原始的な形態を持ち生きている化石として知られるキムラグモを発見したことでも著名である。様々な地域の野生のヤナギを個体識別し、季節ごとに標本を採集し、同一個体から得られた標本を比較することで葉の形態の季節変異の著しいヤナギ科の分類の確立に努めた。初代園長を勤めた東北大学植物園(現・東北大学学術資源研究公開センター植物園)には木村の蒐集した世界のヤナギ科植物の標本木の充実したコレクションが栽培されており、木村は定年退官後も死去の前年まで、この植物園のヤナギ園で研究を続けた。
【写真】



カワアイサ♂ カルガモ コガモとオシドリ



シジュウカラ♀ ヤナギ ハヤブサ夫婦



カワアイサ



ジョウビタキ♂ 雪が溶けて氷に いつもの個体モズ♂



ホオジロ♂ アオジ♂ 3/31雪が降った広瀬川



気温があがりもや 評定河原橋付近 ヤナギの木



ヤナギ ♀抱卵中 いつものモズ



エナガが1羽だけで行動していた



エナガ



エナガ キジバト



シジュウカラ♂ ハクモクレン ハクモクレン



堤防散策路 まだいるカワアイサ サクラの蕾



ハクモクレン 白梅青葉山公園 経ヶ峰とサクラ



サクラ 外来種



カワアイサ カルガモ ハヤブサ♂


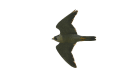
奥にもう一羽 巣の近くの♂ ハヤブサ♂



ハヤブサ♂ 旋回する 巣立ち後



長沼のスイレン ヒヨドリ 白梅

ハヤブサヒナ2羽
Copyright(C)2019 Shigenobu Aizawa All Rights reserved.