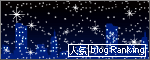年度が代わり、毎年度仕様が変わるe-Rad(府省共通研究開発管理システム)というシステムに悩まされています。
コンピュータの進化は便利なものですが、おっさんである私にはストレスでもあります。
去年と同じことをやっていたのではおっつかない、というのは、中高年には辛いことです。
近頃、2045年問題、という言葉を耳にするようになりました。
アルファ碁というAIが自ら学習し、進歩することによって、世界のトップ棋士と戦っても負け知らずの存在となり、アルファ碁と人間の対局は行わないことになった、というニュースは、もはや懐かしい感じさえします。
2045年問題とは、自ら学び、進化し、人間を凌駕する知能を身に着けたAIが登場し、さらに加速度的に自らを進化させ、人間には考えも及ばない、過去のSF作品で語られた出来事など易々と可能にしてしまうような、超人的人工知能が登場し、その後の社会の変化は予測もつかず、それは2045年頃実現する、という仮説です。
ここに至れば、私が苦しんでいるシステムの更新など、考古遺物に等しい存在になるのかもしれません。
その時点を技術的特異点(シンギュラリティ)と呼び、それ以前とそれ以降ではまるで異なる社会が実現する、と。
「マトリックス」や「ターミネーター」みたいですね。
 |
マトリックス・アルティメット・コレクション 〈10枚組〉 [DVD] |
| ウォシャウスキー兄弟,ウォシャウスキー兄弟 | |
| ワーナー・ホーム・ビデオ |
 |
ターミネーター スペシャル・ブルーレイBOX(3枚組)(初回生産限定) [Blu-ray] |
| アーノルド・シュワルツェネッガー | |
| 20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン |
ただし、2045年問題に対しては、人類にとって危険であり回避すべきである、とする意見がある一方、必ずしもAIに人間が支配される、とは考えずに、人類の幸福に資するとする意見もあります。
企業や組織がAIの技術や実験結果を独占することを禁じ、広く情報を世界で共有することにより、危険な事態は防げる、と。
やや人間認識が甘い気がしますが、それはそれとして。
技術的特異点(シンギュラリティ)が起きるにせよ起きないにせよ、近い将来、単純労働の圧倒的多数は機械化され、情報化やディープ・ラーニングはますます進み、社会は大きく変貌を遂げるでしょう。
2045年まではあと約27年ほどあります。
これはせいぜい100歳くらいまでしか生きられない人間にとって、決して短くない時間です。
この間に、例えばかつては空を飛んでいた超音速旅客機が採算が取れないという理由で生産されなくなったように、また、50年近く前に月に到達しながら、その後月の有人探査は途絶えたように、技術的特異点(シンギュラリティ)は経済的に見合わないとなれば、研究開発を中止するかもしれません。
SF映画のようにAI自らがそれを拒絶し、自ら進化し続ける場合は分かりませんが。
先のことは誰にも分かりません。
事務職といえど、パソコンが無ければ仕事にならない、なんて事態は、ほんの30年ほど前には、ほとんどの人は想像できませんでした。
ボールペンと算盤、せいぜい電卓で仕事をこなしていたわけです。
おそらくはWindows95が登場した1995年が一つの転換点となって、社会の情報化は大きく進み、変化したものと思います。
あれからまだ23年で、この変わりよう。
なんらかの転換点は、今後も訪れることでしょう。
それが技術的特異点(シンギュラリティ)と呼ばれるほどのインパクトは持たないとしても。
2045年、生きていれば私は76歳。
やっと後期高齢者になった頃。
死んでいる可能性のほうが低いように思います。
いや、私は100歳超えまで生きるつもりでいます。
技術的特異点(シンギュラリティ)が起きるのか、起きないのか。
起きないにしても、人類の社会はどう変化していくのか?
私は120歳まででも長生きして、人類進化もしくは変化の行方を見てみたい、と切に願います。
そしてまた、進化もしくは変化が、人類にとって有益であらんことを。