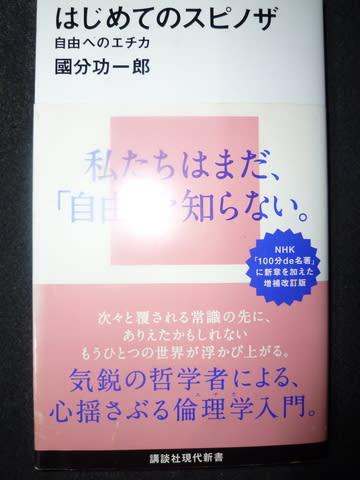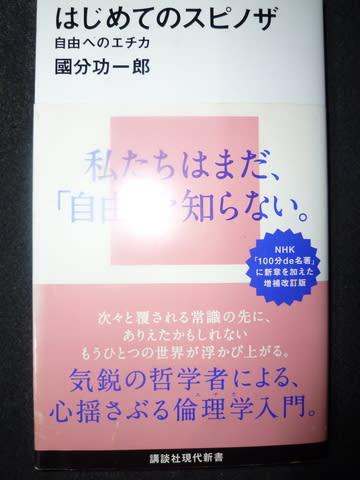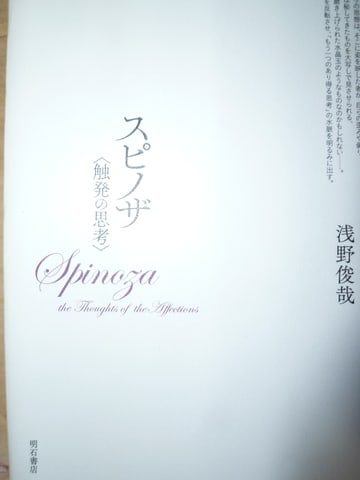スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
28日に平塚競輪場 で争われたヤンググランプリ2022 。並びは吉田‐菊池の関東,山口‐橋本の岐阜,町田‐松岡の西国,犬伏‐石原の四国で寺崎は単騎。第五部定理四二備考 の無知者について述べた部分で,スピノザは無知者は働きを受けるpatiことをやめると存在することもやめるといっています。ここの部分が何を意味しているのかを探求します。この点については『はじめてのスピノザ 』の中で國分も詳しい説明を与えていますが,ここではまずこの部分の何が問題になるのかということから明らかにしていきます。
昨日の伊東温泉記念の決勝 。並びは中野に大川,野原‐村田の近畿,嘉永‐山崎‐中本‐田中の九州で渡辺は単騎。広島記念 以来となる2勝目。このレースは嘉永の先行が有力。すんなりと駆けられてはほかのラインは苦しくなるのが明白。そのために野原は前で受けて飛びつくとという作戦を採ったのでしょう。その作戦がものの見事に決まっての優勝ですから,作戦勝ちといえる結果だと思います。山崎は番手から出ていくのが少し早すぎたような気はしますが,中本が3番手を守れなかったのが大きな痛手となりました。第四部定理六六備考 で示されている自由の人 homo liberです。これは異論がないところでしょう。第四部定理七〇 は,それ自体では無知の人びとと自由の人を対置しているとはいえないかもしれませんが,明らかに対比はしているのであって,したがってこの定理Propositioで無知の人びとといわれている人びとのことを,第四部定理六六備考でいわれている奴隷と同じ意味に解しても,問題はないでしょう。というか,この定理は,自由の人は奴隷たちの親切を避けようとするというように解して間違いないのであって,それはつまり,無知の人びとと奴隷は同じ意味であるということにほかなりません。一方,第五部定理四二備考 の無知者と第四部定理七〇の無知の人びとを異なった意味に解するのは無理があります。よって第五部定理四二備考の無知者と,第四部定理六六備考の奴隷は,同じ意味であるとして問題ありません。というより同じ意味であると解するべきでしょう。原因 causaから様ざまな仕方で揺り動かされるといっています。これは無知者の受動 passioを意味します。このことはそれ自体で明白でしょう。しかしこのことから重要なことが帰結します。というのは,第四部定理四 から理解できるように,現実的に存在する人間が働きを受けないでいるということはできないことになっているからです。これでみれば分かるように,現実的に存在するすべての人間は無知者であり奴隷です。他面からいえば,無知者にならずに現実的に存在する人間は存在しません。同じことですが,奴隷にならず現実的に存在し続けられる人間はいません。
昨日の広島記念の決勝 。並びは坂井‐田中の東日本,寺崎‐石塚の近畿,松浦に山田,犬伏‐久米の徳島で原田は単騎。岐阜記念 以来の優勝で記念競輪18勝目。広島記念は2018年 と2021年 に優勝していて連覇となる3勝目。ここはグランプリに出走する選手は地元の松浦以外は出走しませんでしたので,脚力は上位で順当な優勝。スピードは坂井の方が上だったのですが,うまく牽制して抜かせませんでした。道中で坂井の前に位置した立ち回りと,坂井のスピードを殺した牽制が勝因で,競走の巧みさによる優勝だといえそうです。結果的にラインは関係なく,脚力で優位に立つ選手が上位を独占したレースでした。第一部定義六 でいわれていることを理解していない人間には,神 Deusは存在するということを説明しても,その神が何を意味するのかということは分かってもらえませんから,結局のところその説明自体が無意味に帰すことになります。よって,スピノザの哲学のような,國分のいい方に倣えば僕たちが物事を考える場合にその影響を受けているオペレーションシステムとは別のオペレーションシステムについて考えていることを伝達するというときには,伝達する当の人間には不要であるような復習を繰り返さなければならない機会がそれなりに増加していくのは当然です。いい換えれば,自身が知識や技術を身につけていくことにはそれぞれに難易度の差があるのは当然ですが,それと同じように,それを伝達する場合にも,何を伝達するのかということによって,難易度に差があるのです。
11日の松戸記念の決勝 。並びは山口‐磯田の茨城栃木,松井‐岩本‐和田の南関東,中西‐三谷の近畿で高橋と上田は単騎。千葉記念 以来の記念競輪制覇で記念競輪4勝目。同年に松戸記念 も優勝していて,松戸記念は2年ぶりの2勝目。2011年に優勝した取手記念 も松戸での代替開催でしたので,記念競輪の4勝はいずれも松戸でのものとなりました。このレースは地元勢を引き連れた松井が,他の自力型よりも力量上位。なので前を取って突っ張った方が先行しやすいとみての作戦であったと思います。和田が1番車でしたから,ほかのラインあるいは単騎の選手たちにとっては仕方がない面もあったと思いますが,南関東勢の作戦勝ちというレースでしょう。デカルト René Descartesのオペレーションシステムとは異なるといっておきながら,そのことをデカルトのオペレーションシステムの下で説明しているというように批判したくなるのではないかと思います。実際にそのような批判が可能であるということは僕は否定しませんが,しかしそのような批判は不要であるとも僕は考えるのです。なぜなら國分はおそらくそのようなことは十分に承知した上で,このような説明をしているのだと僕は考えるからです。はじめてのスピノザ 』は入門書なのであって,それを手に取って読むという人の多くは,スピノザの哲学のことをよく知らない人だと思われます。そのような人はデカルトの形而上学の下で物事を考えるということが習慣化されていることが一般です。ですからそういった人たちからみれば,國分の説明というのは,不自然であるどころかむしろ腑に落ちるものだと思います。そこでこの説明によって,スピノザの哲学を学ぶときに,デカルトの形而上学の下で考えてはならないのであり,デカルトのオペレーションシステムとは異なったものとして,スピノザのオペレーションシステムを一から学ばなければならないという心構えをもつことができるのであれば,國分のその表現は,入門書における表現としては有効だといえるでしょう。ですから確かに國分はスピノザの哲学とは相容れないようなことをいってはいるのですが,そのことをとくに問題視しなければならないとは僕は考えません。
高松記念の決勝 。並びは真杉‐佐々木‐吉沢‐宿口の関東,簗田に香川,稲毛‐稲川‐南の近畿。
小倉競輪場 で争われた昨晩の第64回競輪祭の決勝 。並びは新田‐新山‐守沢‐成田の北日本,坂井‐平原の関東,郡司‐小原の神奈川で荒井は単騎。玉野記念 以来となる優勝でビッグは初制覇。このレースは北日本の並びが意味するところが僕には定かではありませんでした。新田が早めに駆けて新山が番手捲りというのは考えられましたが,守沢が自身の優勝よりも新山の援護に回ったのは僕には想定外でした。北日本が結束した結果としての優勝という色が濃いように思います。第一部定理一一備考 の冒頭でいっていることと比較すれば,便宜的なものであるといえるでしょう。他面からいえば,そこでスピノザがしたような説明が必要となるような探求は,あるいはもっと正確にいえばこれは探求そのものではなく探求の方法methodusは,というべきでしょうが,そうした探求の方法を僕は採用していないことになります。
富山競輪場 で行われた昨日の神秘の海・富山湾カップの決勝 。並びは根本‐飯野‐竹内‐泉の北日本,北井‐野口‐近藤の南関東,伊藤‐大塚の九州。ヤンググランプリ を優勝して以来のグレードレース制覇で,GⅢは初優勝となりました。このレースは北日本勢と南関東勢が二段駆けの並びで,飯野も野口もこのメンバーなら脚力は上位ですから,先行ラインの番手選手が有利だろうと思っていました。北井が早い段階から全力で駆けていったために,展開としては野口が有利だったのですが,近藤が離れてしまったのが誤算。このために根本の発進は防げたのですが,飯野の捲りには抵抗することができませんでした。最終周回のバックで根本がいけないとみてすぐに自力に転じた飯野の判断もよかったと思います。6月 よりも良化していました。これはやはり気候的なものの影響が大きかったと思います。それでも低血糖が頻発しているというわけではありませんでしたから,注射するインスリンの量を変更するという措置はありませんでした。低血糖を発症していたこと以外には異常はありませんでした。何の異常もなかったというのは2月 以来のことでした。12月 の通院のときに説明したように,自己管理ノートは形式が変わっていたので,1冊を使用することができる期間が短くなっていたのです。ただ実際には8ヶ月でしたので,このときにもらったノートを使い始めたのは9月になってからです。
昨晩の四日市記念の決勝 。並びは坂井‐守沢の東日本,小原‐福田の神奈川,橋本‐浅井‐坂口の中部,古性‐村田の近畿。別府記念 以来となる記念競輪3勝目。四日市記念は初優勝。この開催は平原が二次予選で敗退となったため,古性と浅井が上位で坂井がそれに対抗するという決勝に。小原がどのような動きをするのかがひとつのカギになるかもしれないと思っていましたが,結果的にその動きが古性にとってやや不利になりました。橋本が不発となったために浅井も余裕をもって捲りにいくことができなくなったので,先行した坂井の番手を得た守沢が有利となりました。守沢は優勝は多くありませんが,安定した成績を残していて,まだ上位で戦い続けることができそうです。預かり金精算書 は,書類ですから,利用者と保護者,つまり妹と僕のサインと捺印を入れて送り返す必要があるものです。ですからこの日に妹と僕の署名と捺印をして送付しました。妹は上手とはいえませんが字を書くことはできます。ですからこのように妹が家にいる場合は,僕は妹自身に署名をさせます。僕が代筆するのはそうでない場合だけです。また,これは前にいったことがあるかもしれませんが,僕は通所施設に渡す必要がある書類については郵送はせず,妹を送ったり迎えに行ったりしたときに通所施設にある事務所の職員に手渡します。ですがグループホーム に渡す必要がある書類に関しては郵送することにしています。これは事務手続き上の書類であって,グループホームに関する手続きは,グループホームを運営している福祉法人が行うものであり,その手続きをする事務所というのは,通所施設の事務作業をする事務所と同一です。ですからグループホームの書類に関しても通所施設で手渡すということは可能です。それでも僕は通所施設に提出する書類とグループホームに提出する書類とでは,その提出の方法を変えています。この預かり金精算書はグループホームの書類ですから,郵送しました。なお,こうした書類には必ず返送用の封筒が入っていますので,郵送費を僕が負担するということはありません。受給者証 のコピーが送付されたという通知でした。
6日の防府記念の決勝 。並びは吉田‐神山の茨城栃木,郡司に佐藤‐永沢の北日本,清水‐桑原の山口に園田で東口は単騎。ウィナーズカップ 以来の優勝。記念競輪は昨年の防府記念 以来となる8勝目。防府記念は2018年 ,2019年 ,2020年 も優勝していてこれで五連覇となる5勝目。このレースは清水にとって最大の強敵は郡司。その郡司が園田の斜行によって落車となりましたので,幸運な面があったのは事実です。ただ,吉田の上昇に先んじて動いて郡司を叩くことによって,吉田ラインの3番手を取ったのはいい作戦でした。仮に郡司が捲ってきたときに,それに合わせて出ることができたかどうかは分かりませんが,作戦面での勝利ということはできるかと思います。根岸町 にあるクリニック です。ただし,僕が接種したときは武田/モデルナ製のワクチンでしたが,妹の予約を入れた日のワクチンはファイザー製でした。つまり同じクリニックでも,日程によって異なった種類のワクチンを接種していたということです。妹の場合はやはり副反応が生じることに大きな不安があり,その点ではすでに2度の接種を終え,発熱以外の副反応を起こしていなかったファイザー製のワクチンを接種するというのは,悪くない選択でした。支援計画書 を作成してもらっているKさんからの郵便物が届いていました。内容は,Kさんが勤務している福祉事業所の名称が変更になるので,契約を改めて結び直す必要があり,そのために妹の受給者証のコピーを送付してほしいというものでした。ただ,僕は妹の受給者証はグループホームに預けてありますので,すぐに対応することはできませんでした。
京王閣記念の決勝 。並びは吉田‐坂井‐高橋の関東,森田‐平原‐宿口‐中田の埼玉で,佐々木と北井は単騎。ドームスーパーナイトレース 以来となるGⅢ2勝目。記念競輪は初優勝。このレースは埼玉勢が4人で結束しましたので,森田の先行が有力。ただ早い段階からの先行になったので,番手を回った平原にはあまり余裕がなかったようです。坂井を牽制しての動きではありますが,宿口のために内の進路を開けたとも受け取れますので,自身が優勝できなくても埼玉勢から優勝者が出ればよいという考えが平原にはあったのではないかと思います。そういう意味では森田の頑張りと平原のアシストを受けての宿口の優勝だったということになりそうです。第二部自然学②公理一 から理解できるように,現実的に存在するAという物体corpusとBという物体が関係することによってAという物体に何らかの運動motusが生じるとき,この様式はAという物体の本性 naturaからと同時にBという物体の本性から生じます。この場合でいえば,僕の腕の痛みというのは,僕の腕の本性と同時に注射したワクチンおよび注射器の本性から生じるのです。一方,この接種によって妹の腕に何らかの運動が生じる場合にも,それは妹の腕の本性とワクチンおよび注射器の本性から生じるのです。なので,同じ注射器で同じワクチンをほぼ同じ腕の部位に接種したとしても,僕は腕に痛みを感じ,妹は痛みを感じないということは,絆創膏の処置をどうするかということとは無関係に生じ得ることです。僕の腕の現実的本性 actualis essentia,もっといえば僕の身体 corpusの現実的本性と,妹の腕あるいは身体の現実的本性は,異なった現実的本性であるからです。
前橋競輪場 で開催された昨日の第31回寛仁親王牌の決勝 。並びは新田‐小松崎‐守沢の北日本,吉田‐平原の関東,古性‐稲川の大阪,松浦‐井上の西国。新田祐大選手 は前回出走の西武園のFⅠから連続優勝。ビッグは2019年のオールスター競輪 以来の優勝で11勝目。GⅠは9勝目。このレースは吉田が先行するのではないかと思っていました。後方から追い上げていったときは吉田もその気だったと思いますが,稲川の後ろに入れる形になったのでそこに入ることになり,古性の先行に。松浦はおそらく捲り切るだけの余力はなかったので平原の内に入ったのだと思います。新田としては外に出せない最悪の位置になりましたが,インからの進出が決まりました。これは古性の走法によるものなので幸運だったというべきであり,この形での優勝では,まだ完全に復調したとはいいきれないように思います。2月 よりは低下していました。ただ,低血糖が多くなっていて,全体の5.7%を占めていました。とくにどの時間が多いというわけではなく,就寝前には0でしたが,その他の時間帯,すなわち朝食前,昼食前,夕食前には万遍なく出ていました。なので持続効果型のインスリンであるトレシーバの注射量を,0.01㎎減らすという措置を講じることになりました。厳冬期はすでに過ぎ,これからは気温も徐々に高くなってきますので,その点も踏まえての措置だったと考えてください。12月 に出て以来の異常です。そのときに詳しく説明したように,僕のアルブミンは平均値より低い値でずっと推移していて,定期的に下限値を下回るという異常が出ます。この日がそれに該当したということです。2013年6月 の通院のとき,150という数値が出ていて,これは上限値です。それ以外は数値ではなくNORMALと記されているか,そうでなければ判定不可と記入されているかのどちらかでした。これは尿の中のクレアチニンにどの程度のたんぱく質が含まれているのかを示す数値で,このときに高くなった理由というのは分かりません。腎機能に関連する数値と思われますが,主治医からも何も言われませんでした。
松山競輪場 で争われた昨晩の道後温泉杯争覇戦の決勝 。並びは根田‐福田の南関東に阿部,稲毛‐森川の近畿中部,佐々木‐渡辺‐坂本の西国で杉森は単騎。グループホーム の間の連絡は,緊急の事項でない限り,この連絡帳でやり取りされます。妹が帰宅したときは,家にいた間の妹の様子などを記入して,通所施設へ持参し,出迎えた妹の担当者に渡します。ところがこの日は,記入はしたもののその連絡帳自体を持参するのを忘れてしまいました。往復 にはバスを利用しています。上大岡駅でバスを乗り継ぐのですが,持参し忘れたことに気付いたのは上大岡駅で乗り継ぎのバスを待っているときでした。上大岡駅まで来てしまっていましたから,とりあえず妹と通所施設まで行き,妹を担当者に預けた後,また家に戻り,忘れてしまった連絡帳を持参して再び通所施設へ行きました。到着したのが13時前後になりましたが,僕が通所施設の玄関を入ると,施設長のNさんがいましたので,連絡帳と,28日に帰宅したときに送付されていた受給者証 を渡して帰りました。
松阪記念の決勝 。並びは皿屋‐浅井‐坂口の三重,三谷‐山田‐の近畿に岡,太田‐大塚の西国で諸橋は単騎。高松記念 以来の4勝目。松阪記念は初優勝。この開催はS班の選手が準決勝で総崩れ。決勝のメンバーでは浅井,太田,三谷の3人が上位。浅井が皿屋マークのレースでしたので,皿屋次第で結果も変わってくると予想していました。太田はたぶん皿屋が叩き返しに来ると思っていたのではないかと推測しますが,3番手を取った三谷がうまく走ったため,発進できませんでした。このあたりは皿屋はまだ経験が不足していたということでしょう。3番手を取って後ろも牽制した三谷がうまかったというレースで,三谷をマークした山田が有利になったという結果でした。第一部公理三 は,自然のうちに因果論が貫徹されるということを意味していて,これが公理 Axiomaとして示されるということは,共通概念notiones communesとして知られる事柄であるという意味ですから,それ以上の意図はありません。いい換えればそこにほかに何らかの狙いが含まれているというわけではありません。ただ,この因果論が貫徹されると,目的論は結果的であるとしても完全に排除されるのです。実際にスピノザは第一部の付録 で,自然は何の目的も立てないし,目的原因causa finalisというのは人間の想像物と断定しています。弁証法は最終形態を少なくとも想定することはできるのであって,その最終目的へ向かって運動するのですから,これは明らかに最終形態が目的原因となっているといえるでしょう。したがって実はスピノザは,このようにいうことで弁証法を方法論的に無効であると宣言しているといえるのです。よって,仮にスピノザの哲学に主体subjectumという概念notioが欠如していないとしても,弁証法はスピノザによって無効化されます。目的原因は想像物であるのですから因果論が適用されなければならず,第一部公理三および第一部公理四 により,方法としては演繹法 が適用されなければなりません。スピノザ〈触発の思考〉 』に関連する考察はここまでにして,また日記に戻ります。
久留米競輪場 で行われた昨日の熊本記念の決勝 。並びは小松崎‐守沢‐佐々木‐高橋の北日本,深谷‐郡司の南関東,松浦‐村上の西日本で松岡は単騎。共同通信社杯 からの連続優勝。記念競輪は4月の川崎記念 以来になる14勝目。熊本記念は一昨年 も制していて2年ぶりの2勝目。このレースは郡司と松浦が強力。郡司は深谷マークのレースになりましたので,深谷がどういうレースをするかで結果が左右されることになると思っていました。その深谷が前受けからすぐに引いて早めに巻き返すというレースをしたので郡司が有利に。松浦の捲りに対して番手捲りで対抗するのではなく牽制してストップさせましたので,番手選手としての仕事も果たした上での優勝ということになり,深谷とのワンツーにはならなかったものの価値は高かったと思います。このような展開になればこういう結果は大いにあり得るところで,配当がつき過ぎたという感があります。個物 res singularisの複合の無限連鎖 が形而上学的に支えるということは,スピノザの哲学に個物の複合の無限連鎖という考え方があるので,それに基づく政治論が抽出されるということを意味します。つまり,ヘーゲルGeorg Wilhelm Friedrich Hegelの哲学に弁証法があるためにヘーゲルの政治論が成り立つのと同じ関係が,複合の無限連鎖とスピノザの政治論との間にあると僕は考えているのです。そしてこのためにスピノザの政治論では国家Imperiumが人間にとってあるいは人類にとっての最終形態とはならず,そしてそのゆえに,浅野がいうように,スピノザの政治論では,社会的地平から国家の問題を照射する道が開かれているのです。第二部自然学②補助定理七備考 で複合の無限連鎖を説明している事柄から理解することができると思います。
向日町記念の決勝 。並びは坂井‐成田‐小原の東日本,脇本‐稲川の近畿,清水‐桑原‐筒井‐小倉の中四国。オールスター競輪 以来の優勝。GⅢは6月の燦燦ムーンナイトカップ 以来で通算11勝目。記念競輪は3月の玉野記念 以来で10勝目。向日町記念は昨年 からの連覇で2勝目。このレースは脇本が脚力上位。清水のラインが4人になりましたが,ライン全体があまり強力ではありませんでしたから,脇本が相当の確率で優勝するだろうとみていました。残り2周のホームではかなり後ろに置かれましたが,そこから巻き返してかまし先行に持ち込み,さらにそのまま粘ったのですから,やはり力が抜けていての優勝だったと思います。