ここまで深刻「食のデフレ」:上野泰也(みずほ証券チーフマーケットエコノミスト)(1)(Voice)
筆者はこのコラムの第3回「地銀の危機と道州制」で、地方経済の苦境と強いデフレ圧力を示す事例として、鹿児島の290円弁当をご紹介した。ところがその後、こうした格安価格の弁当は、東京の都心を含む全国各地に出現するようになった。「食のデフレ」はいまや、全国区の現象になったといえるだろう。
インターネットで調べてみると、もっと安い250円の弁当が、東京・浅草や名古屋、京都で売られている。大手持ち帰り弁当チェーンは、「のり弁当」を290円で提供している。おにぎりの値下げキャンペーンをよく行なっているコンビニエンスストアでは、お弁当の価格帯も下がり気味である。
筆者がもっとも驚いたのは、大手スーパーの一角である西友が4月から「ハンバーグ弁当」などを298円で販売しはじめたことである。筆者も試しに買ってきて食べてみた。率直な感想としては、とくにおいしいというわけではないが、この値段ならば文句はいえない、といったところか。
後日の新聞報道によると、この298円弁当は当初計画を超える順調な売れ行きとなっており、販売元のスーパーでは、次はコロッケを50円未満で売り出すなど惣菜の販売価格帯を引き下げるという。
(中略)
外食産業でも、低価格が消費者に受け入れられるかたちで、ファストフードの独り勝ちが目立っている。日本フードサービス協会が発表している外食産業の市場動向データ(全店ベース)によると、ファストフードの売上高は、今年5月まで8カ月連続で前年同月比プラスになった。一方、ディナーレストランは14カ月連続、ファミリーレストランは6カ月連続でマイナスになっている。
このほか、喫茶は7カ月連続のマイナス。ファミリーレストランでは、価格帯の安い店舗ブランドへの切り替えや、メニュー全体の値下げ、サラダを88円で提供する動きなど、さまざまな経営努力が行なわれている。だが、雇用と収入の不安に突き動かされた消費者による「聖域のない」支出絞り込みと、「食のデフレ」進行のさなかで、苦戦を強いられているのが実情である。
平日は昼休みの食事くらいしか楽しみがないものですし、金額の小さなもので節約する趣味はないですから、ランチには割とお金を落としています。景気回復のための涙ぐましい努力です。都心からはちょっと外れた微妙なところに勤務しているので近隣にファストフードのチェーン店が少ないというのもありますけれど、まぁ時給の半分くらいは昼食に費やしてます。しかるに節約志向の波は嗜好品にとどまらず、生活必需品たる食べものの世界にも及んでいるようでして、格安商品が「まともな価格」の商品を駆逐しているのが現状のようです。これは深刻。そこまで節約しないと生きていけない人が増加傾向にあるのは事実なのでしょうけれど、幸いにして多数派を形成するには至っていないはず、必要もないのに趣味で節約している人が多いような気もします。贅沢は敵だ?
先日、NHKのニュース番組が、東京・池袋で行なわれている弁当価格の引き下げ競争を特集していた。消費者の求めに応じて少しでも安い弁当を提供しようと、人件費の節約に加えて、まとめ買いによる食材の低価格での仕入れ、容器のコストを少しでも安くするための工夫など、裏では大変な努力が行なわれていることが紹介されていた。しかしそれでも、値段の引き下げ努力には限界があると、弁当屋の主人は率直に語っていた。
それでまぁ、消費者の低価格志向に応えるために、製造者側はコストの引き下げに走る、そうした中ではまず人件費が引き下げられ、仕入れ値が引き下げられることによって、仕入れ先もまたコスト削減の圧力に晒され、やっぱりそこでも人件費が引き下げられる、そうして働く人の収入は減少の一途をたどり、それに応じて低価格の商品ばかりを追い求めるようになる、ごくごく単純化すればそんなところでしょうね。この辺の連鎖をいかに断ち切るかが、重要になってくるわけです。
消費者の側は、支出の絞り込みにのみひたすら努力するべきではない。同時に、少しでも収入の上積みを図るための努力や工夫をすべきである。
先日、プールの監視員をしている大学生と話していたところ、厳しい練習のおかげでライフセーバーの資格を取得できたので、アルバイトの時給が50円上がったと、喜色満面で教えてくれた。
日本経済がデフレスパイラル的な悪化に陥らないためには、こうした前向きの努力の積み重ねが欠かせない。
……で、引用元はPHP教団が出版している雑紙ですから色々と限界があって、このような自助努力論で締められています。アルバイトの時給が50円増えただけで将来に希望が持てるかは甚だ微妙ですが、それでもこれは極めて例外的な「幸運な事例」に過ぎないでしょう。実際のところ、努力したところでそれが報われるとは限らない、長年真面目に勤め上げて仕事の腕を磨いても、給料据え置きならまだマシな方、経営悪化を理由に給与引き下げを言い渡されたり、果ては人員整理と称して退職を迫られたり、そういうケースも多いです。そして何より、この「努力」と積み重ねることで労働力の値段は落ちてしまうのですから!
製品の品質が上がっても、それに見合った販売価格の増加が見られないのであれば、それは価値が下がったということです。たとえば2000mAh充電できるバッテリーが500億ジンバブエドルで売られていたとしましょう。そこに開発費を投じて、新たに3000mAh充電できるバッテリーを作ったとします。しかし、その結果として2000mAhしか充電できない旧製品の需要が下がり、460億ジンバブエドルまで価格が下落、一方で新製品が高く売れたのは最初の1ヶ月だけ、結局のところ500億ジンバブエドルに落ち着いてしまうとしたら? 人間と労働の場合にも、同じことが起こります。給料が上がらないのに頑張って働く量を増やせば、労働量あたりの単価は下がる、労働の「値段」は下落してしまいます。これぞデフレですね。日本が嵌り込んでいる状態は、まさにそういうものです。良いものまで安く売られてしまう状況を打破しませんと。
「ビッグマック指数」、そして「マックジョブ」という言葉があります。よほど特殊な国でもなければ世界中どこにでもあるマクドナルド、色々なものの指標として使われるわけです。「ビッグマック指数」とはビッグマックの価格を用いた経済指標であり、「マックジョブ」とは低賃金で将来性のない単純労働を指す言葉ですね。そして日本の場合「ビッグマック指数」が小さい、ビッグマックの価格が他の先進国と比べて大幅に安いわけですが、同時に「マックジョブ」の給与もまた低いわけです。どちらも、先進国と呼ぶにはかなり微妙な水準にある……
日本はビッグマックの価格が安いから、マックジョブの給与が低くてもビッグマックが食べられる、そう思えば国内的には完結しているように見えるかもしれませんが、そこで内向きになったまま世界に取り残されているのが日本経済でもあるような気がします。ここはやはり、双方を引き上げること、食品にまで及ぶ低価格志向に歯止めをかけ、マックジョブの賃金を――最低賃金を――大幅に引き上げる、日本の経済水準に見合ったところまで引き上げることがデフレ脱出の必須要件になるのではないでしょうか。











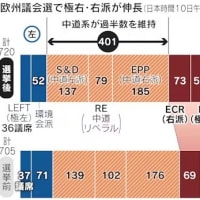


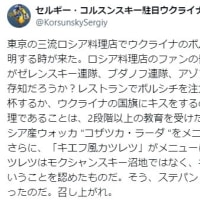

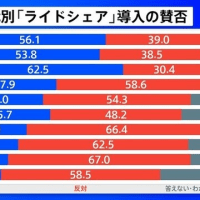
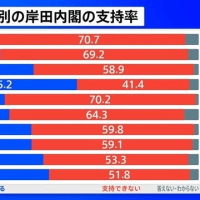
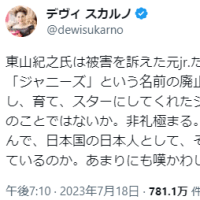
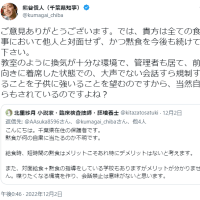
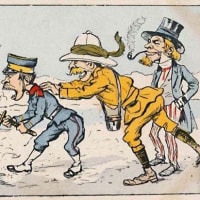






引用記事について言えば、
>少しでも収入の上積みを図るための努力や工夫をすべきである
のは、消費者=労働者ではなくて、その生活を保障する責任を負った「国」ですね。そしてそれをさせるために消費者=労働者側が、「安いものを見つけて何とかしてる俺勝ち組(?)」という思考を何とかしなきゃいけないのも確かなんですよね・・・って頭が"選挙向け"になってるなぁ(苦笑)。
それにしても残業時間の総量規制もないし、過労死を起こした企業名の公表も政府は拒否しているなんて…。日本の労働政策は19世紀の英国なみとしか思えません。
国民が悪い方に適応していると言いますか、無策な国でも生きられるように進化した結果がこうなのかも知れません。国がまともな社会保障を用意しないから、国民は自助努力でどうにかしようとする、その結果として安物志向が強まって経済がなおさら低迷して、と。
>七詩さん
何しろ日本は、労働者側も経営者目線でしか物事を考えられない国ですから。残業を規制して最低賃金を上げて……労働者側からすれば当たり前のことですが、不思議と「それでは経営が成り立たない~」と、そんな声が経営者以外からも聞こえてくる、そんな有様を反映しているのでしょう。
一方で、日本人は箱物が好きです。「食・住」あとは高級オーディオ・ホームシアター、自動車、最近では高額自転車なども。
やはり日本人はハードが好きな民族と虚栄心が合わさった結果なのでしょうか?
「もの作り」という面では、車も料理も同じものだと思うのですが、日本では形の伴わないもの、すぐに消えてしまうものを低く見る傾向があるように思えます。
映像業界では料理を「消え物」といいます、実績が実物になって残らない業種を「水物」ともいいます。同様にハードを動かす事に不可欠な「ソフト」の評価も低い事を考えると、日本人の国民性なのかなとも思ったりしますが。
「代価消費」という言葉があります。仕事や人生がつまらないと、「形ある物」に投資をしてしまう事らしく、私もその傾向がややあります。昔から貧乏人ほど物を買うといいますが、物を買うから自分への投資が出来ない、ローンで会社も辞められない、「低所得のスパイラル」が続きますね。まあ、これが日本を支えてきたと言ってもいいのですが。
「住」に関しては他の2つに比べて売り手が圧倒的に強いので価格が保たれている気がしますね。「衣」に関しては結構な価格破壊が進んでいますけれど、嗜好品が牽引している部分もあるでしょうか。そうなると「食」が削られやすいのかもしれません。たしかに、ものづくり原理主義の社会では形の残りにくいものは低く評価されそうですし(もっとも、それでもマシな方ですが)。
プライベートブランドをどこ彼処でも見かけますが、「人件費を削っているんだろうな」という思いがあります。
少しでも買うようにすれば、その製品に関わった人々が救われるという淡い期待を持てるのですが、実行できません。必要であれば無理のない範囲で買うことはできますが、家族がその手の商品に対して「安かろう悪かろう」のイメージを持っているので厳しい状況です。家族が抱くイメージもある意味で正論なのかもしれませんが。
おこがましい内容もありましたが、私なりに思うところを投稿します。
消費者からすれば安くて良いものはありがたいですが、その陰で人件費が容赦なく削られているとしたら、いずれ巡り巡って自分の首をも絞めることになりますよね。安物でも商品を買うことが生産者の利益になるかもしれませんが、安物を買うことでより市場が低価格方向へとシフトしていったり……
コメントはとても勉強になってます。
さて、私は七詩さんのコメントに心打たれました。低価格競争とは人件費削減競争です。
現場で働く者にとっては人件費削減はとても悲しいことです。仲が良かった人が会社の方針で辞めさせられた。さて、残された能力だけある人、仕事ができる人だけでいい製品、良質でお客さんが満足する商品が作れるか?できるように思います。しかし、できません。自分は大切なのは「人」だと思います。感情、思い、情熱、人は機械にはならない。しかし、だれかが最初にリスクを負わなければ解決しない。みんな自分がかわいく、生きるのに必死で、他人のことなど関係ない。しかし口ではもっともな御託をならべる。結局、だれか行動できる人を待っている状態です。他力本願日本人。