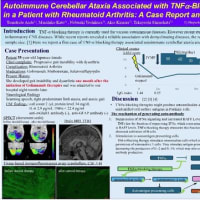「医学のあゆみ」誌では「医師のバーンアウト(燃え尽き症候群)をふせぐためには?―脳神経内科領域の取り組みから学ぶ―」というタイトルで,計10回にわたり,議論を行ってきた.そのなかで個人的に重要と思われた点について列挙する.シンポジウムに参加される方はぜひご確認いただきたい.
【バーンアウトを巡る状況】
1)燃え尽き症候群とバーンアウトは異なる.前者にはやり切った感のイメージが背景にあるのに対して,後者にはそれがない.議論する医師の状況は「バーンアウト」である.
2)海外で医師のバーンアウトに関する研究論文が急増した背景には,医師のサービス業および経済的な側面が重視されるようになり,ストレスフルな職業に変化したためと考えられる.
3)海外,とくに米国神経学会が行っている変革,つまり個人がさまざまなストレスから身を守るためのレジリエンスを鍛える試みや,リーダーシップ教育は本邦でも積極的に取り入れていくべきである.
4)本邦ではようやく医師の過重労働が注目されるようになったものの,バーンアウトについてはほとんど注目されていない.
【バーンアウト対策】
1)若手医師はバーンアウトのリスクを理解して研鑽を積むこと,組織からの支援として,診療の自主性(autonomy)を持たせること,および専門性向上の機会を与えることが有益である.
2)急性期病院におけるバーンアウト対策は,個人でできるものは限られ,病院や地域,国レベルでの対策を要する.
3)大学医師のバーンアウト防止も個人の努力では限界があり,教授等がリーダーとなり組織内で十分な検討を行うこと,そしてリーダーシップ教育が必要である.
4)女性医師のバーンアウトでは個人要因と環境要因があり,後者では我慢が美徳とされ,育児や介護は女性が行うのが当たり前とされる日本独特の文化や,米国と同様に,医局や職場の中で生じるハラスメントがある.
5)脳神経内科医にバーンアウトが多い要因として,医師数と比べて患者数が多いこと,他者の人生に濃密に関わる必要があること,その一方で急患対応が多いこと,書類が多いことがある.
6)それぞれが「自らの幸福とはなにか」を理解することがレジリエンスの強化,バーンアウトへの対策になる.
7)地方で勤務する若手医師のバーンアウト防止に医局の役割は大きく,①経済的保障,②地方診療に貢献した若手を,優先的に都市部の病院に戻す仕組み,③研究留学等を優先的に配慮する仕組み,④学会研究会での役割や発表機会を積極的に与える仕組みをつくることが挙げられる.
8)バーンアウトは精神医学の立場からは正式な診断名ではなく,うつ病のように重度の機能障害を呈する精神疾患から,軽度の機能障害を呈するものの精神疾患とは言えない状態まで含む幅広い概念である.バーンアウトをした医師のほとんどが後者に含まれ,機能障害は軽いため,休むこともなく業務はするものの,脱人格化に陥っている.上司はどのように対応し,労働環境を変えるべきかが分からなくなり,精神科医に相談を行う.精神科医が関わるのはこのようなケースと,重度の機能障害を呈する精神疾患を背景としたケースである.
9)バーンアウトの3症状「情緒的消耗感,脱人格化,個人的達成感の低下」は同時に,並列に生じるものではない.つまり「情緒的消耗感」の段階から,患者さんに対して非人間的な対応をとり,無関心や思いやりに欠ける言動などをする「脱人格化」に至るには「職業人・人間としての倫理観」という大きなストッパーがある.すなわち,このストッパーが機能している情緒的消耗感を呈している早期の段階(Burning out)にある医師を見出し,介入を行い,Burned out,さらには重度の機能障害に進展することを防止するためのさまざまな対策が必要である.
【バーンアウトを巡る状況】
1)燃え尽き症候群とバーンアウトは異なる.前者にはやり切った感のイメージが背景にあるのに対して,後者にはそれがない.議論する医師の状況は「バーンアウト」である.
2)海外で医師のバーンアウトに関する研究論文が急増した背景には,医師のサービス業および経済的な側面が重視されるようになり,ストレスフルな職業に変化したためと考えられる.
3)海外,とくに米国神経学会が行っている変革,つまり個人がさまざまなストレスから身を守るためのレジリエンスを鍛える試みや,リーダーシップ教育は本邦でも積極的に取り入れていくべきである.
4)本邦ではようやく医師の過重労働が注目されるようになったものの,バーンアウトについてはほとんど注目されていない.
【バーンアウト対策】
1)若手医師はバーンアウトのリスクを理解して研鑽を積むこと,組織からの支援として,診療の自主性(autonomy)を持たせること,および専門性向上の機会を与えることが有益である.
2)急性期病院におけるバーンアウト対策は,個人でできるものは限られ,病院や地域,国レベルでの対策を要する.
3)大学医師のバーンアウト防止も個人の努力では限界があり,教授等がリーダーとなり組織内で十分な検討を行うこと,そしてリーダーシップ教育が必要である.
4)女性医師のバーンアウトでは個人要因と環境要因があり,後者では我慢が美徳とされ,育児や介護は女性が行うのが当たり前とされる日本独特の文化や,米国と同様に,医局や職場の中で生じるハラスメントがある.
5)脳神経内科医にバーンアウトが多い要因として,医師数と比べて患者数が多いこと,他者の人生に濃密に関わる必要があること,その一方で急患対応が多いこと,書類が多いことがある.
6)それぞれが「自らの幸福とはなにか」を理解することがレジリエンスの強化,バーンアウトへの対策になる.
7)地方で勤務する若手医師のバーンアウト防止に医局の役割は大きく,①経済的保障,②地方診療に貢献した若手を,優先的に都市部の病院に戻す仕組み,③研究留学等を優先的に配慮する仕組み,④学会研究会での役割や発表機会を積極的に与える仕組みをつくることが挙げられる.
8)バーンアウトは精神医学の立場からは正式な診断名ではなく,うつ病のように重度の機能障害を呈する精神疾患から,軽度の機能障害を呈するものの精神疾患とは言えない状態まで含む幅広い概念である.バーンアウトをした医師のほとんどが後者に含まれ,機能障害は軽いため,休むこともなく業務はするものの,脱人格化に陥っている.上司はどのように対応し,労働環境を変えるべきかが分からなくなり,精神科医に相談を行う.精神科医が関わるのはこのようなケースと,重度の機能障害を呈する精神疾患を背景としたケースである.
9)バーンアウトの3症状「情緒的消耗感,脱人格化,個人的達成感の低下」は同時に,並列に生じるものではない.つまり「情緒的消耗感」の段階から,患者さんに対して非人間的な対応をとり,無関心や思いやりに欠ける言動などをする「脱人格化」に至るには「職業人・人間としての倫理観」という大きなストッパーがある.すなわち,このストッパーが機能している情緒的消耗感を呈している早期の段階(Burning out)にある医師を見出し,介入を行い,Burned out,さらには重度の機能障害に進展することを防止するためのさまざまな対策が必要である.