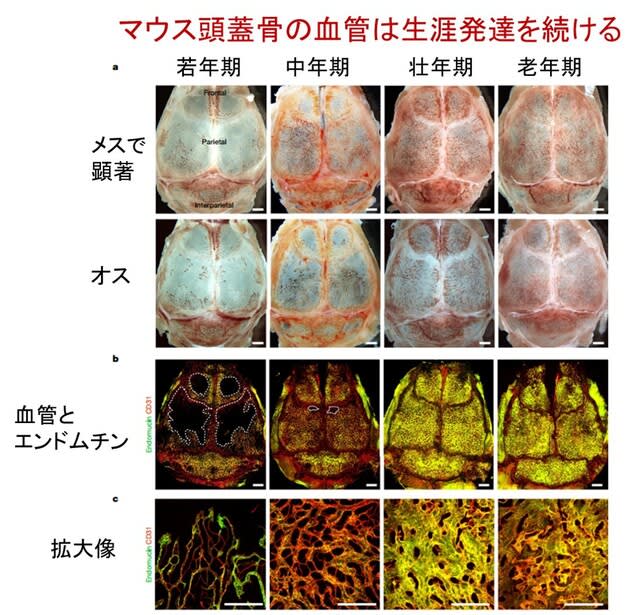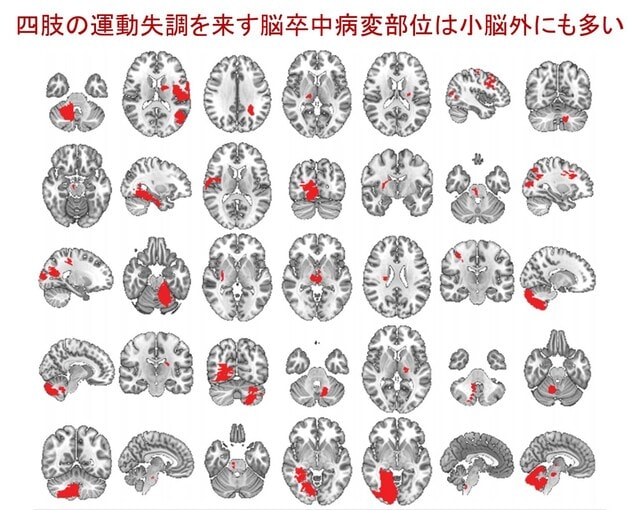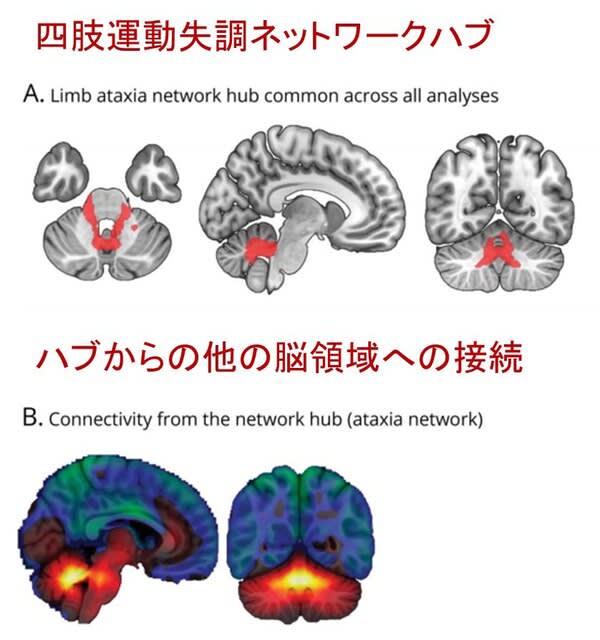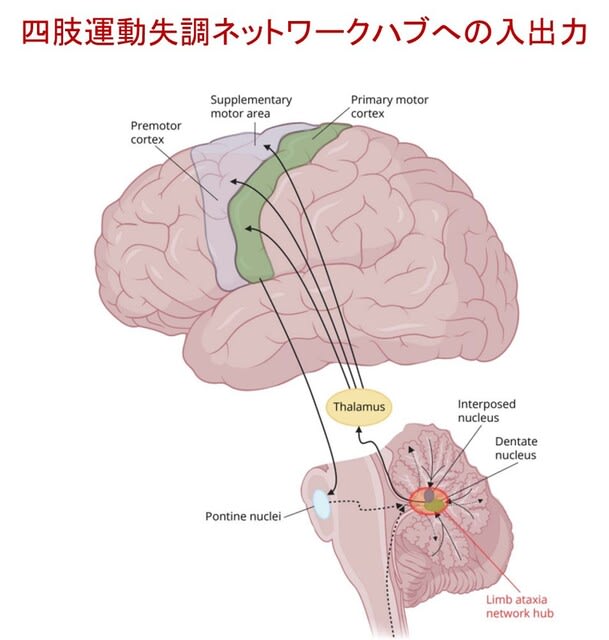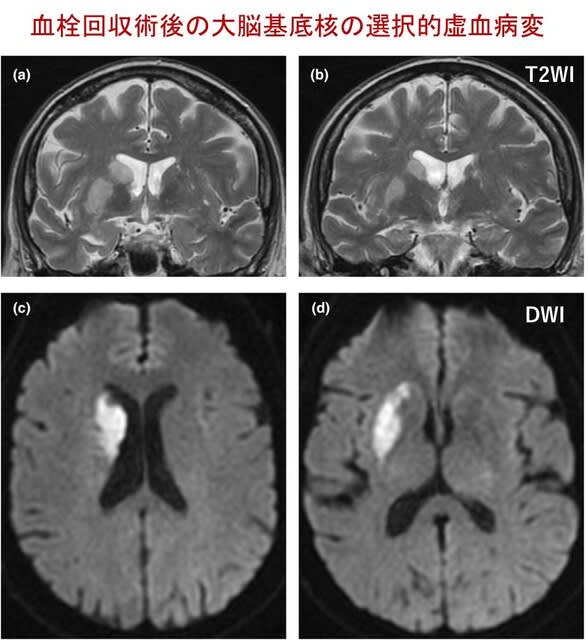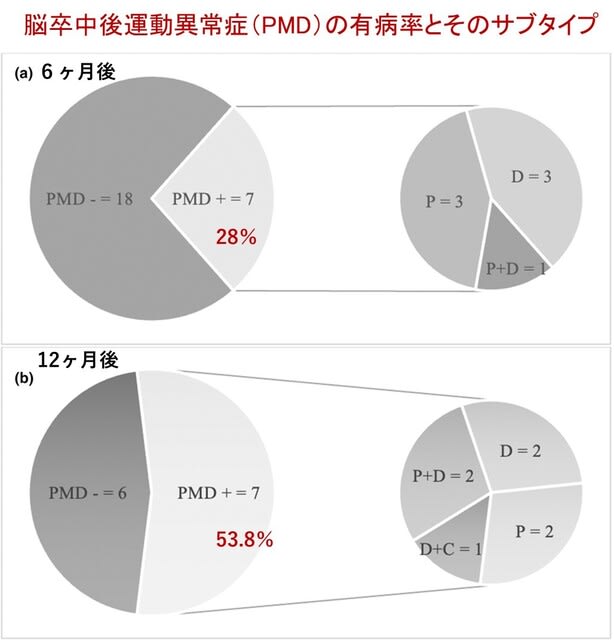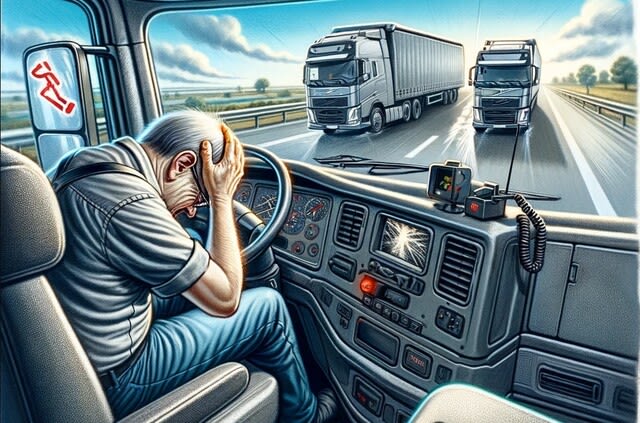STROKE2025,日本脳卒中学会等3学会合同シンポジウム「脳卒中医学・医療の近未来を予見する」において,豊田一則大会長に貴重な機会をいただき,標題の発表をさせていただきました.マイクロ・ナノプラスチック(MNPs)は環境問題としてだけでなく,人体への健康リスクとしても近年,非常に注目され,次々に新たな研究が発表されています.心血管疾患や脳卒中,認知症との関連が指摘され,病態機序の解明が進められています.講演では,基本的な知識,心血管疾患との関連,そして病態メカニズムについて概説しました.全スライドは以下からご覧いただけます.
https://www.docswell.com/s/8003883581/ZXE3GY-2025-03-08-075513
1)MNPs総論
マイクロプラスチックは2004年に概念化され,5 mm以下のプラスチック片として定義されました.さらに微細な1 μm未満のものはナノプラスチックと呼ばれ,より吸収されやすい性質を持ちます.MNPsは,消化管にとどまるだけでなく,さまざまな臓器に蓄積することが明らかになっています.

特にナノプラスチックは,血液脳関門を通過し,脳内に顕著に蓄積する(10g=クレヨン1本分!)ことが指摘されています.

MNPsの発生源としては,化粧品のマイクロビーズ,自動車タイヤの摩耗による微粒子,布地の繊維,さらにはペットボトルの水やティーバッグからの放出が挙げられます.MNPsには有害な化学物質が含まれており,特にビスフェノールA,フタル酸エステル,臭素系難燃剤などは,循環器障害,内分泌障害,神経毒性を引き起こすことが知られています.

欧州ではMNPsへの規制が進んでおり,化粧品中のマイクロプラスチック使用禁止や洗濯機のフィルター義務化などが行われています.しかし,日本では直接的な規制が進んでおらず,啓発活動や調査研究も遅れています.
2)脳卒中や心血管疾患との関連
近年,MNPsが心血管系の疾患と密接に関わることが報告されています.イタリアの研究では,頸動脈プラークの58%からMNPsが検出され,その存在が心血管イベントの複合リスクを4.53倍に増加させることが示されました.

MNPsがプラーク内の炎症を増強させることが関与しており,特にIL-18,IL-1β,TNF-α,IL-6などの炎症性サイトカインの発現が増加していることが確認されています.
また,中国の報告では,脳動脈や冠動脈,深部静脈血栓の80%にMNPsが検出されました.さらに,MNPsが血栓中に高濃度で存在する患者ではD-ダイマー値が上昇し,脳卒中の重症度を示すNIHSSスコアも有意に高くなっていました.
3)病態機序
MNPsは血管内皮細胞に直接影響を及ぼし,酸化ストレスや炎症を引き起こします.動物実験では,ポリスチレンナノプラスチックが大動脈内皮細胞に蓄積し,腸由来の細胞によって吸収させることが確認されています.また,JAK1/STAT3/TFシグナル経路が活性化し,凝固能が亢進することで血栓形成が促進されることが示されました.
このような病態が進行すると,血管障害が生じ,動脈硬化,心筋梗塞,脳卒中のリスクが高まります.さらに,MNPsが神経系にも影響を与え,認知機能低下に関連する可能性があることも指摘されています.
MNPsによる健康被害を防ぐためには,個人レベルと社会レベルの両面での対策が求められます.個人レベルでは,ペットボトルの水やプラスチック製のティーバッグの使用を控える,合成繊維製品の使用を減らす,電子レンジでプラスチック容器を加熱しないといった対応が重要です.一方,社会レベルでは,食品・飲料のプラスチック包装削減,MNPsの生産抑制,人体への影響調査の強化が必要と考えられます.

まとめ
MNPsは,環境汚染の問題だけでなく,心血管疾患や脳卒中の新たな危険因子として認識されるべき物質です.特に,ナノプラスチックは血液脳関門を通過し,脳への影響も懸念されます.動物モデルや臨床研究を通じて,MNPsによる病態機序の解明が進んでいますが,日本では対策が遅れており,今後の研究と政策の整備が急務です.
https://www.docswell.com/s/8003883581/ZXE3GY-2025-03-08-075513
1)MNPs総論
マイクロプラスチックは2004年に概念化され,5 mm以下のプラスチック片として定義されました.さらに微細な1 μm未満のものはナノプラスチックと呼ばれ,より吸収されやすい性質を持ちます.MNPsは,消化管にとどまるだけでなく,さまざまな臓器に蓄積することが明らかになっています.

特にナノプラスチックは,血液脳関門を通過し,脳内に顕著に蓄積する(10g=クレヨン1本分!)ことが指摘されています.

MNPsの発生源としては,化粧品のマイクロビーズ,自動車タイヤの摩耗による微粒子,布地の繊維,さらにはペットボトルの水やティーバッグからの放出が挙げられます.MNPsには有害な化学物質が含まれており,特にビスフェノールA,フタル酸エステル,臭素系難燃剤などは,循環器障害,内分泌障害,神経毒性を引き起こすことが知られています.

欧州ではMNPsへの規制が進んでおり,化粧品中のマイクロプラスチック使用禁止や洗濯機のフィルター義務化などが行われています.しかし,日本では直接的な規制が進んでおらず,啓発活動や調査研究も遅れています.
2)脳卒中や心血管疾患との関連
近年,MNPsが心血管系の疾患と密接に関わることが報告されています.イタリアの研究では,頸動脈プラークの58%からMNPsが検出され,その存在が心血管イベントの複合リスクを4.53倍に増加させることが示されました.

MNPsがプラーク内の炎症を増強させることが関与しており,特にIL-18,IL-1β,TNF-α,IL-6などの炎症性サイトカインの発現が増加していることが確認されています.
また,中国の報告では,脳動脈や冠動脈,深部静脈血栓の80%にMNPsが検出されました.さらに,MNPsが血栓中に高濃度で存在する患者ではD-ダイマー値が上昇し,脳卒中の重症度を示すNIHSSスコアも有意に高くなっていました.
3)病態機序
MNPsは血管内皮細胞に直接影響を及ぼし,酸化ストレスや炎症を引き起こします.動物実験では,ポリスチレンナノプラスチックが大動脈内皮細胞に蓄積し,腸由来の細胞によって吸収させることが確認されています.また,JAK1/STAT3/TFシグナル経路が活性化し,凝固能が亢進することで血栓形成が促進されることが示されました.
このような病態が進行すると,血管障害が生じ,動脈硬化,心筋梗塞,脳卒中のリスクが高まります.さらに,MNPsが神経系にも影響を与え,認知機能低下に関連する可能性があることも指摘されています.
MNPsによる健康被害を防ぐためには,個人レベルと社会レベルの両面での対策が求められます.個人レベルでは,ペットボトルの水やプラスチック製のティーバッグの使用を控える,合成繊維製品の使用を減らす,電子レンジでプラスチック容器を加熱しないといった対応が重要です.一方,社会レベルでは,食品・飲料のプラスチック包装削減,MNPsの生産抑制,人体への影響調査の強化が必要と考えられます.

まとめ
MNPsは,環境汚染の問題だけでなく,心血管疾患や脳卒中の新たな危険因子として認識されるべき物質です.特に,ナノプラスチックは血液脳関門を通過し,脳への影響も懸念されます.動物モデルや臨床研究を通じて,MNPsによる病態機序の解明が進んでいますが,日本では対策が遅れており,今後の研究と政策の整備が急務です.