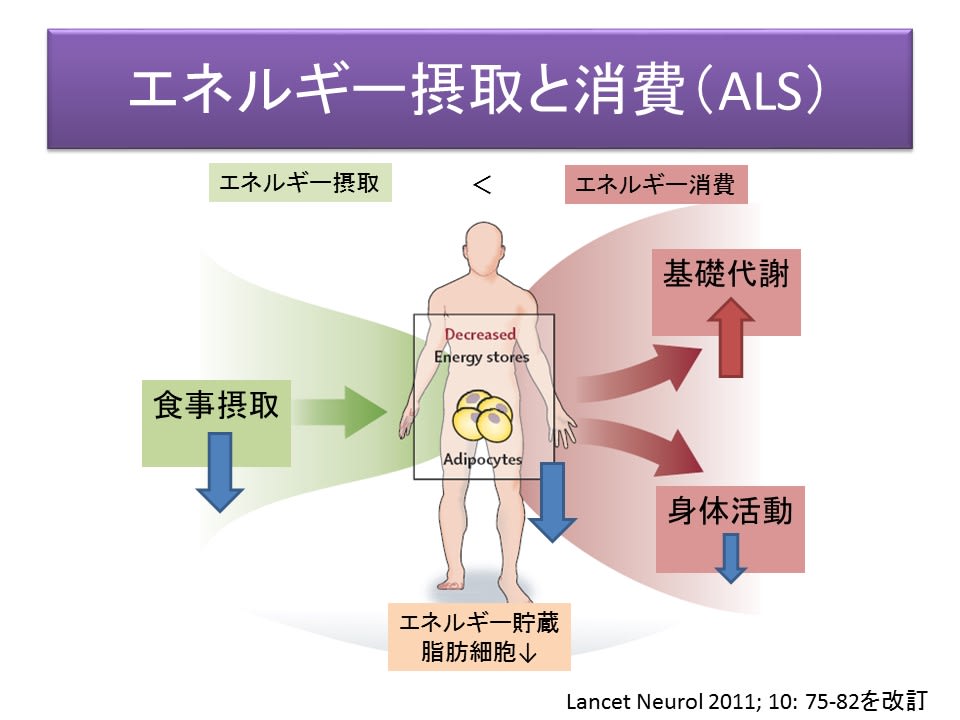食道アカラシアは食道疾患以外の疾患に合併することがある.食道アカラシアの病態機序として,自律神経障害による嚥下時の噴門弛緩不全が推定されている.このため自律神経障害を呈する多系統萎縮症(multiple system atrophy; MSA)においても合併を認めたという昔の症例報告があるものの,詳細は不明である.さらにMSAに合併する食道病変が臨床上,どのような意義を持つかについても不明である.このため,MSAにおける食道アカラシアに特徴的な嚥下造影検査の所見である造影剤の食道残留の頻度と,その臨床的な意義について新潟大学の神経内科と歯科(摂食嚥下科)が共同研究を行ったので紹介したい.
対象はGilman分類のprobable MSAで,臨床的に嚥下障害を認め嚥下造影検査を行った連続16例とした.対照を同じく臨床的に嚥下障害を認める筋萎縮性側索硬化症(ALS)16例とした.嚥下造影検査による造影剤の食道残留の有無・程度を,2群間で比較した.食道残留の程度は,嚥下した造影剤の半分未満の停滞を軽度,半分以上を高度とした.またMSA群においては,食道残留がもたらす合併症や,睡眠呼吸障害の治療に及ぼす影響について検討した.
さて結果であるが,MSA群の罹病期間は5.3±2.5年で,疾患重症度を示すunified MSA rating scale(UMSARS)スコアは54.6±24.1であった.終夜ポリソムノグラフィー検査にて14例(93%)が睡眠呼吸障害を呈し,そのうち7例で持続陽圧呼吸療法(continuous positive airway pressure; CPAP)が行われていた.嚥下造影検査における食道残留は,MSA群で16例(100%;高度7例,軽度9例),ALS群で4例(25%;4軽度)に認められ,MSA群で高頻度であった(P<0.001).食道残留が軽度の症例は,食道の運動不全が食道下部に限局していたが,高度な症例では下部から中部にまで及んでいた.経時変化を確認できた2症例ではいずれも食道停滞の程度が増悪した.食道残留を呈したMSA群16例のうち,嚥下障害以外のげっぷや胸焼けなどの症状は5名(31%)に認めるのみであった.その一方で,4例が誤嚥性肺炎を合併し,1例がCPAP中の繰り返す嘔吐を認め,最終的に食道内容物の逆流によると思われる窒息により突然死を来した.
以上の結果より,臨床的な嚥下障害を呈するprobable MSAでは,高頻度に食道停滞を呈しうることを明らかにした.食道残留が高度な症例では巨大食道症となる(図A).また就寝時の体位(臥位)や,CPAPに伴う呑気のため,食道に残留した食物が逆流し,誤嚥性肺炎や窒息を引き起こす可能性がある(図B, C).以下の2点を強調したい.
1) MSAでは嚥下造影検査の際に食道相まで確認すること.とくにゲップや胸焼けなどを認める症例では注意が必要である.
2) 食道停滞を認める症例では,食後,すぐに寝ずにしばらく坐位を取るよう指導すること.そして食道停滞が高度な症例では,CPAPの中止についても検討を行うことが大切である.
Taniguchi H, Nakayama H, Hori K, Nishizawa M, Inoue M, Shimohata T. Esophageal Involvement in Multiple System Atrophy. Dysphagia. 2015 Jul 24.

対象はGilman分類のprobable MSAで,臨床的に嚥下障害を認め嚥下造影検査を行った連続16例とした.対照を同じく臨床的に嚥下障害を認める筋萎縮性側索硬化症(ALS)16例とした.嚥下造影検査による造影剤の食道残留の有無・程度を,2群間で比較した.食道残留の程度は,嚥下した造影剤の半分未満の停滞を軽度,半分以上を高度とした.またMSA群においては,食道残留がもたらす合併症や,睡眠呼吸障害の治療に及ぼす影響について検討した.
さて結果であるが,MSA群の罹病期間は5.3±2.5年で,疾患重症度を示すunified MSA rating scale(UMSARS)スコアは54.6±24.1であった.終夜ポリソムノグラフィー検査にて14例(93%)が睡眠呼吸障害を呈し,そのうち7例で持続陽圧呼吸療法(continuous positive airway pressure; CPAP)が行われていた.嚥下造影検査における食道残留は,MSA群で16例(100%;高度7例,軽度9例),ALS群で4例(25%;4軽度)に認められ,MSA群で高頻度であった(P<0.001).食道残留が軽度の症例は,食道の運動不全が食道下部に限局していたが,高度な症例では下部から中部にまで及んでいた.経時変化を確認できた2症例ではいずれも食道停滞の程度が増悪した.食道残留を呈したMSA群16例のうち,嚥下障害以外のげっぷや胸焼けなどの症状は5名(31%)に認めるのみであった.その一方で,4例が誤嚥性肺炎を合併し,1例がCPAP中の繰り返す嘔吐を認め,最終的に食道内容物の逆流によると思われる窒息により突然死を来した.
以上の結果より,臨床的な嚥下障害を呈するprobable MSAでは,高頻度に食道停滞を呈しうることを明らかにした.食道残留が高度な症例では巨大食道症となる(図A).また就寝時の体位(臥位)や,CPAPに伴う呑気のため,食道に残留した食物が逆流し,誤嚥性肺炎や窒息を引き起こす可能性がある(図B, C).以下の2点を強調したい.
1) MSAでは嚥下造影検査の際に食道相まで確認すること.とくにゲップや胸焼けなどを認める症例では注意が必要である.
2) 食道停滞を認める症例では,食後,すぐに寝ずにしばらく坐位を取るよう指導すること.そして食道停滞が高度な症例では,CPAPの中止についても検討を行うことが大切である.
Taniguchi H, Nakayama H, Hori K, Nishizawa M, Inoue M, Shimohata T. Esophageal Involvement in Multiple System Atrophy. Dysphagia. 2015 Jul 24.