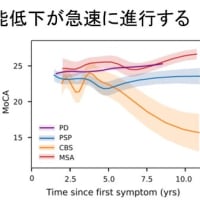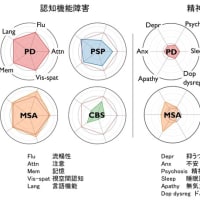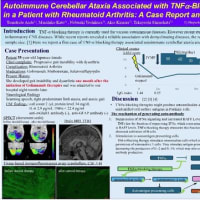新潟大学の先輩であり,岐阜大学における「ヒポクラテスの木」植樹に多大な尽力をしてくださった整形外科医,蒲原宏先生がご逝去されました.訃報に接し,深い哀しみとともに,先生との思い出が蘇ってきます.
「ヒポクラテスの木」は,ギリシャのコス島にあるヒポクラテスが弟子たちに医学を教えたとされるプラタナスの大樹のDNAを引き継いだ木であり,日本にはいくつかの系統があります.その中でも特に知られているのが「蒲原株」です.これは蒲原先生が1969年にギリシャのコス島で木の実を採取し,日本に持ち帰り,自ら播種育成されたものが起源となっています.学生時代,新潟大学の武藤輝一先生の「ヒポクラテスの誓い」についての講義後,「病院前のヒポクラテスの木を見に行くように」と指導を受けた私にとって,その木は医学の精神を象徴する特別な存在でした.
8年前に岐阜大学に異動してから,病棟実習の5年生に対する「ヒポクラテスの誓い」の講義を続けていますが,岐阜大学には「ヒポクラテスの木」はなく,学生たちにその存在を直接見せることができず残念に思っていました.このため,日本の脳神経外科の礎を築いた中田瑞穂先生が描かれた「ヒポクラテス像」の絵画を購入し,廊下に掲げて,それを見ていただいていました.しかし,やはり本物の木を学生たちに見せたいという思いが募り,蒲原先生にご相談したところ,快く承諾してくださり,移植の準備が始まりました.学生時代に眺めたその木から挿し木を行い,2年かけてようやく移植が可能な状態に育ちました.そして,多くの学生や同僚,事務の方々の協力を得て,2023年3月に念願の植樹が実現しました.
蒲原先生は,単にヒポクラテスの木を広められただけでなく,医史学研究家としても,また俳人としても大きな足跡を残されました.医学生時代から俳人・中田瑞穂,高野素十らの指導を受け,「蒲原ひろし」の俳号で俳誌「雪」を主宰されるなどご活躍されました.ある日,先生が私に送ってくださった俳句に「其恕乎(それじょか)の 孔子の一語 あたゝかし」というものがあります.「恕(じょ)」とは思いやりの心を意味し,孔子が「己の欲せざるところ,人に施すことなかれ」と説いた言葉に由来します.先生はこの言葉を20歳のときに脳神経解剖学の大家・平澤興先生から伺い,その精神を大切にされていました.医師として,患者さんに対する思いやりや共感(empathy)を何よりも重んじられた先生のお人柄が,この一首に凝縮されているように思います.私もこの俳句を大切に部屋に飾っていつも眺めています.

蒲原先生が遺された「ヒポクラテスの木」は,きっとこれからも大きく育ち,多くの学生に医学の精神を伝え続けてくれると思います.先生のご功績に深く感謝し,心からご冥福をお祈りいたします.最後に蒲原先生が,新潟市医師会報(2023.4月号)にご寄稿された文章のなかから,私の大好きな一句をご紹介したいと思います.
つんつんと若芽つんつん医聖の木
新潟日報 記事(先生のお写真はこの記事からの引用)
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/567411
新潟市医師会報「満100歳を目の前にして─生き過ぎがまだ欲ばっている─」
https://www.niigatashi-ishikai.or.jp/newsletter/contribution/202304266498.html
「ヒポクラテスの木」は,ギリシャのコス島にあるヒポクラテスが弟子たちに医学を教えたとされるプラタナスの大樹のDNAを引き継いだ木であり,日本にはいくつかの系統があります.その中でも特に知られているのが「蒲原株」です.これは蒲原先生が1969年にギリシャのコス島で木の実を採取し,日本に持ち帰り,自ら播種育成されたものが起源となっています.学生時代,新潟大学の武藤輝一先生の「ヒポクラテスの誓い」についての講義後,「病院前のヒポクラテスの木を見に行くように」と指導を受けた私にとって,その木は医学の精神を象徴する特別な存在でした.
8年前に岐阜大学に異動してから,病棟実習の5年生に対する「ヒポクラテスの誓い」の講義を続けていますが,岐阜大学には「ヒポクラテスの木」はなく,学生たちにその存在を直接見せることができず残念に思っていました.このため,日本の脳神経外科の礎を築いた中田瑞穂先生が描かれた「ヒポクラテス像」の絵画を購入し,廊下に掲げて,それを見ていただいていました.しかし,やはり本物の木を学生たちに見せたいという思いが募り,蒲原先生にご相談したところ,快く承諾してくださり,移植の準備が始まりました.学生時代に眺めたその木から挿し木を行い,2年かけてようやく移植が可能な状態に育ちました.そして,多くの学生や同僚,事務の方々の協力を得て,2023年3月に念願の植樹が実現しました.
蒲原先生は,単にヒポクラテスの木を広められただけでなく,医史学研究家としても,また俳人としても大きな足跡を残されました.医学生時代から俳人・中田瑞穂,高野素十らの指導を受け,「蒲原ひろし」の俳号で俳誌「雪」を主宰されるなどご活躍されました.ある日,先生が私に送ってくださった俳句に「其恕乎(それじょか)の 孔子の一語 あたゝかし」というものがあります.「恕(じょ)」とは思いやりの心を意味し,孔子が「己の欲せざるところ,人に施すことなかれ」と説いた言葉に由来します.先生はこの言葉を20歳のときに脳神経解剖学の大家・平澤興先生から伺い,その精神を大切にされていました.医師として,患者さんに対する思いやりや共感(empathy)を何よりも重んじられた先生のお人柄が,この一首に凝縮されているように思います.私もこの俳句を大切に部屋に飾っていつも眺めています.

蒲原先生が遺された「ヒポクラテスの木」は,きっとこれからも大きく育ち,多くの学生に医学の精神を伝え続けてくれると思います.先生のご功績に深く感謝し,心からご冥福をお祈りいたします.最後に蒲原先生が,新潟市医師会報(2023.4月号)にご寄稿された文章のなかから,私の大好きな一句をご紹介したいと思います.
つんつんと若芽つんつん医聖の木
新潟日報 記事(先生のお写真はこの記事からの引用)
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/567411
新潟市医師会報「満100歳を目の前にして─生き過ぎがまだ欲ばっている─」
https://www.niigatashi-ishikai.or.jp/newsletter/contribution/202304266498.html