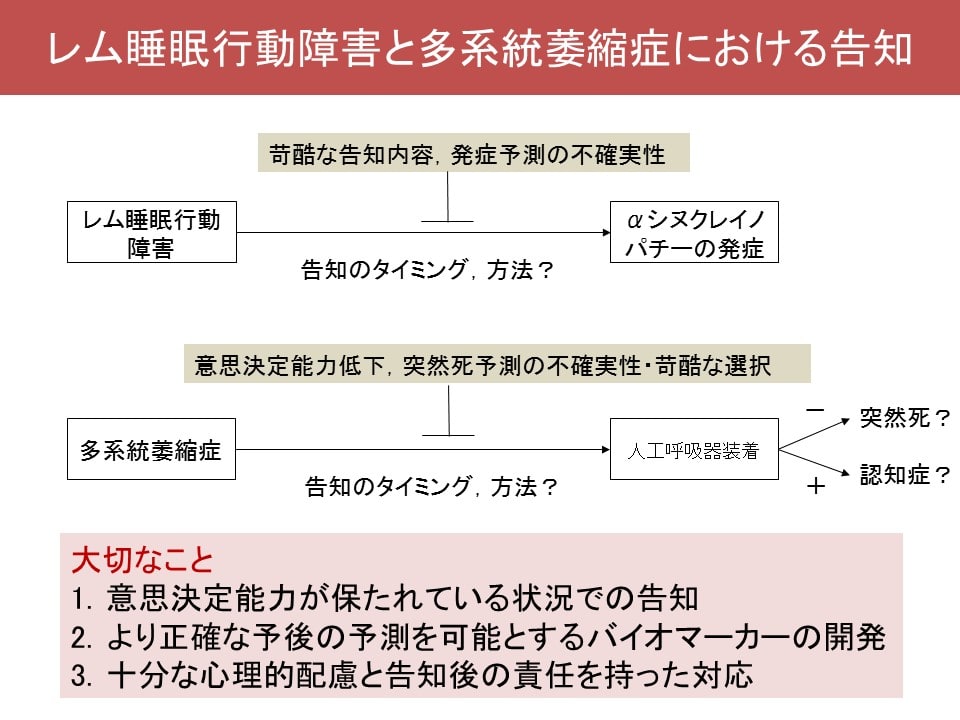筋萎縮性側索硬化症では,進行にしたがって体重が減少する.高度の体重減少は予後不良を示唆するため,体重減少を防ぐための高カロリー食が推奨される.またパーキンソン病でも進行に伴い,体重が減少することが知られている.では多系統萎縮症(MSA)ではどうだろうか?私たちは,MSAにおける病期ごとの体重と栄養状態について検討を行い,論文として報告したのでご紹介したい.
【研究の結果】
対象は2001年から2014年までに当科に入院したGilman分類probable MSAの82例(男性38例,女性44例)である.65例がMSA-Cで,17例がMSA-Pであった.うち24例が2回以上の入院をしたため,のべ130回の入院があった.アルブミン値に影響を及ぼす疾患(肝腎不全,うっ血性心不全,炎症性疾患,感染)を合併する症例は,対照から除外してある.評価項目はADLによる病期(自立/車いす/寝たきり),嚥下障害の有無,摂取カロリー,body mass index(BMI)とし,栄養学的な指標としてはしばしば使用される血清アルブミン値,血清総コレステロール値,リンパ球数とした.
さて結果であるが,自立群/車いす群/寝たきり群はそれぞれ50名,52名,28名であった.摂取カロリーは病期の進行に伴い低下したが(p<0.05;Fig A),BMIには変化はみられず(p<0.05;Fig B),体重の減少は認めなかった.一方,栄養の指標である総コレステロール値,リンパ球数には変化はなかったが,血清アルブミン値は病期の進行に伴い,4.18/4.03/3.07 g/dlと有意に低下した(p<0.05;Fig C).以上より,MSAではBMIが保たれていても(体重の減少がなくても),進行期には低栄養状態を呈しうること,その指標として血清アルブミン値が有用である可能性が示唆された.つまり,体重が減っていないからといって,栄養状態が良好であると油断してはいけないのである.MSA-CおよびMSA-Pに分けて行った解析でも,病期間のBMIに差はないこと,ならびに進行に伴い血清アルブミン値が低下することが確認された.
【なぜ体重は減少しないのか?】
ではなぜ体重は減少しないのだろうか?その理由として,まず嚥下障害による摂取カロリーの減少と消費カロリーの減少の程度が同等で,バランスが取れた可能性が考えられる.またMSAでは,むしろ低カロリーの食事摂取にも関わらず,気管切開・胃瘻造設後には皮下脂肪の蓄積傾向を示すことを,都立神経病院のNagaokaらは報告し,進行期にはカロリー制限する必要性についても言及している(臨床神経50;141-146, 2010).Nagaokaらはさらに検討を進め,脂肪細胞から分泌されるレプチンがMSAではうまく働いていない(つまりレプチン抵抗性の状態にある)可能性を示している(Neurol Sci 36; 1471-7, 2015).レプチンは脂肪細胞から分泌され,視床下部にて作用し,食欲の抑制,エネルギー消費の増大,交感神経刺激に伴う脂肪分解を介して,体重減少に作用するが,肥満者ではレプチン濃度が高くなっているもののレプチンによる刺激に鈍感になり,体重減少が起こらない.これを肥満者におけるレプチン抵抗性と言うが,NagaokaらはMSAでは自律神経障害によりレプチン抵抗性が生じているのではないかと考察している.
ちなみにわれわれの検討では血清コレステロール値に変化はなかったが,Nagaokaらの検討では低下を認めている.
【まとめ】
以上の結果から,1)MSAの進行期では体重は減少せず,むしろ増加もありうる.2)症例によっては摂取カロリーを絞る必要がある.3)栄養の指標としては血清アルブミン値が有用である,とまとめることができる.
Sato T, ShiobarabM, Nishizawa M, Shimohata T. Nutritional status and changes in body weight in patients with multiple system atrophy. Eur Neurol. 2016 Nov 29;77(1-2):41-44. [Epub ahead of print]

【研究の結果】
対象は2001年から2014年までに当科に入院したGilman分類probable MSAの82例(男性38例,女性44例)である.65例がMSA-Cで,17例がMSA-Pであった.うち24例が2回以上の入院をしたため,のべ130回の入院があった.アルブミン値に影響を及ぼす疾患(肝腎不全,うっ血性心不全,炎症性疾患,感染)を合併する症例は,対照から除外してある.評価項目はADLによる病期(自立/車いす/寝たきり),嚥下障害の有無,摂取カロリー,body mass index(BMI)とし,栄養学的な指標としてはしばしば使用される血清アルブミン値,血清総コレステロール値,リンパ球数とした.
さて結果であるが,自立群/車いす群/寝たきり群はそれぞれ50名,52名,28名であった.摂取カロリーは病期の進行に伴い低下したが(p<0.05;Fig A),BMIには変化はみられず(p<0.05;Fig B),体重の減少は認めなかった.一方,栄養の指標である総コレステロール値,リンパ球数には変化はなかったが,血清アルブミン値は病期の進行に伴い,4.18/4.03/3.07 g/dlと有意に低下した(p<0.05;Fig C).以上より,MSAではBMIが保たれていても(体重の減少がなくても),進行期には低栄養状態を呈しうること,その指標として血清アルブミン値が有用である可能性が示唆された.つまり,体重が減っていないからといって,栄養状態が良好であると油断してはいけないのである.MSA-CおよびMSA-Pに分けて行った解析でも,病期間のBMIに差はないこと,ならびに進行に伴い血清アルブミン値が低下することが確認された.
【なぜ体重は減少しないのか?】
ではなぜ体重は減少しないのだろうか?その理由として,まず嚥下障害による摂取カロリーの減少と消費カロリーの減少の程度が同等で,バランスが取れた可能性が考えられる.またMSAでは,むしろ低カロリーの食事摂取にも関わらず,気管切開・胃瘻造設後には皮下脂肪の蓄積傾向を示すことを,都立神経病院のNagaokaらは報告し,進行期にはカロリー制限する必要性についても言及している(臨床神経50;141-146, 2010).Nagaokaらはさらに検討を進め,脂肪細胞から分泌されるレプチンがMSAではうまく働いていない(つまりレプチン抵抗性の状態にある)可能性を示している(Neurol Sci 36; 1471-7, 2015).レプチンは脂肪細胞から分泌され,視床下部にて作用し,食欲の抑制,エネルギー消費の増大,交感神経刺激に伴う脂肪分解を介して,体重減少に作用するが,肥満者ではレプチン濃度が高くなっているもののレプチンによる刺激に鈍感になり,体重減少が起こらない.これを肥満者におけるレプチン抵抗性と言うが,NagaokaらはMSAでは自律神経障害によりレプチン抵抗性が生じているのではないかと考察している.
ちなみにわれわれの検討では血清コレステロール値に変化はなかったが,Nagaokaらの検討では低下を認めている.
【まとめ】
以上の結果から,1)MSAの進行期では体重は減少せず,むしろ増加もありうる.2)症例によっては摂取カロリーを絞る必要がある.3)栄養の指標としては血清アルブミン値が有用である,とまとめることができる.
Sato T, ShiobarabM, Nishizawa M, Shimohata T. Nutritional status and changes in body weight in patients with multiple system atrophy. Eur Neurol. 2016 Nov 29;77(1-2):41-44. [Epub ahead of print]