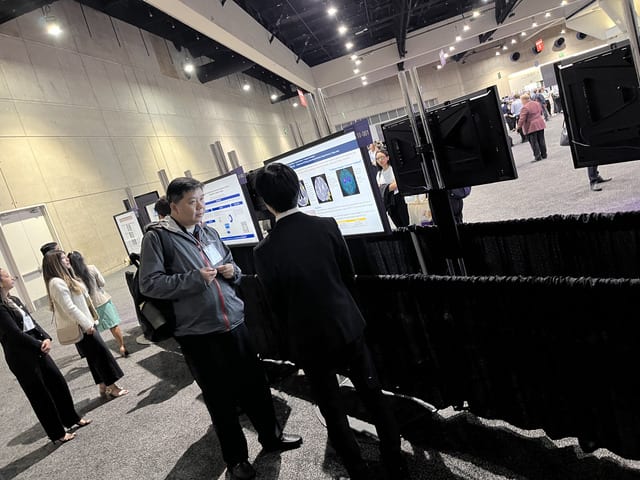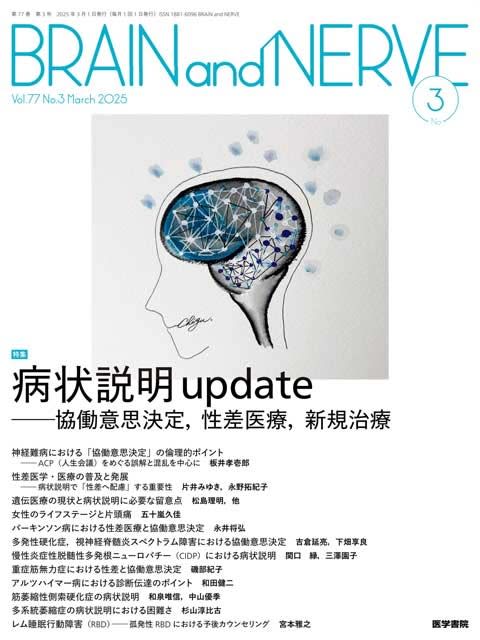「臨床神経学」誌は,日本神経学会が発行する月刊の神経学雑誌です.その名称の由来を,今月号の編集後記に執筆しました.よろしければご一読ください.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
編集後記
本誌の名前が「臨床神経学」となった経緯をご存知でしょうか?たとえば「日本内科学会雑誌」のように,「日本神経学会雑誌」ではなく,「臨床」の2文字がつけられている理由についてです.実は,当学会は1960年(昭和35年)に「日本臨床神経学会」と命名され,その機関誌は「臨床神経学」となり,発表された演題はすべて症例報告であったそうです1).その理由は,当時の神経学研究が臨床と離れたものであったことに対する反省が込められていると,新潟大学初代教授の椿忠雄先生が述べられています1).しかし1963年(昭和38年)には学会の英語名であるJapanese Society of Neurologyに対応させるため,また一層の発展を期して,「臨床」の2文字を外し,「日本神経学会」へ改名されました2).そして,最後まで「臨床」の2文字を外すことに反対されたのは,日本に初めて神経学の教室を設立した九州大学初代教授の黒岩義五郎先生でした3).椿先生と黒岩先生は東京大学の同級生であり,自律神経系に関する研究等で知られる冲中重雄教授の弟子でもありました.「日本臨床神経学会」設立の中心になり,初代学会幹事(理事)長に就任した冲中重雄先生は,「erstens Bett!(ドイツ語.何をおいても患者さんのこと―臨床―を第一に考えよ)」という教えを弟子たちに伝え鍛えたそうです3).すなわち,「臨床神経学」には「患者さんのため」という思いが込められているのだと思います.私たちは本誌の「臨床」の2文字に込められた初心を忘れず,患者さんのためにしっかりと症例報告を書いていきましょう.
1. 椿忠雄. 神経学とともに歩んだ道(非売品・1988)
2. 葛原茂樹.日本神經學會創立(1902)から116年―歴史に学び教訓を未来に活かす―.臨床神経2020;60:1-19
3. 黒岩義之. 黒岩義五郎. Brain Nerve 2017;69:949-956
https://www.neurology-jp.org/Journal/public_pdf/065050408.pdf
ちなみに写真は,学会事務局からいただいた貴重な資料で,冲中重雄先生が学会誌の方針や編集委員のメンバーについてお書きになられたものです.当時の雰囲気や意気込みが伝わってきます.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
編集後記
本誌の名前が「臨床神経学」となった経緯をご存知でしょうか?たとえば「日本内科学会雑誌」のように,「日本神経学会雑誌」ではなく,「臨床」の2文字がつけられている理由についてです.実は,当学会は1960年(昭和35年)に「日本臨床神経学会」と命名され,その機関誌は「臨床神経学」となり,発表された演題はすべて症例報告であったそうです1).その理由は,当時の神経学研究が臨床と離れたものであったことに対する反省が込められていると,新潟大学初代教授の椿忠雄先生が述べられています1).しかし1963年(昭和38年)には学会の英語名であるJapanese Society of Neurologyに対応させるため,また一層の発展を期して,「臨床」の2文字を外し,「日本神経学会」へ改名されました2).そして,最後まで「臨床」の2文字を外すことに反対されたのは,日本に初めて神経学の教室を設立した九州大学初代教授の黒岩義五郎先生でした3).椿先生と黒岩先生は東京大学の同級生であり,自律神経系に関する研究等で知られる冲中重雄教授の弟子でもありました.「日本臨床神経学会」設立の中心になり,初代学会幹事(理事)長に就任した冲中重雄先生は,「erstens Bett!(ドイツ語.何をおいても患者さんのこと―臨床―を第一に考えよ)」という教えを弟子たちに伝え鍛えたそうです3).すなわち,「臨床神経学」には「患者さんのため」という思いが込められているのだと思います.私たちは本誌の「臨床」の2文字に込められた初心を忘れず,患者さんのためにしっかりと症例報告を書いていきましょう.
1. 椿忠雄. 神経学とともに歩んだ道(非売品・1988)
2. 葛原茂樹.日本神經學會創立(1902)から116年―歴史に学び教訓を未来に活かす―.臨床神経2020;60:1-19
3. 黒岩義之. 黒岩義五郎. Brain Nerve 2017;69:949-956
https://www.neurology-jp.org/Journal/public_pdf/065050408.pdf
ちなみに写真は,学会事務局からいただいた貴重な資料で,冲中重雄先生が学会誌の方針や編集委員のメンバーについてお書きになられたものです.当時の雰囲気や意気込みが伝わってきます.