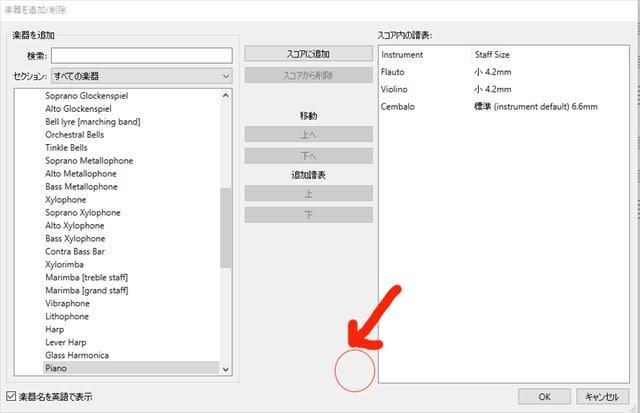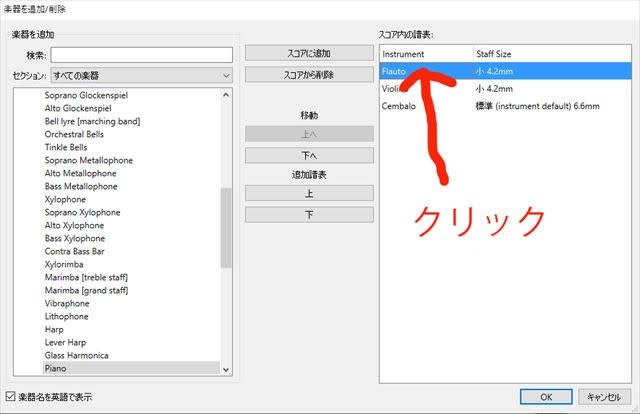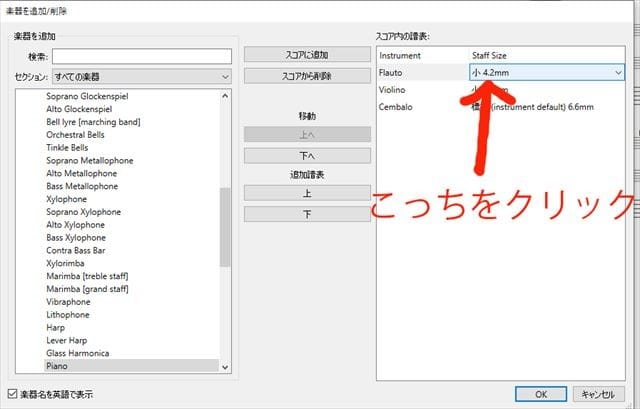三重県でも県南部の尾鷲市、熊野市、紀北町、紀宝町、御浜町以外で本日から2月13日までまん延防止等重点措置が適用されます。細かいところは異なるかも知れませんが概ね今までと同様の方向のようです。
市の方からバロック音楽の旅14講座コンサート会場の対応について連絡が来まして、定員の半分以下で感染対策をきちんとしていれば開催可能だということでした。内閣府の基本方針では、大声をあげないイベントの場合は100%の収容人員でもいいとありますので、バロック音楽の場合は皆さん座って静かに聴きますので100%でもいいのでしょうけど。まぁとりあえず一安心です。多分ないと思いますが、緊急事態宣言発出となると話は変わってくるかも知れませんが。
第5回講座は1月30日で第6回が2月6日と2回とも重点措置の期間に入っていますが、私の直感的な予想では2月6日頃はピークを過ぎているような気がします。
県内のホールの対応も調べてみましたが概ね同様でした。昨年の12月にコンサートをしました横浜の鶴見区民文化センターサルビアホールのHPも見てみましたが、中止になっているイベントはありませんでした。このあたりは軒並みイベントが中止になった2020年3月終わり頃とは大きく異なります。その頃は実は今よりは感染者はずっと少なかったのですが、今よりずっと厳しい対策を取っていました。(おかげで東京でのコンサートがなくなってしまいましたが)今はウィルスとの共存の仕方がだんだんわかってきたという感じです。
市の方からバロック音楽の旅14講座コンサート会場の対応について連絡が来まして、定員の半分以下で感染対策をきちんとしていれば開催可能だということでした。内閣府の基本方針では、大声をあげないイベントの場合は100%の収容人員でもいいとありますので、バロック音楽の場合は皆さん座って静かに聴きますので100%でもいいのでしょうけど。まぁとりあえず一安心です。多分ないと思いますが、緊急事態宣言発出となると話は変わってくるかも知れませんが。
第5回講座は1月30日で第6回が2月6日と2回とも重点措置の期間に入っていますが、私の直感的な予想では2月6日頃はピークを過ぎているような気がします。
県内のホールの対応も調べてみましたが概ね同様でした。昨年の12月にコンサートをしました横浜の鶴見区民文化センターサルビアホールのHPも見てみましたが、中止になっているイベントはありませんでした。このあたりは軒並みイベントが中止になった2020年3月終わり頃とは大きく異なります。その頃は実は今よりは感染者はずっと少なかったのですが、今よりずっと厳しい対策を取っていました。(おかげで東京でのコンサートがなくなってしまいましたが)今はウィルスとの共存の仕方がだんだんわかってきたという感じです。