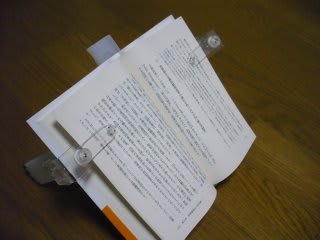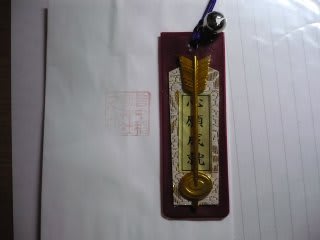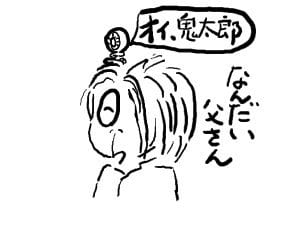朝は少し寒かったものの、日中は気温も上がって少し暖かくなりました。東京の桜開花予想日はもう来週に迫りました。
さて、明日から一泊二日で掛川へ行ってきます。明日の土曜日は、NPOスローライフ掛川の活動だったライフスタイルカレッジの卒業式。一年間の成果を分かち合いながら、たくましくなった受講者の皆さんの顔を見てこようと思います。
お茶を学ぶのに、器を焼き物で作るところまで行ってしまう講義とは、いったいどのようなものでしょうか。小さいと思った窓を開けてみると、大会が広がっていた、なんてことが多いのです。
そして明後日は、市内で造り酒屋をやっている知人のお宅でお酒の蔵開きがある、というので覗いてこようと思っています。やはり蕎麦打ちをしている知人の団体が応援に回ると言うことで、掛川の蕎麦研もお手伝いとしてかけつけます。
お互いに団体同士が切磋琢磨して腕比べをするというのは刺激的です。微妙に蕎麦の打ち方も違ったりして、流派の違いが分かることもあります。
酒、蕎麦、器…と、いろいろな要素が揃ってきたような気がします。あとは書、友、家…と世界が広がりそうな予感。
どんなに小さくても、初めは小さい窓を開けるところから始まるのです。
さて、明日から一泊二日で掛川へ行ってきます。明日の土曜日は、NPOスローライフ掛川の活動だったライフスタイルカレッジの卒業式。一年間の成果を分かち合いながら、たくましくなった受講者の皆さんの顔を見てこようと思います。
お茶を学ぶのに、器を焼き物で作るところまで行ってしまう講義とは、いったいどのようなものでしょうか。小さいと思った窓を開けてみると、大会が広がっていた、なんてことが多いのです。
そして明後日は、市内で造り酒屋をやっている知人のお宅でお酒の蔵開きがある、というので覗いてこようと思っています。やはり蕎麦打ちをしている知人の団体が応援に回ると言うことで、掛川の蕎麦研もお手伝いとしてかけつけます。
お互いに団体同士が切磋琢磨して腕比べをするというのは刺激的です。微妙に蕎麦の打ち方も違ったりして、流派の違いが分かることもあります。
酒、蕎麦、器…と、いろいろな要素が揃ってきたような気がします。あとは書、友、家…と世界が広がりそうな予感。
どんなに小さくても、初めは小さい窓を開けるところから始まるのです。