平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」
かさぶた日録
「新田次郎 山の歳時記」を読む
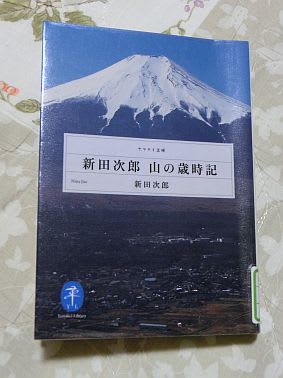
久し振りに山のエッセイを読んだ。新田次郎を読むのも久し振りである。新田次郎の山岳小説は9割方読んでいる。読んだのはまだ昭和の時代であった。「八甲田山死の彷徨」「孤高の人」「芙蓉の人」「聖職の碑」「剣岳<点の記>」「強力伝」「槍ヶ岳開山」「富士山頂」「銀嶺の人」「栄光の岩壁」など、数えてみると今でも懐かしい。その作品群は消えることなく、現在も読み継がれているという。
読み始めて、ふるさと霧が峰の子供時代の話に、あれっ!と思い表紙を見直した。何を勘違いしたのか、井上靖のエッセイを読んでいるように錯覚して、著者名を確認した。井上靖なら伊豆がふるさとだから、変だなあと思った。さらに先を読んでいくと、山行の話が出てきて、あれっ!と思い、再び著者名を見て納得した。今度は、深田久弥のエッセイと錯覚して、どうも肌触りが違うと思った。山のエッセイで名のある文学者は、串田孫一、深田久弥、井上靖、新田次郎と数えられるが、皆んな亡くなり、このあとを、誰が継いでいるのであろう。
「新田次郎 山の歳時記」はオリンピックから万博へと日本が高度成長していた時代に出版された、エッセイ集「白い野帳」「山旅ノート」から抜粋して文庫本にまとめたものである。山へ登る人口が増えて、この頃には、山々の植生がずいぶん失われてきたと書いている。自分が山登りを始めたのは、その後であった。自分たちにとっては、山はまだまだ自然が残っていると思っていた。現在は南アルプスなど鹿の食害でお花畑が全滅のような話を聞くが、新田氏の時代は自然破壊はもっぱら登山者であった。それにしても、雷鳥を追い回し、その雛を捕まえて、焼き鳥にして食べた人がいたという話にはびっくりした。雷鳥には天気の悪い日、何度もお目にかかったが、食べる対象に考える人がいたことは少なからずショックであった。
新田次郎はかなり気難しい人で、作品にはずいぶん頑固な部分が描かれている。あまり人の話を聞かない性格のようだ。それでいて、単独の山行はほとんどしていない。山には案内人を付けて登っていた。
山登りの経験は、ほとんど小説の材料に使われて、エッセイに書かれたものは、作品化しなかったものだけであり、新田氏はエッセイに書くよりも、小説に書く方が楽だと書いている。新田氏にとって、小説が主で、エッセイは余儀だったのだろう。
エッセイの中で、時々気象庁の技官としての顔が出てくる。富士山レーダー設置のときの活躍は、「富士山頂」の作品に詳しいが、無線雨量計を発明して、1号機を設置したのも新田氏であるとは初耳であった。
これを機会に、新田次郎の読み残した作品を読んで見ようと思った。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
木谷恭介著「死にたい老人」を読む

木谷恭介著「死にたい老人」を読んだ。といっても読んだのは1週間ほど前で、「専務」のことがあって、感想を書くチャンスが無かった。木谷恭介といえば、旅情推理小説で流行作家だった。特に著者の作品の愛読者だったわけではないが、図書館の新刊案内で題名を見て、気になって借りてきた。
木谷恭介氏は現在83歳、掛川市(旧大須賀町)で一人暮らしをしている。人口減、老齢化がすごい勢いで進行している日本で、福祉の危機が問題になっている。若い時から好き放題やって来て、この年齢になっても長らえている。生きるためには書かなければならないけれども、書くことにも疲れた。早くこの世におさらばした方が、国のため、社会のためだと思った。しかし、日本では安楽死や尊厳死は末期状態にならなければ、認められる可能性はない。
出来れば意味のある死を死にたい。考えているうちに、断食によって死んで、死の直前まで身体の状況や思いなどを克明に書き残し、遺稿として世に出せば、意味のある死になるのではないかと考えた。そこで自分の最新の著書の後書きに断食による死を実行すると宣言した。ただ、断食を実行する際に、周囲にいる人たちが、保護責任者遺棄罪として訴追されては申し訳ない。それでヘルパーさんやアシスタントの女性を解雇した。少し離れている近所には、子供のところへ引っ越すという話を広めた。
1度目は断食を始めようとしたときに、救急車で運ばれるような病を発症して実行出来なかった。2度目はかなり長く断食したが、医者から出されている何種類かの薬を飲み続けていたので、そのうちに胃が激しく痛んで、そのまま続けると胃に穴が空き、腹膜炎になって死ぬ。それでは断食による死にならないので、病院に行き、ドクターストップになってしまった。死に至る断食を試みながら、様々な薬を飲み続ける滑稽さにはほとんど気付いていない。
3度目の断食に入った所で、ある人から人間、理性的に自殺する事は出来ないと言われた。断食をしようとすると色々障害が起きるのも、理性が生存本能を使って引き起こしている障害であろうと思った。すっかり納得してしまい、断食を中止してしまった。そこまでの記録を本にしたのが、「死にたい老人」である。
かつて、僧が食を絶ち経を読みながら死んで即身仏なる行が行われた。即身仏はミイラ化し、信仰の対象になった。特に東北地方ではそういう即身仏が何体も残っている。僧は一本の竹筒だけで外界と繋がった穴倉に入って、経を読み続ける。その弟子たちは、竹筒から読経が聞こえなくなったら、成仏したとみなして穴を埋めてしまった。著者はその事実を、やはり人間は理性的に死ぬことは難しいから、弟子たちが手を貸して成仏させるのだろうと解釈する。
著者は今回は失敗したが、まだ諦めたわけではないと、断食による死に未練を残している。この老作家、意外としたたかかもしれない。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「東京歳時記」を読む

出久根達郎著「東京歳時記」を読んだ。俳句雑誌に連載したエッセイを一冊にまとめたものだという。先人の俳句を一句最初に掲げ、その句とつかず離れずといった内容のエッセイである。日常起きる些細なことを取り上げて書いているが大変面白い。
プロの書くエッセイと、素人が書くものの違いは、プロのエッセイは嘘が混ざっていることだと思う。嘘では聞こえが悪ければ、創作と言った方がよい。事実と創作が区別できないように混ざっていて、一つの作品となっている。読者はついついすべてが実際に起きたことと信じてしまう。テレビのバラエティトークと似たようなところがある。
「東京歳時記」を読みながら、ここは著者の創作だと、見破ろうと追っている自分がいた。いやな性格である。それでも、著者のちょっと創りすぎと思ったところが何ヶ所かあった。ただ指摘は失礼だから止めよう。
素人が書くと事実にこだわりすぎて、平板なものになってしまう。自分もブログでは嘘が全く書けない。出来るのは実際にあった事を、書くか書かないかの選択だけである。だから、面白くない。話を創れば面白く書けるかと思うのだが、際限がなくなりそうで、どうしても踏み込めない。
中に「エッセイの題材」という項ではなるほどと思わせるものがあった。インタビューを申込まれたが、花粉症が酷くてその気になれず、質問を文章で頂いて、文章で答えることにした。エッセイの題材はどんな風に見つけるのかという質問があった。それっ、自分も聞きたいと読み進んだ。
当り前の日常でも、ふと立ち止まって、よくよく眺めると、あれ?面白いなと思うことがある。例えば、夜中にお腹がすいて、カップめんをよく食べる。紙ぶたを半分空けて湯を注ぐ。3分間待つときに紙ぶたが開かないように重石を置くと思うが、手頃な重石に皆んな何を使っているのだろう。それだけでエッセイのネタになる。ちなみに、著者は急須のふたを重石にしているという。自分はカップを包んでいるビニールを切り取るために使ったハサミが重石になっている。
インスタント焼きそばでカップの湯を流しに捨てると、ステンレスの流しが、ビンと大きな音をたてる。まるで流しが熱い!て悲鳴を上げているように聞こえる。あれって、どの家でも同じなのだろうか。ちなみに家でも古い流しは同じように悲鳴を上げた。しかし、最新の流しに変えたら悲鳴は無くなった。
こんな調子で日常のどこにでも題材が転がっていると、次々に実例が述べられて大変参考になった。ちなみに「東京歳時記」のエッセイの長さは約3000文字である。このブログは最低でも1000文字と考えている。ここまでで軽く1000文字を越えた。
コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )
「龍の棲む日本」を読む

図書館の「龍」の特集コーナーで、黒田日出男著「龍の棲む日本」を借りてきた。辰年の新年、何もお祝い事はしなかったが、辰年らしい本を一冊読もうと手に取った。岩波新書だから、簡単に読み飛ばせると思ったが、読み始めてから、読み終るまでに1週間ほど掛かった。その間に別の本を何冊か読んでいる。
日本人は昔、自分の国をどんな風にイメージしていたのか。最も古い日本図として、神奈川県立金沢文庫所蔵の「日本図」がある。日本の西半分しか残っておらず、東半分は失われている。鎌倉時代末期の行基式日本図と考えられている。駿河、遠江などの国名、国の等級、田地の丁数がうろこの形に仕切られて書き込まれている。その全体が独鈷という仏教で使う法具の形に描かれ、その周りを鱗を描かれた蛇のような胴が囲んでいる。東半分が残っておれば、頭と尻尾があって、何が描かれていたかが判るのだが、謎として残された。しかし、時代を追って同様の日本図を調べていくと、蛇のような胴は龍の胴であることが判る。
当時、元寇という国難を迎えて、鎌倉幕府、朝廷、寺院などが一丸となって元を迎え撃った。民衆まで含めて、日本が初めて国として意識され、珍しく団結した瞬間ではなかったかと自分は思う。その当時に製作された日本図である。日本は龍の胴体にぐるりと囲まれて守られているように描かれた。元寇は2度までも神風が吹いて、日本は守られた。しかし、三度元が攻め入るという恐怖心は日本人の心に長く残った。
日本の国を龍が囲って守るという日本図は、江戸時代までしばしば描かれてきた。龍は地震、雷を起こし、降雨、止雨を司ると考えられていた。地震は龍の頭と尾を鹿島神宮の要石が押えて止めていたが、時々揺れる。地震には「龍神動」「火神動」「水神動」「帝釈動」などの区別があって、それぞれ吉兆の占いの元になる。前に安政の大地震を描いた古文書に、地震には火震と水震があると書かれていたが、同じ情報源なのだろう。
日照りが続くと雨乞いを行う。村々には龍の棲むといわれる龍穴が必ずあった。洞穴だけでなく、滝、池、山、お堂など様々なところに、龍が住むと信じられた場所があった。大勢で鉦太鼓を鳴らして雨乞いをした。確かに古文書を見ていくと、しばらく天気が続くと村中集って雨乞いに行くという文書をしばしば見る。
江戸時代になると、それまで地震を司る龍の役割は鯰に取って代られる。江戸時代の出版物に鯰絵という絵がある。鯰と地震の関係は現代にも尾を引いている。どうして龍が鯰にかわり、鯰絵がどんな目的で出版されたのか。それはまた別の問題で、この本には詳しくは書かれていない。
日本図も地図といえるようなものではないし、架空の生き物である龍を追いかけても空しい気がするけれども、中世から近世にかけて、人々の心象風景を知るという意味で価値があるのであろう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「台湾人には、ご用心!」を読む

図書館の予約システムで、新刊書の「台湾人には、ご用心!」を借りた。図書館で本を手にしたとき、場違いな本を借りてしまったかとげんなりした。台湾在住の日本人がその体験から台湾人の気質を書いた本と思って借りた。表紙の絵は、日本に“萌え”の状態にある台湾人を象徴的に示した絵なのだろう。内容はいたって真面目な比較文化論で、誤解して購入する人もいるであろう。
台湾人が大変親日的であることは、台湾旅行をしたことのある日本人が身を持って感じることである。台湾は戦前、日本の統治下にあった。日本語教育が行なわれて、お年寄りは皆んな日本語がしゃべれた。戦後、大陸から逃げてきた国民党統治下になり、中華民国となった。国民党の政治が余りに略奪的で、不満分子の大量の粛清があったりして、日本統治下へのノスタルジーから日本贔屓になっているといわれてきた。
しかし、著者の見解は少し違う。日本統治下であってもすべてが肯定的に考えられているわけでもない。評価されているのは治水や水道、農業開発、衛生面の啓発などであり、強圧的な統治方法まで是としているわけではない。
台湾人は商売の相手としては付き合っているが、基本的に中国人や韓国人は嫌いで、日本人は好きである。中国人や韓国人は他者に厳しく自分に甘い、日本人は他者に厳しいが自分にも厳しい。それに対して、台湾人はマレー系の人種の特徴で、他者に甘く自分にも甘い。どちらにしても、台湾人に対して厳しいのは嫌であるが、日本人は他者に厳しい分、自分にも厳しいから許せると考える。
台湾では日本人というだけで、特別の扱いをされる。中国人や韓国人をはじめ、東南アジアのどの国の人も受けない待遇である。これは元植民地で独立した国が、宗主国の国民に抱く感覚と同じであるという。
若い人たちは、長い平和の時代の産物としての、漫画、アニメ、ゲームなどから始まった日本の新しい文化へ憧れを持っている。そして、日本語を勉強し、遊びに行くなら日本へ行きたいと多くの若者たちが思っている。
台湾の人たちは、大震災で救援物資の配給を整然と行列して待ち、感謝していただく日本人の映像を、日本で放映されると同等のレベルで見てきた。多くの死者を出しながら、落ち着いた態度で終始する日本人の姿を感銘を持って見てきた。国内の一地域が被害にあったような感覚でとらえていた。だから、他人事とはおもえなくて、短期間に200億円という、世界のどこの国よりも桁違いに多くの義捐金が集った。
そんなに友好的な国民であるが、付き合うときには気をつけなくてはならない。東南アジアの多くの国民と同じようにマレー系の人種の特徴で、他人に甘く、自分にも甘い。約束は平気で忘れる。ドタキャンは日常茶飯事。しかし人を騙そうとするような悪意はない。だから咎めるのが難しい。面罵すると、面子を傷つけられたと、反撃される。一方、大陸の中国人は、いつでも平気で悪意を持って人を騙そうとする。だからその場で厳しく糾弾しても、面子を失ったとは思わない。その手が通じないと理解して、2度と同じ手は使わなくなる。しかし、新たな方法を考える。扱い方としては中国人の方が扱い易いかもしれない。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「警官の条件」を読む

最近、佐々木譲著「警官の条件」を読んだ。最期の数ページを涙を流しながら読んだ。最近、歳とともに涙腺が甘くなって、緩むことが増えてきた。本を読みながら涙を流すことなど、かつては無かったことである。
そこで、日本の男はどんな場面で泣くのだろうと考えてみた。同じ刑事ものでも、最近テレビで何週かに渡って放映していたダーティハリーシリーズなど、どれだけ絶対的な危機を超人的な活躍で乗り越えようと、最後にハッピーエンドで男女が抱き合おうと、日本の男どもには何の感興も呼ばない。だから映画を見終わってああ面白かったで終わりである。
「警官の条件」で何が泣けたのか。殉職した警官の息子が新人刑事になって、殉職に関わりのあった刑事の下に配属されてくる。責任も感じて何とか一人前にしてやろうと仕事を教えていた。ところが新人刑事は、何かと素行が悪いが実績を上げる刑事を快く思わない警務部から、内部告発するように指示を受けていた。新人刑事は間もなく内部告発し、上司の刑事は警察を追われる。
何年か経って、実績が上がらないその部門に、その新人刑事が係長として戻ってくる。一方、上司の刑事も警務部から復職を懇願されるが断っていた。ところが当時の部下で可愛がっていた部下が不容易な潜入捜査で殉職する。「もっとしっかり仕事を教えておくべきだった」と葬儀で語り、殉職刑事が所属した係に復職した。行き掛かり上、新人刑事の係と、復職刑事の配属係が、殉職刑事の犯人を追って競争することになる。
復職刑事所属の係長は復職刑事のはみ出し捜査に耳を貸さない。単独捜査の復職刑事の動きが、いくつか部下から伝わってくる。ひらめいた新人刑事は係を総動員して、復職刑事の行動を追う。復職刑事は単独で廃工場に入っていく。外で待機していた新人刑事に「直ぐに突入しろ」と復職刑事から携帯が掛かってくる。予想もしない事態に戸惑っていると、銃声が聞こえ突入する。全員逮捕して殉職刑事の事件は解決するが、撃たれた復職刑事は行き絶え絶えになりながら、「世話掛けやがって」と言って、目を閉じる。
書いてみるとそんな筋なのだが、400ページもの小説を、その最後の一言をいわせるために、書いて来たように思えた。最後は何となくそんな終わり方になるのだろうと想像しながら、その場面になると感極まるのである。
日本の作品の書き方はそんなパターンが多い。海外の作品ではそんな盛り上げ方は余りお目にかからない。ハリウッドがマンネリになり、日本の作品をカバーした作品が新しいとして取り上げられるのは、そんな感覚があるのだろうと思う。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
推理小説と古文書解読

四年程前、自分と同時期に会社の役員を退いたH氏は、退職後は親の介護をしなければならないと送別会で話していた。介護をしながら推理小説を書くと話して、我々をびっくりさせた。もともと技術畑のH氏にそんな素振りは全く無かったから、密かにそんな計画を持っていたとは意外に思った。
推理小説を沢山読んでいると、こんな小説なら自分にも書けると思う人は多い。しかし思うことと、書くことは全く次元の違う話である。何と言っても絵空事にしろ、人を何人も殺すことが普通の人には出来ない。作家は殺人者ではないけれども、殺人者と普通人との間で、より殺人者に近い位置にいる。
なぜ推理小説に殺人が頻繁に起きるのか。推理小説は謎解きが中心になる小説であって、被害者が生きているとその証言で謎が簡単に解けてしまう。だから死んでもらわねばならない。しかも殺人は犯罪の中でも最大の事件である。だから殺人事件が多くなる。
探偵が動き、謎に迫ると、それを予期したようにキーマンが殺される。そういう意味では、殺人の半分以上は、探偵が動かずに迷宮入りになっていたら起きなかった殺人である。だから、真実を明らかにするために、間接的にしろ、最も多くの人を殺したのは、かつては金田一耕助であり、今は浅見光彦であることは間違いない。
近頃、殺人事件でない謎解きの楽しみを見つけた。推理小説の謎は作家によって設定された謎で、パズルを解くようなものである。見つけた謎解きの謎は、自分で見つけた謎で、設定した人は誰もいない、いわば天然の謎である。ここまで書くと何を言いたいか解ってしまった人もいるかもしれない。
古文書の解読を勉強していると話すと、何が面白いのかとよく聞かれる。最近用意している答えは、古文書を解読していくと、自分で疑問符が沢山付いていることに気付く。それを謎として一つずつ解明していく。単純には一つの言葉の意味であったり、誰が書いた文書なのか、どこのことを書いたものだろう、現在所縁の地はどうなっているのか、などなど、色々な謎が湧いて来る。
この謎解きでは殺人事件は起きない。古文書に関わったすべての人々は、殺さなくてもとっくに死んでいるから、元々彼らに質問をぶつけることは出来ないのである。古文書から読み出した謎を解明しようとしながら、探偵になったような気分で、その一つでも解明されると大変に楽しい。
話は元に戻るが、H氏は推理小説を書いているのだろうか。書けたらミステリー何とかという賞に応募するのだろうが、まだ朗報に接していない。殺人事件の起きない天然の謎を追跡した推理小説を誰か書いてくれないだろうか。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「女流阿房列車」を読む

用もないのに汽車に乗る。汽車が好きだから汽車へ乗る。内田百氏が阿房列車の旅を始めて、その紀行文を文学にまで高めたのは、戦後の昭和26年のことである。戦前には思いも浮かばなかった、汽車に乗ることを楽しむ旅の始まりである。その後、鉄道の楽しみ方は色々と分化して、亜種が幾つも出来ている。電車、路線、鉄道写真、鉄道模型、鉄道施設、時刻表、車窓、駅、廃線など、それぞれ興味を持つところが違う。彼らは鉄道オタク、あるいは鉄人と呼ばれて認知されている。
鉄人には色々な変り種もあって、それを語るのも面白いが、ここでは、色々なテーマや条件を設けてひたすら汽車に乗り、その記録を発表するライターの話である。内田百氏を先頭に、色々な文学者が汽車の旅を書いているが、忘れてはならないのが宮脇俊三氏である。「最長片道切符の旅」「時刻表2万キロ」など、鉄道の旅に関わるたくさん著書は、鉄道オタクをメジャーな位置まで引き上げた。前述の二著をバイブルとして、多くの人たちが鉄道の旅に出かけた。
かくいう自分も汽車好きを自認している。鹿児島へ度々の出張に、飛行機はめったに使うことはなかった。かつてはブルートレイン、新幹線にリレーつばめ、さらに現在は鹿児島まで新幹線で行ける。それぞれ目的のある出張だから鉄道オタクとはいえないが、鉄道好きは否定しない。
今日読み終えた本は、酒井順子著「女流阿房列車」である。鉄道オタクや鉄道好きは男性専科と思っていたが、立派な女流がいた。但し、男性の鉄人とは楽しみの壺が違うようである。鉄道の旅は時刻表を駆使して誰も考えなかった旅程を組み上げるのが、楽しみの大きな部分である。けれども、鉄女(サッチャー元英首相ではない)は計画作りは他人任せで、与えられた難行苦行をひたすらにこなしていく。いささかマゾ的な楽しみ方である。
ところが、読み進んで行くと、せっかくの車窓の絶景ポイントを、何度も、激睡、熟睡、気絶状態と、寝てしまい見逃している。つまりは、彼女にとっては列車はゆりかごであって、何を隠そう、彼女の鉄道好きは電車に乗って寝ることが好きという事なのかもしれない。そういう自分も新幹線の車内で数時間読書が出来ると楽しみにしながら、半分以上を寝て過ごしてしまうから、その気持はよく理解が出来る。
鉄女に与えられたミッションは「東京地下鉄一日で完乗」「24時間耐久鈍行列車の旅」「東海道53乗り継ぎの旅」「東京-博多こだま号の旅」「四国旧国名駅17(改)札所の旅」といった、物々しいミッションが並んでいる。それぞれどんな旅なのか想像がつくだろうか。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
佐藤正午著「ダンスホール」を読む

中国・四国、近畿、東海地方まで、今日一斉に梅雨明けした。東海地方は例年よりも12日早い梅雨明けだという。今年も暑い長い夏が始まった。
この夏の電気需要は20%ほど節電しないと計画停電をしなければならない。大変厳しい状況である。この夏は何とか乗り切れても、このまま、原発の再起動をしなければ、一年ほどですべての原発が停止してしまう。原発の安全性を主張するのは良いけれども、電気が不安定になれば、企業の海外シフトがさらに進んで、日本に職場が無くなり、巷に失業者が今以上に溢れるようになる。一方、この夏にすでに始まっているように、節約でクーラーを使用しないために、多くのお年寄りが熱中症でなくなるというように、電力不足をもろに受けて、電力弱者という人たちが、多数死んでいくようになりかねない。
こういう電力不足の危険性を一切無視して、今まで散々利用してきた原発を一切排除してしまう方向へ走るのが果たしてよいのであろうか。原発廃棄をいう人々に、その覚悟がはたしてあるのであろうか。自分たちは、テレビも冷蔵庫もクーラーも無い子供時代を経験しているから、それがどんなものであるかを知っているけれども、多くの人たちはそんな生活が想像できないと思う。
原発問題を冷静に考えれば、廃棄するにしても、40年ほどの期間をかけて、原発はコストが高いことを知らしめて、徐々に別のエネルギーに切替えていくしか方法はないと思う。
* * * * * * *
佐藤正午著「ダンスホール」を読んだ。6人の作家が「死様(しにざま)」というテーマで競作の小説を書いていて、本書はその一冊である。佐藤正午という作家は自分は数年前に発見して10冊ほど著書を読んでいる作家である。
気の病で書けなくなった作家が、離婚をして身の回りを整理した。街角で起きた発砲事件を引き金に、様々な偶然が結んだ不思議な男女の縁の連鎖が作られて行く。その連鎖の中で、一度も逢った事の無い男の人生を想像するうちに、いつの間にか作家の本能が刺激されて、ストーリーを紡いでいる。書けない作家がどうやらトンネルから抜けられそうになっている。
一方、小説の最終場面で、作家が描いた自分の人生のストーリーを、間接的に聞いた男は、ストーリーの通りに行動しそうになりながら、わずかな違いに安心してみたりする。
実は、この小説は、冒頭から、作家を主人公のストーリーと、男を主人公にしたストーリーが時間を追いながら交互に出てきて、展開されていく。終わりにきて考えてしまうのは、男のストーリーはわずかな伝聞情報を膨らませて、作家が紡いだストーリーだったのか、あるいは著者が作家と男のストーリーを並行して描いたものだったのか、どうでもよいようであるが、考えさせられてしまった。その辺りは作家が仕組んだ仕掛けにはまったのかもしれない。
この作家の小説の主人公はいずれも作家自身の分身なのだろう。激しい流れを泳いで渡りきるような小説が多いなかで、作家の小説は流れに逆らわないで、悠々と流れて行く。そんな生き方は、現代を生きる読者にやさしい癒しを与えるのではないかと思う。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「世界中が日本に憧れているその理由」を読む

マックス桐島著「世界中が日本に憧れているその理由」という新書版の本を読んだ。著者は、1970年、高校生で映画製作を夢見てアメリカに渡り、以後40年、アメリカで勉強し、ハリウッドで映画俳優などを経たあと、念願の映画プロデューサーとなり、40年経って近年日本へ戻り、宮崎の田舎に定住した経歴の持ち主で、今浦島の目で日本を見て、海外の人々が日本を憧れる理由が解って来たという。
日本にいると、バブルがはじけて以来、ろくなことがなく、日本は日々その力を失って行くように見える。東日本大震災と、その後に起きた原発事故によって、そのとどめを刺されたと思った人は多いだろう。放射能にまみれた列島から外国人が逃げてゆく。そんな風景を諦念をもって眺めていた。
たまたま出版がその直後となり、何を今さらと感じながら、本書を手に取った。読み進めると、アメリカ人は、日本のどんなところに憧れるのか。著者の交友関係の中で、色々と明らかにされて興味深かった。
アメリカでは、日本人は女性男性問わず、実年齢よりも若く見られる。小柄で童顔な上に、日本食で極端に肥った人は少なく、アメリカの男性が男性ホルモン過剰で若くして禿頭が多いのに比べると、日本人は髪が多い。アメリカの食事といえば何でも量が桁違いに多く、ジャンクフードを食べ続け、みるみる肥満になる。健康保険の制度が備わっていないため、いまや糖尿病は貧困層が罹る病気になっている。そんな環境のアメリカ人が日本食に憧れ、スリムな日本人に憧れるのは分る気がする。
日本人は外国から取り入れた食文化を真似するだけに留まらず、レベルを上げた新しい食文化に進化させている。だいたいは食文化を取り入れても似たような食べ物、あるいはまがい物になってしまうのだが、日本人は味や食感、見た目までも追求して止まないため、中には本家をしのぐものもある。これは車や電化製品などの工業製品と同じ道を通っている。
サービス業においても、アメリカから伝わったスーパーマーケットやコンビニ、ハンバーガーショップなど、マニュアル化し過ぎという批判はあるが、アメリカの同種の店の対応などを見てきたものには、まるで違う店に見える。例えばレジが込み合うと、たちまちレジ場が増やされて客を待たせない配慮など、アメリカで長い行列を作らせながら、レジ係が客と無駄話をしていて平気であることを見てくると、カルチャーショックであろう。日本では試着が終った衣料品はたちどころに畳み直されて柵に並ぶが、アメリカではいつまでもぐしゃぐしゃのままであるなど。
その他、アメリカ在住40年の著者ならではの、様々なクール・ジャパンが紹介されている。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |
