平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」
かさぶた日録
イーハトーブの民俗学 - 島田図書館文学講座

このブログに今までに載せた最小の花である。直径5ミリほどではあるが、目を凝らして見れば、小さくても手を抜かないという花の意志を感じる。小さいなりに、好んで訪れる小さなお得意様の虫がいるのだろう。しかし「掃溜め菊」とは、何とも無残なネーミングではないか。
午後、島田図書館文学講座に出席した。講師は八木洋行氏、その講演は色々な場所で何度か聞いている。肩書に「環境民俗学研究家」とある。大学の先生というわけではなく、全く在野の人で、決して学問的な体系などはないけれども、その分、発想が自由で面白い。今日のテーマは「イーハトーブの民俗学」。取り上げた作品はいずれも宮沢賢治の童話、「風の又三郎」「セロ弾きのゴーシュ」「雪渡り」の三作品であった。
「風の又三郎」は、小さな分教場に9月1日に転校生がやってきて、2週間足らずの9月12日に去っていくまでの、短い期間の、分教場の子供たちと転校生の日々の物語である。象徴的なのは、やって来た9月1日は、昔から台風の当り日、二百十日である。(年によって1日ほどのずれはある。)稲がこの頃に花を咲かせ、稲は風媒によって受粉するから、適度の風は必要不可欠であるが、吹きすぎると受粉できなくて、収穫量に大きく影響する。9月の前半は、まさに稲穂にとって風が重要な役割を負っているのである。転校生はまさにその風のようにやってきて、風のように去って行った。最後に、その転校生を指して、独りの生徒が「あいつは風の又三郎だったな」という。
日本海沿岸と富山県から新潟・青森・岩手県では、風の又三郎・風の弥三郎と呼ぶ、風の神信仰がある。遠州では風の弥三郎婆と呼ばれている。ちなみに、風除けの槙の生垣に晩秋に赤く稔る実を「やぞうこぞう」と呼ぶが、これは弥三郎の小僧の意である。また、思うに、富山県七尾の風の盆は、稲の豊作を祈る風祭りと精霊を送る盆が重なった祭りと考えられる。
「セロ弾きのゴーシュ」は活動写真館でセロを弾くゴーシュの話である。下手で、音楽団の団長から練習するように言われ、ゴーシュは毎晩、水車小屋で練習する。すると、動物たちがやってきて聴いている。どうやらそのセロを聞くと、動物たちの病気が治ってしまうようだ。練習の成果があって、楽団の演奏は大成功に終わった。
この話、ゴーシュは、かつて東北で門付けをして歩いた瞽女(ごぜ)さんを示している。往時の瞽女の三味線は、人々を楽しませるだけでなく、牛馬の病を治し、蚕の病気も防いだという。そんな役割を持っていたため、村々で大切にされて目が不自由でも生活できた。ゴーシュが弾いた「印度の虎狩り」という曲、この虎は、垂乳根(たらちね)、つまり女性を示している。島田ゆかりの「虎御前」も「虎瞽女」なのだろう。
「雪渡り」は、冬が終りを告げて、堅雪、凍み雪になると、子供たちの行動範囲が広がり、「堅雪かんこ、凍み雪しんこ‥‥‥」と歌いながら雪の上を好きに歩き、動物たちとの交流が始まる。「堅雪かんこ、凍み雪しんこ」は似た童謡が弘前や雫石などに残っている。
民俗学者たちの出身をみると、雪のめったに降らない地域の人がほとんどである。だから雪国の人たちの生活感覚をよく理解していないことに気付く。たとえば、雪の中から家へ入って来た人に、まず必要なのは、タオルではなくて、座敷箒で、服や頭に着いた雪を払い落すことから始まる。雪国育ちの自分にはよく理解できるが、たぶん静岡の人は理解できないことかもしれない。
最後に「銀河鉄道の夜」について、お盆が終って、精霊(しょうろう)舟を北上川に流す場面に何度か立ち会ったが、夜、北上川の先に、ちょうど天の川があって、北上川が天の川に繋がって、精霊舟はそのまま天の川へ上って行くかのように見えた。宮沢賢治もその景色を見て、「銀河鉄道の夜」を書いたに違いないと思った。
今日の話には目から鱗的な話が多く、面白いと思うとともに、今一度、宮沢賢治の童話を読み直してみようと思った。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「白雲の彼方へ-異聞・橘耕斎」 - 掛川文学鑑賞講座 1

この日曜日、掛川市立中央図書館主催の「文学鑑賞講座」の第1回に参加した。講師は大学講師の和久田雅之氏である。この文学講座は、始まって5、6年続いているという。主に掛川ゆかりの文学の鑑賞をする講座のようだ。たまたま図書館の情報を見て、主に木曜日に、年6回の講座で、空いている曜日なので、申込んでみた。40人の募集に30人ほどの参加であった。市外在住でも参加はOKであった。
幕末、安政の大地震の津波を受けて、プチャーチンが率いるロシアの軍艦ディアナ号が、伊豆近海で遭難し、乗組員が上陸後、沈没した。その話は有名である。500人の乗組員は、色々な船便を使って帰国したが、中に戸田で建造した船で帰った乗組員もいる。掛川藩の若き藩士、増田甲才(後の橘耕斎)は掛川藩を脱藩し、帰国する乗組員に混じり密航して、ロシアへ渡った。そんな話は初めて聞く。
その橘耕斎を発掘して、歴史小説に書いた人がいる。靜岡市出身、千葉在住の、山上籐吾という作家である。その「白雲の彼方へ」という小説が、今日の文学鑑賞の課題である。
文学鑑賞講座どんな段取りで進んで行くのか、興味津々で聞いていた。小説から抜粋した文を読み進めながら、舞台が掛川藩となり、出てくる地名を、受講者に聞いて確認しながら、講義が進んで行く。「逆川の右岸は城内で武家屋敷が並んでいる」という記述では、逆川の流れの方向や、城内が確かに右岸であることを確認をしたり、小泉楼という料亭が出てくると、昔は外に山口楼、富田楼の3軒あった話をしたり、文学の鑑賞というよりも、解説が主になっている。
途中から、文学鑑賞とは何なのだろう。文学鑑賞講座を受講していながら、そんな疑問を浮かべて聞き流していた。鑑賞講座は講師の読書感想を聞く場なのだろうか。
第一回目の講座を受講して、解ったことは、文学鑑賞講座は我々が読書するための切っ掛けを作ってくれる講座だということであった。
この講座では少なくとも3人の人物が紹介されている。まずは講師の和久田雅之氏、次に作家の山上籐吾氏、3人目に主人公の橘耕斎である。
講師の和久田雅之氏には、「靜岡文学散歩」「山頭火、静岡を行く」「伊東の文学」などの著書がある。作家の山上籐吾氏には、「白雲の彼方へ」「花橘に茶の香り」「豆州測量始末」などの著書がある。また、橘耕斎に付いても何冊か本が出ている。これらを知るだけで、読書人にとっては大きな情報となる。図書館が主催する文学鑑賞講座だから、それで十分目的を達している。
まずは、課題図書の「白雲の彼方へ」を図書館に予約して、本日借りてきた。これから読むつもりである。次月も、橘耕斎の続きで、耕斎の人物像に迫るという。それまでに、この小説は読んでおこうと思う。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
静岡県立図書館に行く

駿河古文書会で、初めての発表当番を仰せつかり、文書以外の史料調査などはいらないよといわれて、翻字しただけの資料を用意して渡した。それでも、何か参考になる文献でも目を通して置こうかと思っている時に、会長講演で川崎文昭氏のことを知り、ネットで見ると、氏に、「近世海難と浦証文の研究」という著書があることを知った。これは目を通しておいても良いだろうと思った。
ネットでも新品は売られていないから、古書で調べると、7000円ほどして、購入するには少し辛いから、間違いなく所蔵していると思われる県立図書館から借りて来ようと思い、朝、車で出かけた。
今日は空気がきれいで、靜岡に入ると、青空に富士山が見えた。駐車場に車を置いて、左手に靜岡県立大学のキャンパスを見ながら、グラウンドの西縁を通り、林の中のなだらかな斜面を登って行く。グラウンドを縁取るように桜並木があった。桜が開花したと聞いたのは、ほんの2、3日前のことであったが、もう進んでいる桜は七、八分咲きになっていた。遅れているものも三分咲きくらいにはなっている。
県立図書館は県立美術館の東隣にある。県立図書館の貸出カードは2、3年前に作ってあり、昨晩探し出して持ってきた。案内カウンターで書名のメモを渡すと、司書の女性がパソコンを打ち、レシート状の「資料情報」を出してくれた。勝手がわからない様子に、司書の女性は書棚の位置まで案内して、本を取り出してくれた。立派な装丁の本で、高価なことも納得出来た。
これ借りられますかと聞くと、貸出できますよと言った後、別の本を書棚から出して背表紙を見せて、ここに赤い印があるものは貸出が出来ませんと説明してくれる。このやり取りで、この本を借りる気になっていた。
閲覧テーブルで「近世海難と浦証文の研究」をパラパラと拾い読みした。幾つかの論文をまとめた本で、県内の浦々の名前だけではなくて、太平洋岸の浦名が出てくるから、範囲が県外にまで広がっている。関西と江戸を行き来する廻船は多く、昔の船では、海難事故は珍しいことではなかった。遭難した廻船がたどり着いた浦では、浦役人が立会い、遭難の状況を細かく調べて、遭難の証明書を作成した。それを「浦証文」と呼ぶ。
けっこう悪さをする船乗りも居て、途中で荷を降ろし、横流ししておいて、遭難を装うような手合いも居たらしい。そのような問題も出ているのであろうか。先ほどの司書に借りると告げたところ、まずはカードの更新(住所や電話番号の変更がないかどうかのチェック)を行い、この本は貸し出し出来ませんと、背表紙の赤い印を見せた。確かに赤い印があった。どこで行き違ったのだろう。
自分はこの本が借りられるかどうか確認した積りだったが、司書の女性は一般論として答え、一般論として赤い印のある本は貸し出せないと説明したのであろう。こんな行き違いは時々ある。悔しいけれども、赤い印を確認しなかった自分が悪いのであろう。本はこちらで書棚に返して置きますと司書は気の毒そうに言った。後で見ると、「資料情報」には「貸可資料」とあった。この「貸可」とはどういう意味なのだろう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「キャパの十字架」を読む

沢木耕太郎著「キャパの十字架」を読んだ。推理小説を読む勢いで読んでしまった。
沢木耕太郎といえばノンフィクション作家として有名である。かつて、伝説の戦場写真家としてしられるロバート・キャパについて書かれた本を翻訳するなど、キャパに大変注目し、評価している。その作家が、ロバート・キャパが戦場写真家として世に出た、最高傑作「崩れ落ちる兵士」が、ヤラセでしかも盗作だと論証するセンセーショナルな本である。内容については先にNHK特集で放映されたので解っていたのだが、この本でより理解が出来た。
1930年代の後半に、左派人民戦線政府と、フランコが率いる右派反乱軍が戦ったスペイン内戦は、第二次世界大戦の前哨戦といわれる。若き写真家のロバート・キャパは恋人のゲルタ・タローと、内戦が始まったスペインに行く。二人ともユダヤ人でファッシズムの台頭するドイツを抜け出し、フランスからスペインの、反ファッシズムの人民戦線政府側に入り、戦場を撮ろうとしたけれども、なかなか戦場に遭遇できない。
そこで人民戦線の兵士に頼んで、模擬戦闘シーンをカメラに収めておいた。デジカメのない時代、カメラに何が撮れたのかは現像して見なければ判らない。戦場カメラマンはフィルムのままで、後方に送り、現像して報道写真として使うことは、後方部隊に任されていたようだ。カメラマンは帰ってからどのような写真が撮れて、どのように報道写真として使われたかを知ることになる。
「崩れ落ちる兵士」と名付けられた1枚は、模擬戦闘シーン撮影時に、丘の斜面で滑って後ろに倒れそうになり、銃を後ろへ放り出す瞬間が偶然にカメラに撮れてしまった。事情を知らない後方部隊は、戦闘中に弾丸を受けて後ろへ弾き飛ばされる瞬間を捉えたものとして発表してしまった。キャバが戻ると新進戦場カメラマンとして迎えられ、今さら模擬戦闘シーンだったとは言えなくなってしまった。悪いことには、その1枚はキャパの撮影したものですらなかった。恋人のゲルタがたまたま撮影したものであった。
否定できなくなったキャバは、その後のカメラマン人生で、重い十字架を背負うことになった。あの1枚を越える戦闘写真を撮らない限り、背の十字架は下せない。キャバは自らの身を、常に最前線に置いて、傑作をねらった。
ようやく、あの1枚を越える写真がノルマンディ上陸作戦で撮れた。銃弾の飛び交う中を、兵士より先に上陸して、振り返ってその兵士を撮った。これは大変なことで、カメラマンは敵に背を見せる形になり、危険極まりなく、誰にもできないことであった。
「崩れ落ちる兵士」は今でも、敗れた人民戦線側の記念すべき1枚となっている。ノルマンディ上陸作戦の1枚も、激戦だった上陸作戦を象徴する写真となっている。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
鴎外の文学とその影響 - 島田文学講座

島田文学講座も今日で3回目、最終回を迎えた。今日のテーマは「鴎外の文学とその影響」である。鴎外の文学は次代の青年たちに大きな影響を与えた。講師は以下5項目を挙げる。
1.「舞姫」や「即興詩人」のロマンチシズムは多くの読者や若い作家に強い印象を与えた。
2.「舞姫論争」や「没理想論争」など、正面から論争して、論敵を徹底的に攻撃した。文学論争とは何かを実践で示したといえる。
3.「歴史離れ」の小説「山椒大夫」、「歴史そのまま」を徹底した史伝物の世界(代表作「渋江抽斎」)と、歴史小説の二つのあり方を示した。
4.明白な主題を持つ「高瀬舟」などは、芥川龍之介や菊池寛のテーマ小説の先駆けとなった。
5.「渋江抽斎」などに見られる徹底した考証主義は現代の作家たちにも手本となり、強い影響を与えてきた。
一方の旗手、漱石が多くの弟子を持ち、弟子たちが漱石のもとに入り浸りで、仕事にならないと、週に木曜日だけを解放(「木曜会」と呼ばれる)するように限ったといわれるほどであったのに対して、鴎外は直接的な弟子は全く持たなかった。漱石の日常のエピソードは多くは弟子たちによって書き残されているのに対して、鴎外の姿は弟子がいない分、一族の出世頭として、多くの文学的素養のある係累によって書き残された。言い方を変えれば、鴎外はそれらの題材となって、多くの親族を没後も営々と養ってきたともいえる。以下へ親族たちによって書き残されたものの幾つかを示す。
1.実弟、森潤三郎編「鴎外遺珠と思い出」(1933昭和書房)
同 著「鴎外森林太郎」(1983森北出版)
2.実妹、小金井喜美子著「鴎外の思い出」(1956八木書店)
同 著「森鴎外の系族」(1983日本図書センター)
3.後妻、森しげ著「あだ花」「波瀾」(1983筑摩書房、明治女流文学集2所収)
4.長男、森於菟著「父親としての森鴎外」(1969筑摩書房)
5.長女、森茉莉著「父の帽子」(1991講談社文芸文庫)
同 著「記憶の絵」(1992ちくま文庫、「全集」8巻筑摩)
6.次女、小森杏奴著「晩年の父」(1981岩波書店)
同 著「朽葉色のショオル」(1977春秋社)
同 著「不遇の人鴎外」(1982求龍堂)
7.三男、森類著「鴎外の子供たち」(1995ちくま文庫)
上記は、鴎外の兄弟、妻、子供に限ったが、それ以外にも傍系などを含めるとまだまだたくさんの鴎外を描いた本がある。
鴎外の最初の妻、登志子は、この明細にはない。登志子は海軍中将男爵赤松則良の長女という名門の出であったが、長男於菟を産んで程なく離別されている。文学的な熱気にあった森家の中で、良家の子女として嫁いだ登志子は、一人浮いていたのであろう。家風に合わない嫁をはじき出してしまう、森一族の結束の固さを改めて感じるエピソードである。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
鴎外の歴史小説 - 島田文学講座

小さく、子供館の音楽が聞こえていた)
明日より、我が家の回線がようやく光回線に切り替わります。ところが手続きが遅れたために、ネットへ接続までに数日を要することが判明しました。このブログもその間休載となります。ご了解下さい。
島田文学講座の続きである。
明治45年に鴎外は「かのように」という小説を書く。主人公が歴史学者で、日本という伝統や特殊な国家思想や神話が温存されている国において、歴史を研究するものの苦衷を述べている。この頃から鴎外は歴史に取材した小説を志向したと思われる。大正元年、鴎外の歴史小説の第一作は「興津弥五右衛門の遺書」で、明治天皇に殉死した乃木希典夫妻の事件を予見したような作品であった。作品は事件の前に脱稿されていたといわれる。さらに翌年、同じく武士の殉死を扱った「阿部一族」を書いた。「忠興公以来御三代殉死の面々」と題する細川藩に伝わる古文書がもとになっている。
大正5年に書かれた「渋江抽斎」に代表される史伝群を、54歳から5年ほどの間に、新聞に連載した。「津下四郎左衛門」「椙原品」「寿阿弥の手紙」「伊沢蘭軒」「都甲太兵衛」「鈴木藤吉郎」「細木香以」「小嶋宝素」「北条霞亭」がそれである。
それらの作品群について、鴎外は「歴史其儘と歴史離れ」と題して、次のように書いている。
私が近頃書いた、歴史上の人物を取り扱った作品は、小説だとか、小説でないとか云って、友人間にも議論がある。(中略)小説には、事実を自由に取捨して、纏まりを付けたあとがある習いであるに、あの類いの作品にはそれがないからである。(中略)こういう手段を、わたくしは近頃小説を書く時、全く斥けているのである。なぜそうしたかと云うと、その動機は簡単である。わたくしは史料を調べて見て、その中に窺われる「自然」を尊重する念を発した。そしてそれをみだりに変更するのが厭になった。これが一つである。わたくしは又現存の人が自家の生活をありの儘に書くのを見て、現在がありの儘に書いて好いなら、過去も書いて好い筈だと思った。これが二つである。
これは、当時、大いに流行った、自然主義文学を頭に置いて書かれている。そう来たか、といった感じである。鴎外のこの考え方は、ある意味で納得できるけれども、人の人生は何も起きないで淡々と進むのが常で、そのまま書かれては、読むにつらい作品となる。鴎外はさらに続けている。
わたくしは歴史の「自然」を変更することを嫌って、知らず識らず歴史に縛られた。わたくしはこの縛の下に喘ぎ苦しんだ。そしてこれを脱せようと思った。
こうして、歴史から離れて書いた作品が「山椒大夫」で、鴎外は「山椒大夫」の舞台裏を詳しく書いている。安楽死を扱った「高瀬舟」も、同じ系統の小説であろう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
鴎外の「舞姫」を読む - 島田文学講座

午後、島田文学講座の第2回へ出席した。先週に続いて、「舞姫」を読んでいく。
幕末から明治に掛けて、日本へやって来た欧米人と日本の女性との恋は、「蝶々夫人」や「唐人お吉」に代表されるように、多くの物語を産んできた。「舞姫」はこれらの物語とは逆に、日本から西欧に留学した明治のエリートと、西欧の女性との物語である。明治のエリートたちは西欧へ留学などで出向き、その多くは西欧の女性を現地妻にしていたという。鴎外もその例外ではなかった。同じ留学をしながら、漱石にはそのような影が無かった。しかし、その分、ロンドンで気鬱の病に捕らわれていた。
先週に引続き、「舞姫」のモデル探しが続けられた。作品鑑賞のポイントがそのモデル探しであるといわんばかりの講義内容で、少し違うように思ったが、興味は引かれる。「舞姫」の主人公、太田豊太郎は鴎外自身に間違いないけれども、多くの点で鴎外の人生との違いがある。
その家族構成は多くの点で実人生と変えている。早く失ったとする父はまだ息災であり、一人っ子というが実際は3人兄弟であった。母の死も鴎外が55歳の時で、まだまだ先の話しである。ドイツの恋人エリスはエリス・ワイゲルトという実在の女性で、日本へ帰る鴎外を追いかけて、来日している。但し、エリスの妊娠や発狂などは鴎外の創作である。病状の描写などは医者としての鴎外の面目躍如といったところである。
「舞姫」は帰国途中のサイゴンの港に停泊中の船中で書いたことになっているから、エリスの来日のことは後日談なのだが、来日したエリスに鴎外が会ったかどうかは明白ではなく、解っていることは、鴎外の兄弟たちがエリスに会い、納得させて、問題を起こすことなく、帰国させていることである。
鴎外は一族にとっては出世頭、希望の星であり、スキャンダルで失脚させるわけには行かなかった。封建的な家族制度の名残りをたっぷりと残した明治時代にあって、近代的な自我に目覚めた鴎外も、一族や国家の期待である立身出世を投げ打つことは出来なかった。これは鴎外にとっては、一種の挫折であり、それこそ「舞姫」の創作動機になったものだと思われる。
「舞姫」の主人公は、友人相沢謙吉の諫言と活躍によって、修羅場から抜け出し、復権して帰国の途に着くことが出来た。「舞姫」は最後に次の一文で終わる。
嗚呼、相沢謙吉が如き良友は世にまた得がたかるべし。されど我脳裡に一点の彼を憎むこころ今日までも残れりけり。
鴎外はこのあと、続けて「うたかたの記」「文づかい」という、ドイツを背景とする小説を発表し、「舞姫」と合わせて、ドイツ記念三部作といわれる。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
島田図書館の文学講座へ出席

この先でアプト式の区間に入る)
午後、島田図書館主催の島田文学講座へ出席した。講師は水島雅久氏である。演題は「森鴎外、人と文学」、昨年は森鴎外生誕150年に当るために、取り上げたという。今日から3回の講座である。今日は「『舞姫』と鴎外の生涯」と銘打ち、鴎外の小説の中でもっともポピュラーな作品の「舞姫」を読んでいく。
島田図書館が、駅前のユニー跡地に建った「オビリア」に移転して、初めての文学講座であった。近くの駐車場は30分を越すと有料になるので、市役所の駐車場に車を停め、10分ほど歩く。受講者は40名ほどで、熟年の女性が多い。
新しい試みとして、オーバーヘッドプロジェクターを使い、フィルムに話しの要約を、同時通訳のように書き込んで示す「要約筆記」という方法を、数人のボランティアの皆さんが、交替で行ってくれた。耳が遠いお年寄りなどには、手話の心得がなくても、これなら伝わる。テレビでも近年、日本語を日本語で示す字幕が増えてきたが、そんなテレビの字幕のようなものである。
意外に的確に要約が書かれる。その手際の良さに見惚れてしまった。近年は文字を手書きすることが減り、漢字を書けといわれると、書けなくなってきている。そんな漢字混じりの言葉を、きれいな字で、すばやく書くというのは、すごいことである。
しかし中にはこんなこともある。講師の父親が出征したときの話が出たとき、そのボランティアの女性は「出征」が解らず、「出生」→「終戦」→「出生」と書き迷って、仲間に教わって漸く「出征」にたどり着いた。戦後60数年間、出征した日本人は一人もいない。若い世代にとっさに出てこなくても不思議はない。「出征」が死語になるような世界になってほしいものである。
受講者には、テキストとして「舞姫」原文のプリントが渡された。旧漢字、旧仮名遣いで文語調の名文と評判の高い鴎外の文である。高校の国語教師歴が40年を越す講師は、鴎外の文を教室で読み進みながら、名文に酔っているのは自分一人で、生徒たちはきょとんとしていたと述懐した。
話しは少し脱線するが、古文書の解読を始めて、自分が旧漢字にも旧仮名遣いとも、ほとんど抵抗なく読んでいることに、改めて気付いた。戦後生まれだから、当用漢字、新仮名遣いに切り替わり、学校で教わった記憶はない。どうして抵抗無く読めるのだろう。
実は、故郷の我が家は戦前に古本屋を営んでいて、戦後商売は止めたが、本棚には、売れ残った古本がたくさん残っていた。まともな全集があるわけではないが、自然にその中から本を持ってきて読んでいた。戦前の文学書は、すべて旧漢字、旧仮名遣いで、文語調の文章が多い。子供になかなか読めるものではないが、一つ、すばらしいことは、すべての漢字にルビが振られ、仮名さえ読めれば読めるのである。半分も理解できなくても、それらを読んでいるうちに、旧漢字にも、旧仮名遣いにも抵抗が無くなっていた。両刀使いだから、たまに旧仮名遣いの本を読むことがあっても、旧仮名遣いに気付かないほどである。
今日の講座は、「舞姫」の途中まで読んで、時間になってしまった。一週間後に第2回があるから、講座内容については次週に書く。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「無法者(アウトロー)」を読む
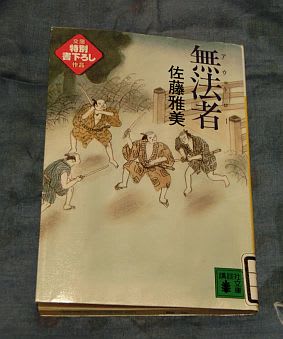
天保年中に起きた、下総国の笹川繁蔵と飯岡助五郎、この両者のヤクザの抗争事件は、天保水滸伝として、講談や浪曲の題材になった。映画にもなった。この話を知っているかと聞かれれば、名前くらいは、としか言えない。佐藤雅美著の「無法者(アウトロー)」はこの抗争事件を描いた小説である。
両者ともにアウトローの話が正史に残ることはない。講談や浪曲の題材は、ほとんど人伝てに聞いた話に枝葉をつけ、解釈が付けられて、ストーリとして編まれたものである。助五郎は、網元で、ばくち打ちの上、関八州廻りの道案内を勤めていて、ヤクザと関八州廻りの手先の、二足のわらじを履いており、ヤクザの喧嘩に、八州廻りの召捕り状を使って向かった。返り討ちされたけれども、逃げた繁蔵はお尋ね者になった。ほとぼりを冷まし、3年後に戻った繁蔵を待ち伏せして闇討ちにするなど、助五郎の行動は卑怯だと感じられたのだろう。判官びいきもあって、講談や浪曲では、助五郎は敵役になり、繁蔵は悲劇のヒーローとして語られてきた。
「無法者(アウトロー)」という小説は、作られた虚像を廃し、両者の実像に迫ろうとした小説に見えた。正史に無いものを、どのように掘り起こすのか。読んでいくと、随所に古文書の片鱗が出てくる。作家は古文書を読むことで実像に迫ろうとしたのだろうと思った。繁蔵は漢学を学んだというから、文字は読めたのだろうが、助五郎は読み書きが出来なかった。読み書きの出来る手下を秘書のように使っていた。けれども両者が書き残したものは何もなく、手掛かりは、乱暴狼藉を訴える訴状、願い書などの文書、召捕り状や人相書、召捕られ、取り調べの関連書類などから、事件を再構成して実像に迫ろうとしたもののようだ。もちろん、判らない詳細は作家の力が試される部分である。
逃げた繁蔵の人相書を作るための問答が描かれている。「歳は?」「三十五、六」「丈は」「高こうございます」「やせている方か、肥っている方か」「中肉です」「眉は?」「濃いほうです」「目は」「細いほう」‥‥
人相書と言っても似顔絵が画かれるわけではなく、聞き取ったものを箇条書きにしたものである。人相書を古文書講座で読んだことがあるが、絵にしなかったのは、印刷技術の無いころは、人相書が回ると全国の村役人にまで触れが回る。村役人はそれを写して自分の控えとする。絵であったら、写し続けるうちに、似ても似付かぬものになってしまうだろう。
しかし、人相書きで捕まる例はほとんどなく、役人のところに人相書きが何枚も溜まっていくのが通常であった。
参考文献をみると、作家が直接古文書を読んだわけではなくて、学者、郷土史家や好事家が古文書を研究してまとめた本を参考にしたようであった。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
「孤愁 サウダーデ」を読む
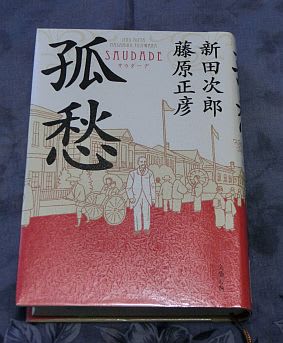
安倍内閣が今日発足した。党を挙げての新内閣らしく、大臣たちの顔ぶれに安定感を感じる。しかも平均年齢が57歳とずいぶん若返った。民主党に政権を渡していたこの3年半、自民党は生まれ変われたのであろうか。有権者は期待と不安を持って注目している。この期待感があきらめにならないように、頑張ってもらいたいと思う。
一つ、最近気付いたことがある。選挙で大敗し多くの議員がバッチを失い、野に下った3年半に、それまで魑魅魍魎が住むように見えた自民党から、そんな部分の多くが党外に去り、あるいは引退して、大勝の今回はたくさんの新しい顔になって戻ってきた。ずいぶん新鮮に感じるようになった。
前回の民主党の大勝のときも、国会が新人だらけになってしまったが、今回も同じことを感じる。新人たちは単に投票マシーンになってしまわないで、それぞれが自分の専門分野を持って、その道のプロフェッショナルになれるように猛勉強してもらいたい。その頑張りが2期目以降に繋がると思うべきである。
安倍首相は今回再登板であるが、歴代の総理で最登板したのは、戦後間もなくの吉田茂首相以来のことである。政界に2世、3世議員が目立つけれども、安倍首相は祖父の岸信介、父の安倍晋太郎に継ぐ3世議員である。父を越え、祖父を越えた政治家と讃えられるように、なってもらいたいものである。
* * * * * * *
最近、「孤愁 サウダーデ」という小説を読んだ。明治時代、ポルトガルの外交官として来日し、日本に魅せられ、文筆家として日本紹介し続け、生涯日本に住んで、徳島でその生涯を終えた、モラエスを描いた小説である。新田次郎がその最晩年に取組み、日露戦争が始まったところで絶筆となり、未完に終わっていた作品である。昔、未完の作品ながら読んだことがあった。最近、新田次郎の息子の数学者にしてエッセイストの藤原正彦氏が、父の集めた資料を引き継ぎ、父が取材したすべての地を再訪して、死んだ父の年齢になるのを待って、「孤愁 サウダーデ」を書き継いで完成させたと聞き、早速図書館で借りて、600ページを越す大作を読み終えた。
議員ほどではないが、作家にも2世、3世の作家がいる。親の引きでそこそこまでにはなるが、親を越える作家になる者は少ない。藤原正彦氏もエッセイストとしては名声を上げているが、偉大な父、新田次郎に追い付くにはまだまだと思った。モラエスの後半生を追って描きながら、作家の思いが出てしまうのは当然のことであるが、読んでいく間に、これはモラエスの思いではなくて、藤原正彦氏の考えだろうと思ってしまう部分があちこちにあった。新田次郎が書いた前半には全く感じられなかったことである。その分、物語に没頭できる前半に比べて、後半は時々覚醒させられ、興ざめに感じる部分があって気になった。藤原正彦氏は小説家としてはまだまだなのだろう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ |
