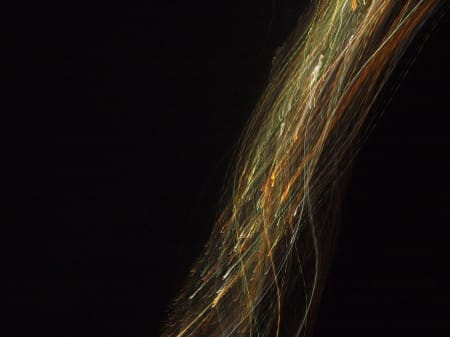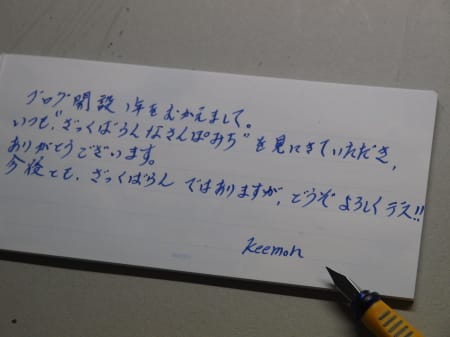どうも。
欧米の植民地からアジアの国々を解放するという側面もありますが、戦争というのは突然起こるものではなく、だんだんに近づいていくものなんでしょうね。そこにいろいろな人間、国家、組織の思惑が絡んできて、、、でも最終的には、傷つくのは戦地になったところの人々、国や家族を守るため人殺しをする兵士、勝とうが負けようが心が受けるダメージは大きいですね。でも、戦争を始めた人間は自らの手を汚すことはないですよね。
とても、簡単な話ではないので・・・僕は聞いた話や残されたものを見て、いつまでも忘れないようにしていきたいと思います。
僕の祖父は、中国やフィリピンミンダナオ島へ工兵として行き、祖母は本土で祖父家族と本土で過ごしたと思います。戦争を知らない僕にはわからない過酷な状況を過ごしたと思います。
数か月前になりますが、僕のお茶づくりをする牧之原台地に”飛行場”という畑の呼び名があり、由来である大井海軍航空隊の痕跡を見に行ってきました。
正門門柱や近くのコミュニティーセンター(寄合所)には当時訓練機として大井海軍航空隊にあったとされる白菊という飛行機のエンジンなどが展示されています。
暑い日が続きますね。
昨夜は久しぶりの雨の音を聴きました。
気づくと秋の虫が鳴いています。
8月は戦争のことを考えますね。
太平洋戦争とも、大東亜戦争とも呼ばれる戦争。
日本も軍国主義であり、アメリカもまた戦争したい、戦争することで国は力を増す、、軍需産業、医療品などそういった産業界も戦争したいし、戦争がお金儲けになることを金持ちたちは知っているんですね。歴史の中で対戦相手双方にお金を貸すなんていうこともしてきたという。
日本は、当初アメリカと開戦せず、イギリス領から攻めるはずだったのに、、アメリカとの開戦をしたのは日本側にアメリカのスパイがいたという話しもありますね。
作戦は筒抜けで真珠湾には最新鋭の戦艦はなかったとか。
開戦しても、各地では激戦を繰り広げ、多くの敵味方、現地民が巻き込まれ、悲惨すぎます。虐殺や暴行、略奪もあり。それとは逆に現地民とののどかな交流があるシーンもあったかもしれません。体重が70キロの兵隊さんが28キロになるほどの、食料・物資の補給もない戦地では敵や味方、現地民の人の肉を食らう状況にならざるを得ません。
戦争末期には日本の本土、沖縄、、東京、広島、長崎、都市から田舎いたるところが爆撃されました。
欧米の植民地からアジアの国々を解放するという側面もありますが、戦争というのは突然起こるものではなく、だんだんに近づいていくものなんでしょうね。そこにいろいろな人間、国家、組織の思惑が絡んできて、、、でも最終的には、傷つくのは戦地になったところの人々、国や家族を守るため人殺しをする兵士、勝とうが負けようが心が受けるダメージは大きいですね。でも、戦争を始めた人間は自らの手を汚すことはないですよね。
とても、簡単な話ではないので・・・僕は聞いた話や残されたものを見て、いつまでも忘れないようにしていきたいと思います。
僕の祖父は、中国やフィリピンミンダナオ島へ工兵として行き、祖母は本土で祖父家族と本土で過ごしたと思います。戦争を知らない僕にはわからない過酷な状況を過ごしたと思います。
数か月前になりますが、僕のお茶づくりをする牧之原台地に”飛行場”という畑の呼び名があり、由来である大井海軍航空隊の痕跡を見に行ってきました。
正門門柱や近くのコミュニティーセンター(寄合所)には当時訓練機として大井海軍航空隊にあったとされる白菊という飛行機のエンジンなどが展示されています。
※写真が前後バラバラですみません。

↑海から引き揚げられたもののようです。





基地があったために、アメリカの飛行機が攻撃にやってくることもあったでしょう。
今なお、アメリカの影響が続く日本。
これからの世代も戦争を考え反省し、戦ったり亡くなった方々に感謝して、平和を守るために忘れてはいけませんね。
土用干しを終えた梅。


なんで人は戦争するんでしょうね。

↑海から引き揚げられたもののようです。





基地があったために、アメリカの飛行機が攻撃にやってくることもあったでしょう。
今なお、アメリカの影響が続く日本。
これからの世代も戦争を考え反省し、戦ったり亡くなった方々に感謝して、平和を守るために忘れてはいけませんね。
土用干しを終えた梅。


なんで人は戦争するんでしょうね。