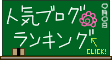2010-2011シーズン聴いたコンサート観たオペラはこちらから。
2010-2011シーズン
.
2011年6月19日(土)2:00-5:00pm
オペラパレス、新国立劇場
.
プッチーニ 蝶々夫人
.
演出、栗山民也
.
蝶々夫人、オルガ・グリャコヴァ
ピンカートン、ゾラン・トドロヴィッチ
シャープレス、甲斐栄次郎
スズキ、大林智子
ゴロー、高橋淳
他
.
イヴ・アベル 指揮
東京フィルハーモニー交響楽団
新国立劇場合唱団
.
●
これだけウェットで艶々で綿々と流れる音楽、明日への勇気は出ないかもしれないが、一生オペラを観聴き続けて死んでいけるなら本望だわ、と思わせる力はある。唐突だがバルビローリがこのオペラを好きだったのはよくわかる。とにかく最初から最後まであふれ出るメロディー、川のように流れるフレーズが心のひだをきっちりと埋めていってくれる。棒のアベルはこのオペラが絶対に得意に違いない。オーケストラは前日のきちんと整理されたハーディング&新日フィルとは比べ物にならないぐらい粗かったが、それでも流れる音楽が美しい。オペラのツボはきっと別のところにあるに違いないと確信させる泣き節はオーケストラも含めて聴きごたえ、観ごたえがありました。
歌とオケが重なる部分の多いオペラですけれど、タイトルロールのグリャコヴァは、全部が彼女のためにあるような舞台でしたね。見栄え、しぐさ、それに目力(めじから)、なにもかもが日本人から見て違和感がなくそれにものすごい迫力。もちろんやや硬めの美しくて巨大な声が劇場全てを飲み込む感じ。イタオペ・ファンが第1幕1時間、第2幕1時間半、吸いつけられて微動だにせず観聴きしていました。そういう自分も全く同じ。吸い取り紙に全部持っていかれました。この綿々とした果てしもない美しさはたしかになにもかも忘れさせてくれる。プッチーニの中でも格別の美しさだ。
来日中のメトが演目としてもってきているラ・ボエーム、この美しさの中に交響曲のような構成感を感じさせる第1,2,3,4楽章。つまり第1,2,3,4幕。蝶々夫人とは大幅に趣を異にする。蝶々夫人の方は構成感なんかどこかへ行っちまって、とにかくひたすらウェットな音楽が流れ続けるだけだ。両方同時に観ようと思えばできるタイミング、ぜいたくすぎるか。
ちょっと話がそれるが、今回のメトのボエームのプロダクションはゼッフィレルリのものと聞きおよびちょっとめまいを感じる。それこそ四半世紀前に数知れず観たメトのボエーム。そのプロダクションがいまだいきている、当時、ゼッフィレルリは、とにかく舞台の上に乗せられるだけの人数を乗せようとした。それだけでは足りず動物も盛りだくさん。アタッカではいる第2幕の行進や2階建てなんかもなにもかも日本の舞台ではメトの再現は無理。どちらかというと声で勝負。現地にいれば声とプロダクションの双方が呼応し合って極度のエンターテイメントになっていることがよくわかる。メトの蝶々夫人の舞台も大きさを感じさせるが、場所設定が日本の昔の家、ということもありどこかコンパクトな感じはあった。メトの得意演目はワーグナーとともにイタオペ。オーケストラにその響きが身についてしまっている。誰が歌おうと歌うオーケストラに変わりはない。
.
マダムバタフライのしなやかさ。一体この音楽はどこからきたのか。構造はないがストーリーだけがある。綿々と流れる音楽と儚いストーリー。食い入るように魅入る聴衆。観る者の心のひだ、隙間にまるで水のように浸み込んでくる。このものすごい説得力。第三者としてではなくまるで自分自身の出来事のように音楽が同化してくる。プッチーニの魅力の一つだな。
舞台は第1,2幕変わりばえしない。動きも最後の場面を除いて動きがない。何もないかというとそうでもなく、どちらかというと光、その陰影、そのようなもので色彩感覚をよく出している。これはこれで非常に美しいもの。シルエット舞台のハミングも美しかった。音楽と舞台の表情が一体化した瞬間で、聴衆は固唾をのんでみまもる。一発勝負ではないイタオペの真髄がここにもあります。
ストーリーはあまりにもやるせなくて男でも泣きたくなる。男泣きではなく、人間泣きです。このようなストーリーによくもこんな美しすぎる音楽をつけた。
歌は書いた通りグリャコヴァが圧倒的な声で安定感も抜群。細かいニュアンスもきっちりと表現できていて、この心理表現オペラの動きを的確に表現できてました。さらにスタイル、容姿のバランスの良さもさることながら、日本人的しぐさが自然で好感、そしてなんといっても大迫力の目力(めじから)、一途な切実さがぐっと伝わってくる。ものすごい迫力。
役的には割に合わないピンカートンですけれど、最後のカーテンコールでお子を抱いてあらわれてまずは憎まれずに済んだ。そのテノールはこのくらいの響きでちょうどいういのではないか。あまりに存在感がありすぎるとまるで正義を勝ち得たような雰囲気になってしまい、こらえきれず去る場でさえ正当化されるかもしれない。それでは悲劇の正義、そのようなものがあるのかどうか知れないが、薄くなってしまう。ケイトの前に自らを捨てる選択肢しかなかった蝶々、痛いほどよくわかる。逃げ場などというところを考えたこともない蝶々、自分の居場所というものをよく知っていた。ならばなぜ、最初から世のなかば常識化していた現地妻になってしまったのか、それを自分は変えれる、そこまでは思わなくても、アメリカ人の本当の心をつかみたかった。みてみたかった。それは己をみることでもある。己が作った悲劇ではある。悲劇はえてしてそういうものかもしれない。哀しくも美しすぎる音楽がホールを包み込む。ああ、なんというプッチーニの音楽。音楽でしか表現できないものだった。
自分を殺すところで子供が正面に対峙する。あれはどういう意味なのだろうか。やりすぎの演出だと思う。障子のシルエットであったならばもう少し違和感が緩和されていたかもしれない。舞台の光と影、花の美しさ、まぶしいほどの純白、それだけで十分な見事な舞台だっただけにこの部分だけは残念。その場では茫然唖然と観ているだけなのだが、あとあとに残る違和感。考えさせられるところは何もない。プッチーニが言いたい心のひだはこんなもんじゃないだろうと思う。
おわり