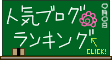●
今年のサマーフェスティヴァルの初日の公演。テーマは、映像と音楽。
冒頭のシェーンベルクは映像無しで演奏のみ。シュニトケとヴァレーズは映像と音楽。それぞれ、映像監督のトークが演奏の前にあり。シュニトケのグラス・ハーモニカの演奏前のトークは監督のフルジャノフスキー本人がステージ上で熱く語った。ヴァレーズの砂漠ではヴィオラの話がヴィデオで18分ほど流れた。
こうやって説明を言葉であらかじめしなければならないというところが致命的であるとするか、まして、映像がついているのに、である。
ある時代の様式感というのがあって、例えばソナタ形式という様式を理解していれば、その時代の音楽については説明などなくても理解して楽しめる、そのような、時代の様式音楽を求めるか、はたまた、いわゆる現代の音楽というものを別の切り口で求めていくのか。
というところなんですが、音楽の多様な広がりを今の時代だから楽しめる、振幅の右端と左端まで見渡せる、これはこれでいいと思う。ただ、両方見渡せるということは双方ともに過去に追いやられてしまっているという感じがなくもない。
.
それで、一曲目のシェーンベルクなんですが、12音階のいわゆるわかりにくいものなんですけれど、最初の12個の音列進行を理解すれば(頭の中で)、その後のヴァリエーション作りはかすかに理解可能。シェーンベルク独特なグレーなペイント、厚い曇り空のような音色は避けることはできないし、ましてこれがどうして映画(架空)の伴奏音楽なのだろうというあたりの理解までに到達するには、彼の音楽をもっと好きにならなければいけない。(実は好き)
一体どうすればこのような音楽を作曲できるようになるのだろうというのは、理論を先にしてその理論で作れば出来上がる。音色旋律とかリズムは後発の技のような気がする。
シェーンベルクはたまにたまらなく聴きたくなることがある。(実は昨年購入したCD、2000枚のうち100枚ぐらいはシェーンベルクだったなぁ。ストラヴィンスキーも同じぐらい買っちゃったけど。)
.
2曲目のシュニトケ。先に書いたように映像監督のフルジャノフスキーが登場して通訳を介した長々とした話があった。この行為、致命的ととるか、説明責任があるととるか。まして映像があるのに、である。
映像は1968年作のアニメ。アニメといっても今風に滑らかに動くものではなく、漫画雑誌の一コマずつを並べたような感じ。名画を並べたコラージュといったものだから、時代も多岐にわたりその多様性に合うような音楽が求められる。同じく1968年にこの映像のために作曲したシュニトケの音楽が流れる。ロマンティックなもの。
グラス・ハーモニカという魔法の楽器がもたらす浮き沈みを表現。
観て聴いて一番最初に感じたのは、例えばベートーヴェンのエロイカはいつも新鮮でグラス・ハーモニカは既に古臭いということ。面白さとは別の次元で。
その感を強めたのは映像。この映像、まるでロシアのオペラでも見ているようなもので、それもボリスとかホヴァンシチーナといったヘビー級なものではなく、わりと現代に近い方のウィットにとんだオペラ、壁崩壊前の東独のような演劇的な表現の感じもなんとなくあって、1968年当時では先取り感覚はあったのであろうが、現代から見れば取り残された後れてきたもののように見えてしまうこと。つまり、典型的な「時代映像」なのである。
.
3曲目はヴァレーズの未完1949-1954作の「砂漠」に、ヴィオラが1994年に映像をつけたもの。ヴァレーズの砂漠にはいわゆるテープ・ミュージックがはいっている。
ちょっと横道にそれますが、テープ・ミュージックいりのもので一番インパクトのあったのはやっぱりヘンツェのトリスタンです。自分の記憶では生演奏は二回聴いたことがあるはずですが、うち一つがこれ。
1984年5月31日のニューヨーク・フィルハーモニックによるもの。ヘンツェの自作自演。
797-Horizon’s 1984 Festival二日目 ヘンツェ ペンデレツキ 両方自作自演1984.5.31 HF-2
798-Horizon’s 1984 Festivalヘンツェ ペンデレツキ の新聞評 HF-2.1
あのときの薄気味悪さ、ゾクゾクするハートの鼓動、奇妙なヴォイス、忘れられませんね。
.
それで、ヴァレーズの方ですけれど、細かい神経が厚く重なり合っている。そんな感じの曲で、雑音のような部分もあります。60年前の流行の先端ですね。テープは3回はいります。
映像自体は具体的なもの(風景といった)。ヴィオラは砂漠に住んでいたことがあって、そこでの生活からクリエートされたもの、一見、音楽とは隔離された世界で想起されるもの、そのような経験が生かされたとヴィデオで語っていたような気がします。偶然映像をつけたのではなく、アンサンブル・モデルンから委嘱されて制作したものと語ってましたね。(たしか)
砂漠という曲ながら映像には、海底、火、砂漠、山、いろいろ出てくる。テープのところは自宅のテーブルでスローモーションでスープをすする男が連続性をもって3回現れ、3回目ではテーブルから床に落としたものが男本人が倒れるという行為も含め、いつの間にか床が水になりそのなかに溶け込むというわりとインパクトがあるもの。
既にある音楽に映像を後でつける行為は、再現芸術としては、結局、既にある映像に生で(実演で)音楽をつけていくしかないのではないかと思う。つまり、既にある音楽に映像をテンポを合わせ映していくのは困難。結局、映像の動きを見ながら音楽をつけていくしかない。実演では必ずそうなる。つまりオペラと同じ。オペラは映像ではなく人の動きを伴った生き物なので映像とは異なり、テンポの伸縮含め音楽に合わせ動かすことはできるのであるが、昨今の電気仕掛けの秒単位までの正確性を持たざるを得ないようなプロダクションでは映像とその特質が似てきてしまっているのではないだろうか。
いわゆる映画音楽のように同時作成されたものでない場合、今回のヴィオラのような堅苦しくて流れない映像に、結果的にならざるをえないのだろう。後で作った映像をまるで先にありきのように再現しないといけない、しなくてもいいがそのようになってしまう、このぎこちなさを拭い去ることはできない。
具体的なストーリー展開をもった内容の映像を先出し音楽につけていくことはできないのだろうか。それは単なる技術のもてあそびに終わってしまう可能性が高いんだろうね。
ただ、ヴァレーズの砂漠の場合、テープ・ミュージックの挿入という新機軸があるため、そそこにひねりを入れた映像構成は比較的簡単に発想、表現できたのだと思われる。むろん、3回挿入されたこの音が、今回の映像のように連続的な内容を求めるものであったのかどうか、そこは考えてみる余地はあるが。解釈を広げるためのヒントとしてはいい出来だとは思うけれど。
多様性とは、ある意味、限界を見せつける行為、そのようにこの日の公演を通して感じました。
おわり