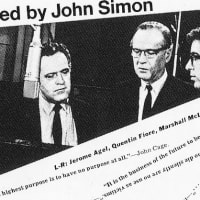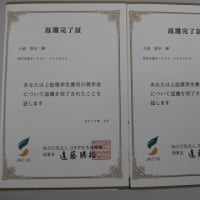金井良太『脳に刻まれたモラルの起源:人はなぜ善を求めるのか』岩波科学ライブラリー, 岩波書店, 2013.
脳の構造から人間の持つ倫理感覚を探る内容。タイトルはちょっと誤解させるところがあり、進化心理学的な説明──ある種の感情は進化の途上でこれこれこういう理由で有利になったために人類に普及した──が展開されるのではなく、「ある種の感情の処理は脳のどこどこの部位で行われている」という生理学的な説明が基本となっている。
はじめの三章は次のような内容。道徳感情は、公平に扱われることなど「個人の尊厳」に関するものと、秩序維持や社会における人の正しい役割など「義務などへの拘束」に関するものの二つに大別できる。これはいわゆるリベラルと保守の違いに当てはまる。それぞれが司る脳の部位は別であり、画像解析をして該当部位の大きさを測れば、その人物がどちらを重視するタイプかある程度わかってしまうそうである。なお、その原因として遺伝の部分的な影響もあるし、歳を重ねれば変化するということもあるとのこと。
本書で紹介されたとある実験によれば“リベラルな大人になる子どもたちは、三歳のときすでに問題に直面したときに乗り越える能力を発揮し、自発的で表現力豊かで、独立心が強いという特徴があった。一方、保守的な大人になる子どもたちは、不確かな状況に置かれると居心地悪く感じ、罪の意識を感じやすく、怖い思いをすると固まってしまうような子どもだった”(p.39)だって。酷い言われようだな。
このほか、信頼感とオキシトシンなるホルモンの関係、ただ乗り行為を思いとどまらせる「評判」のシステム、幸福感および孤独感と関係する脳の部位、などのトピックが並んでいる。短いので読みやすいが、考察は控えめである。もっと著者の持論を展開してくれたほうが面白くなったと思えるが、このシリーズはいつもこんな感じかな。
脳の構造から人間の持つ倫理感覚を探る内容。タイトルはちょっと誤解させるところがあり、進化心理学的な説明──ある種の感情は進化の途上でこれこれこういう理由で有利になったために人類に普及した──が展開されるのではなく、「ある種の感情の処理は脳のどこどこの部位で行われている」という生理学的な説明が基本となっている。
はじめの三章は次のような内容。道徳感情は、公平に扱われることなど「個人の尊厳」に関するものと、秩序維持や社会における人の正しい役割など「義務などへの拘束」に関するものの二つに大別できる。これはいわゆるリベラルと保守の違いに当てはまる。それぞれが司る脳の部位は別であり、画像解析をして該当部位の大きさを測れば、その人物がどちらを重視するタイプかある程度わかってしまうそうである。なお、その原因として遺伝の部分的な影響もあるし、歳を重ねれば変化するということもあるとのこと。
本書で紹介されたとある実験によれば“リベラルな大人になる子どもたちは、三歳のときすでに問題に直面したときに乗り越える能力を発揮し、自発的で表現力豊かで、独立心が強いという特徴があった。一方、保守的な大人になる子どもたちは、不確かな状況に置かれると居心地悪く感じ、罪の意識を感じやすく、怖い思いをすると固まってしまうような子どもだった”(p.39)だって。酷い言われようだな。
このほか、信頼感とオキシトシンなるホルモンの関係、ただ乗り行為を思いとどまらせる「評判」のシステム、幸福感および孤独感と関係する脳の部位、などのトピックが並んでいる。短いので読みやすいが、考察は控えめである。もっと著者の持論を展開してくれたほうが面白くなったと思えるが、このシリーズはいつもこんな感じかな。