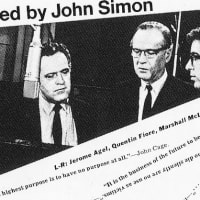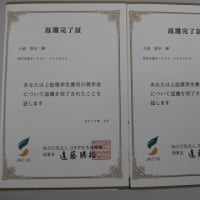川口大司編『日本の労働市場:経済学者の視点』有斐閣, 2017.
労働経済学の教科書で、編者による序章と終章と、20人に及ぶ執筆者による14章という構成となっている。読者ターゲットは経済学部の大学院生以上だろう。「RCT」だとか「回帰不連続デザイン」とかいった因果分析の概念がさらっと言及されるし、章によっては回帰分析の表も提示される。というわけで初学者にわかりやすい内容ではないのだけれども、この分野の重要な研究成果が紹介されていてとても参考になる。
構成は次のとおり。最初の三章は、日本の会社における人事、昇進、採用、トレーニング、および学校での教育を含めた人的資本形成である。続く七章は、地方経済、高齢者、女性、外国人労働者、障がい者、失業保険、生活保護がそれぞれの章のトピックになっている。これらでは関連する法制度についても簡単に解説されている。最後の四章は、因果分析、労働経済学の理論、経済学における実験、行動経済学を扱っている。
次のような知見が披瀝されている。正社員と非正社員の間に賃金を筆頭に様々な格差があること(これは通説通りだろう)、高齢者の雇用継続によって必ずしも若者の就労機会が奪われるわけではないこと、男女間格差もまだ残っているものの以前に比べれば改善されていること、日本の失業保険は失業者を十分カバーできていないこと、などなど。まだわかっていないことも多くて、外国人労働者のインパクトや、障がい者雇用による企業への影響などは今後の検証待ちであるとのことである。
教育学科所属の僕としては、やはり「3章 人的資本と教育政策」(佐野晋平)が興味深いものだった。世間では若者に大学進学を勧め、政府にはそれを支援するよう促す雰囲気がある。しかし、学力差からくる大学進学/非進学というセレクション・バイアスがあり、学歴がもたらす賃金の差は能力の差を反映しているだけかもしれない。この批判はカプラン著と一緒だ。というわけで、この差を統制して大卒と高卒の賃金の差への影響を推定したところ、平均して年でおおよそ8%とのこと。直観では「悪くない値」だと思った。12章で大卒者の供給が増えるとその賃金も下がる、と暗にただし書きされるけれども。また、大学ランクや学部によっても変わるだろう。
以上。僕が大学院生だった20年前にもいくつか労働経済学の教科書を読んだ記憶があるが、どれも理論重視の説明で事例は欧米のことばかり、というような内容だった。本書は実証研究の結果が多く紹介されており、日本での研究成果も多い。残された課題も明確だ。この分野の研究の進展をまざまざと見せつけられる。また、因果分析の強力さもよくわかる。
労働経済学の教科書で、編者による序章と終章と、20人に及ぶ執筆者による14章という構成となっている。読者ターゲットは経済学部の大学院生以上だろう。「RCT」だとか「回帰不連続デザイン」とかいった因果分析の概念がさらっと言及されるし、章によっては回帰分析の表も提示される。というわけで初学者にわかりやすい内容ではないのだけれども、この分野の重要な研究成果が紹介されていてとても参考になる。
構成は次のとおり。最初の三章は、日本の会社における人事、昇進、採用、トレーニング、および学校での教育を含めた人的資本形成である。続く七章は、地方経済、高齢者、女性、外国人労働者、障がい者、失業保険、生活保護がそれぞれの章のトピックになっている。これらでは関連する法制度についても簡単に解説されている。最後の四章は、因果分析、労働経済学の理論、経済学における実験、行動経済学を扱っている。
次のような知見が披瀝されている。正社員と非正社員の間に賃金を筆頭に様々な格差があること(これは通説通りだろう)、高齢者の雇用継続によって必ずしも若者の就労機会が奪われるわけではないこと、男女間格差もまだ残っているものの以前に比べれば改善されていること、日本の失業保険は失業者を十分カバーできていないこと、などなど。まだわかっていないことも多くて、外国人労働者のインパクトや、障がい者雇用による企業への影響などは今後の検証待ちであるとのことである。
教育学科所属の僕としては、やはり「3章 人的資本と教育政策」(佐野晋平)が興味深いものだった。世間では若者に大学進学を勧め、政府にはそれを支援するよう促す雰囲気がある。しかし、学力差からくる大学進学/非進学というセレクション・バイアスがあり、学歴がもたらす賃金の差は能力の差を反映しているだけかもしれない。この批判はカプラン著と一緒だ。というわけで、この差を統制して大卒と高卒の賃金の差への影響を推定したところ、平均して年でおおよそ8%とのこと。直観では「悪くない値」だと思った。12章で大卒者の供給が増えるとその賃金も下がる、と暗にただし書きされるけれども。また、大学ランクや学部によっても変わるだろう。
以上。僕が大学院生だった20年前にもいくつか労働経済学の教科書を読んだ記憶があるが、どれも理論重視の説明で事例は欧米のことばかり、というような内容だった。本書は実証研究の結果が多く紹介されており、日本での研究成果も多い。残された課題も明確だ。この分野の研究の進展をまざまざと見せつけられる。また、因果分析の強力さもよくわかる。