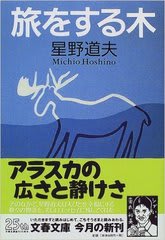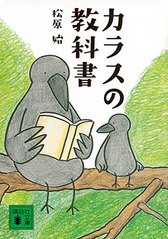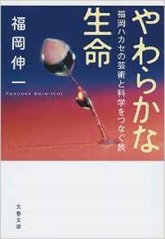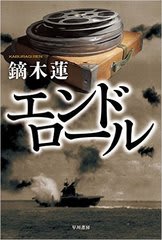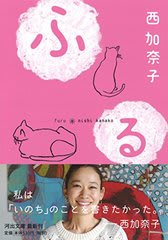あるピアノコンクールの予選から本選まで次々と奏でられる曲を
読んでいるのに、まるでその場で聞いているかのように見事に言葉で表現された作品。
2016年下半期直木賞受賞作品

たまたま知っている曲の場面があり、そこでは恩田さんの文章とともに
嵐のように音が頭の中に押し寄せてきてちょっと興奮しました。
作品に登場する一つ一つの曲を実際に聴きながらこの本を読んだらすごいことになるだろうと思う。
若いピアニストたち、審査員たち、それを囲む人々、
それぞれの人生も曲に重なり、たくさんのイメージが描かれます。
さらにそのイメージは、外の自然へと解放されるように導かれ、
そして気づくのです。
音楽は自然の中にあふれていると。
有名なクラシック音楽を作曲したかつての巨匠たちも、
自然の中に耳を傾け楽しい音を聞き取り楽譜に表現したのでしょう。
「音楽を外へ連れ出した」風間塵のピアノを本当に聞くことができたならどんなにすばらしいだろう
会員登録が必要ですが、こんなページもあります
⇒蜜蜂と遠雷コンクール曲プレイリスト
恩田さんの作品は何冊か入り込めずそれ以来敬遠していたけど、
絶えず挑戦的に実験しているような作品群ですね。
恩田陸 1964年生まれ
読んでいるのに、まるでその場で聞いているかのように見事に言葉で表現された作品。
2016年下半期直木賞受賞作品

たまたま知っている曲の場面があり、そこでは恩田さんの文章とともに
嵐のように音が頭の中に押し寄せてきてちょっと興奮しました。
作品に登場する一つ一つの曲を実際に聴きながらこの本を読んだらすごいことになるだろうと思う。
若いピアニストたち、審査員たち、それを囲む人々、
それぞれの人生も曲に重なり、たくさんのイメージが描かれます。
さらにそのイメージは、外の自然へと解放されるように導かれ、
そして気づくのです。
音楽は自然の中にあふれていると。
有名なクラシック音楽を作曲したかつての巨匠たちも、
自然の中に耳を傾け楽しい音を聞き取り楽譜に表現したのでしょう。
「音楽を外へ連れ出した」風間塵のピアノを本当に聞くことができたならどんなにすばらしいだろう

会員登録が必要ですが、こんなページもあります
⇒蜜蜂と遠雷コンクール曲プレイリスト
恩田さんの作品は何冊か入り込めずそれ以来敬遠していたけど、
絶えず挑戦的に実験しているような作品群ですね。
恩田陸 1964年生まれ















 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック




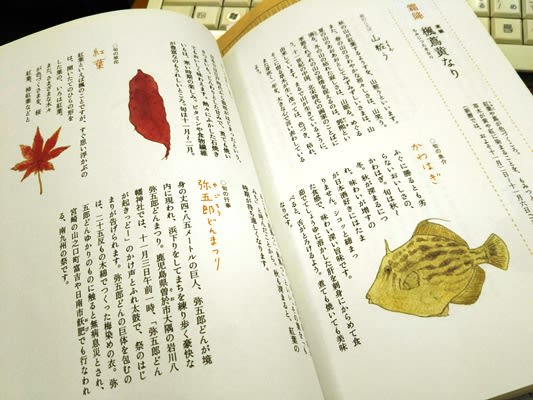

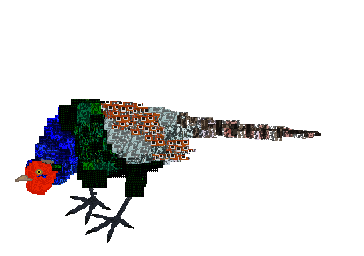
 全国実力薬局100選子宝部門
全国実力薬局100選子宝部門