なぜ生き死にを繰り返すのか?
なぜそうして命を紡ぐのか? なぜそう行動するのか?
もちろんヒトだけでなく微生物からあらゆる動植物に至るまで。
そんな根源的な自然科学のテーマを梨木果歩の文学力で追及した小説です。
その物語は、
先祖伝来のぬか床をもらいうけた若い女性、久美の生活から始まります。
朝晩欠かさずぬか床をかきまぜなければならない生活。
しだいに自分の生活が(思考さえも)ぬか床に支配されているのでは?
と危機感を感じながらも、不思議にその状況に居心地の良さも感じて抜け出られないのです。

久美は事態をとても冷静に的確に判断できる女性です。
彼女の思いやことばは読んでいてとてもすっきりしていて、
なるほど、そうよねえ

と納得してしまいます。

さて、それでもテーマがテーマですから、
久美の分析力をもってしてもしばしば考え込んでしまいます。
もとは、たったひとつの小さな細胞がある日、ぽつんと地球に生まれたとして、
その命が、絶対的な孤独を感じながらも、ずっと在り続けるという夢を抱いた?
それが結果として、
いくつもの進化の多様性を果たしながら命は連綿と繰り返されている?
ある時はクローン増殖を淡々と繰り返しながら、
またある時は自己と他者の間に壁を作りながら、
またある時は自己の死をいとわず他者と一体化し新しい命を発生させながら・・・
もちろん明快な答えがでるわけではありませんが、
微生物らを
「気配を生みだす世界の住民」と表現しています。
そして、
「寄生され自分の上に幾重にも重なった他者があり、自分の身一つが単に自分のみの問題ではなくなっている状態の時、すべては穏やかに一つと考えたらどうだろう」
という表現があります。

そう、ヒトは偉そうに、地球を支配しているかのように考えているけど
たとえばぬか漬けを食べたら、その食べ物や微生物が私の体の一部となって
行動や思考に影響し合っている。
それらの総合的な意思によって次の命に向かって行動してるんじゃないか?
そしてその流れに、そう簡単に抗うことはできない。

そういえば、ウイルスが感染して風邪をひいたとき、
くしゃみをするのはウイルスが次の体に向かおうとするから、
という説を聞いたことがあるなあ。

それに、家族とか、同じ食べ物を食べたら体質が似るってこともよくあるし。
それが、食べた多くの「命」の総合的な意思だというふうに考えると、
すごい、と思う。
梨木香歩 一段と恐るべし。
村田エフェンディ滞土録
家守綺譚
梨木果歩作品覚書



















 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック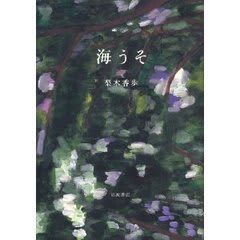









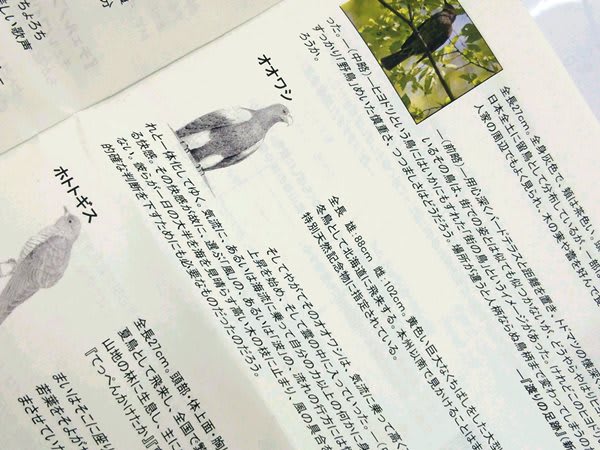


 (梨木さんのヒヨドリの表現はさんざん過ぎて面白かった)
(梨木さんのヒヨドリの表現はさんざん過ぎて面白かった)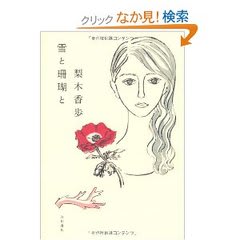

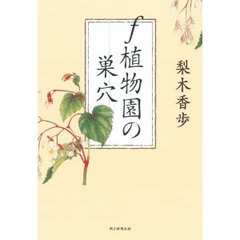
 weblio辞書より「犬雁足」
weblio辞書より「犬雁足」 weblio辞書より「月下香」
weblio辞書より「月下香」 weblio辞書より「ムジナモ」貉のシッポみたいな食虫植物
weblio辞書より「ムジナモ」貉のシッポみたいな食虫植物
 久美は事態をとても冷静に的確に判断できる女性です。
久美は事態をとても冷静に的確に判断できる女性です。 と納得してしまいます。
と納得してしまいます。 そう、ヒトは偉そうに、地球を支配しているかのように考えているけど
そう、ヒトは偉そうに、地球を支配しているかのように考えているけど