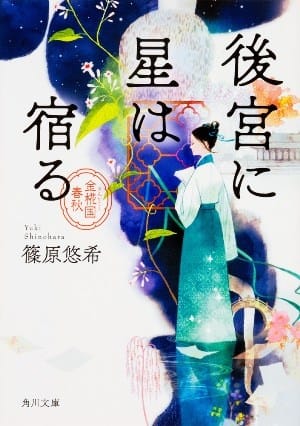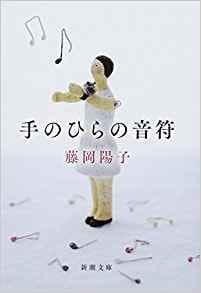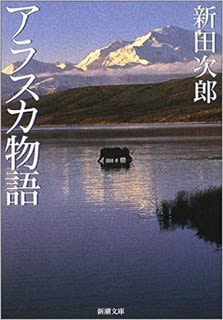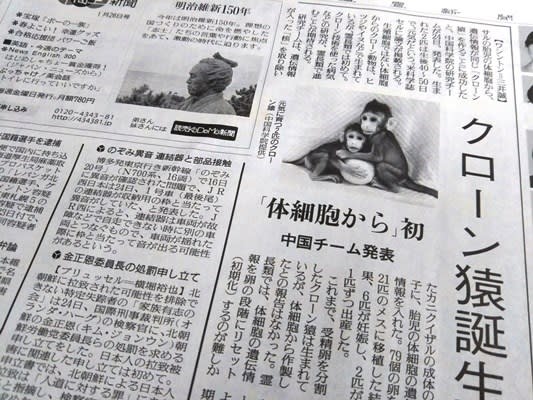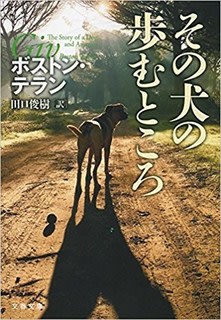金椛国春秋シリーズ第二話
逃亡の身である遊圭は女官に扮装してとうとう皇太后の娘、麗華の体調管理役となる。
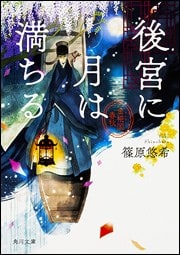
麗華は母皇太后の愛情を受けられず卑下して引きこもりとなり過食に走り、
そのためPMSや生理痛がひどい。
医師試験に合格して経験の浅いしかも男である遊圭が、
血の道症に戸惑いながらも薬膳や漢方対策をする姿が面白い
「油で揚げた甘い菓子を食べすぎてはいけない」
と、物語の中でなんども諫言する
麗華付の女官たちも皆、菓子の食べ過ぎで吹き出物など肌荒れがひどいのだ
遊圭を手助けする明々(ミンミン)が疲労がたまっているところへ、果物をつぶして化粧パックする
遊圭に、初めて使うものは腕の内側で試さないと、と言われるが、案の定、顔が真っ赤に腫れあがる
スリル満点の状況の中、こんな漢方の知恵話が面白い
⇒金椛国春秋シリーズ第一話・後宮に月は宿る
 漢方家ファインエンドー薬局HP
漢方家ファインエンドー薬局HP
http://kampo.no.coocan.jp/
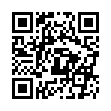 生理・不妊症・更年期・婦人科疾患のための漢方薬
生理・不妊症・更年期・婦人科疾患のための漢方薬
http://kampo.no.coocan.jp/seiri.html
 全国実力薬局100選子宝部門
全国実力薬局100選子宝部門
 漢方美肌づくり
漢方美肌づくり
http://kampo.no.coocan.jp/beauty.html
 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく
逃亡の身である遊圭は女官に扮装してとうとう皇太后の娘、麗華の体調管理役となる。
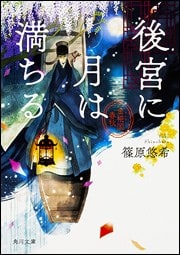
麗華は母皇太后の愛情を受けられず卑下して引きこもりとなり過食に走り、
そのためPMSや生理痛がひどい。
医師試験に合格して経験の浅いしかも男である遊圭が、
血の道症に戸惑いながらも薬膳や漢方対策をする姿が面白い
「油で揚げた甘い菓子を食べすぎてはいけない」
と、物語の中でなんども諫言する
麗華付の女官たちも皆、菓子の食べ過ぎで吹き出物など肌荒れがひどいのだ
遊圭を手助けする明々(ミンミン)が疲労がたまっているところへ、果物をつぶして化粧パックする
遊圭に、初めて使うものは腕の内側で試さないと、と言われるが、案の定、顔が真っ赤に腫れあがる
スリル満点の状況の中、こんな漢方の知恵話が面白い
⇒金椛国春秋シリーズ第一話・後宮に月は宿る
 漢方家ファインエンドー薬局HP
漢方家ファインエンドー薬局HPhttp://kampo.no.coocan.jp/
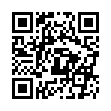 生理・不妊症・更年期・婦人科疾患のための漢方薬
生理・不妊症・更年期・婦人科疾患のための漢方薬http://kampo.no.coocan.jp/seiri.html
 全国実力薬局100選子宝部門
全国実力薬局100選子宝部門 漢方美肌づくり
漢方美肌づくりhttp://kampo.no.coocan.jp/beauty.html
 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック いいね!クリックどうぞよろしく