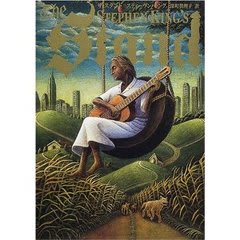
『ザ・スタンド(上・下)』 スティーヴン・キング ☆☆☆★
再読。長い。とにかく長い。
これは人によってはキングの最高傑作とも言う超大作で、書かれたのは『シャイニング』『デッド・ゾーン』の頃。飛ぶ鳥を落とす勢いでベストセラーを連発していた時期で、その勢いみたいなものは確かに伝わってくる。話のスケールもでかく、登場人物も多く、とにかく細かく書き込むというキングの力技が行き着くところまで行った感じだ。読んでも読んでも終わらない。最初に出版された時は長すぎるというのであちこちカットされたらしいが、後に完全版が出た。その完全版がつまりこれである。そういうわけでキング・ファンの思い入れが強くなりがちな作品であるらしく、キングもこれがファンの間で一番人気のようだと書いている(ちなみにキング自身の自己ベストは『デッド・ゾーン』)。私的には力作であることは認めるが、傑作とは言えないと思う。
テーマは「滅亡後の世界」である。『ザ・ロード』のところで書いたが古典的なSFのテーマであり、同じテーマで数多くの作品が存在する。本書もその一つということになる。田舎町をまるごと崩壊させるのはキングの得意技だが、この作品ではとうとう世界全部を崩壊させてしまった。そういう意味では確かにキングの集大成かも知れない。全体は大きく三部に分かれていて、最初はスーパー・フルが蔓延して世界が滅ぶ過程=主要登場人物たちがバラバラに動き回る部分、二つ目が生き残った人々が集結してあらたなコミュニティ=フリーゾーンを建設していく過程、そして三つ目が邪悪な男との戦い、である。
そう、本書で世界を滅ぼすのはインフルエンザなのである。自然発生したものではなく、アメリカの軍が細菌兵器として開発した感染率、致死率ともに97%だか99%だかという恐ろしいシロモノだ。これが漏れてすべてがアジャパーとなってしまう。最初は軍の施設から逃げ出した一人とその家族、それが車で小さな町に辿り着いて死に、バーにたむろしていた連中へと感染し、それが警官へ感染し、警官がパトロールした先の人々へ感染し、とだんだん広がっていく。この過程を例によって微に入り細をうがつ文体で、しつこくしつこく描いていく。私はこの部分が一番面白かった。
後に集結するキャラクター達はまだあちこちに散らばって自分たちの生活を持っているわけだが、妊娠した若い娘とかブレークしたばかりのロック・シンガーとか工場労働者とか旅をする聾唖の青年とか、彼らがそれぞれに生きている人生のドラマも多彩で面白く、それがスーパー・フルの蔓延という黙示録的なイベントに呑み込まれ押し流されていくさまは圧巻である。
そして生き残った人々は、なぜかギターを弾く黒人の老婆と黒マントを来た邪悪な男を夢に見るようになり、そのどちらかに集結して、滅亡後の世界に善と悪二つの集団が形成される。ここらへんからファンタジー的になってくる。私の嫌いな「邪悪な存在」が出てくる。
もちろん、これまで登場した主要人物たちは(悪役を除き)善の側であるフリーゾーンに集結する。そして邪悪な男フラッグが西の方に形成しつつある悪の集団がだんだん大きくなるのを神秘的な力で感知し、(まだ攻められたわけでもないのに)彼らとの対決を決意する。しかしキングの世界ではなぜこのように、先験的に悪と善が明快に区別されているのか。自分は善の側であり、敵が悪であるというこの絶対的な確信はどこから来るのか。やはりこれがアメリカ人のメンタリティなのか。イラク戦争の時に、テレビの街頭インタビューでお題目のように「自由と民主主義のために」と言って爆撃を支持した大勢のアメリカ人たち。「だってフセインはバッド・ガイじゃない、どうしてやっつけちゃいけないの?」などと脳天気に言い放った女もいて、胸糞悪くなったものだが、それと似たような違和感を感じる。
要するに、アメリカ人にとって正義とは自分たちのことなのである。自分たちが望むことがすなわち正義。従って敵対者は自動的に悪と断定される。私を含め大部分の日本人は、多分こういう思考にはついていけないだろう。なんせ私ら、子供の頃に観た『ウルトラセブン』なんてヒーロー番組の中でさえ、「実は我々こそが侵略者ではないのか、我々こそが悪なのではないか」という懐疑主義を植えつけられてますから(『ノンマルトの使者』『ダーク・ゾーン』など)。
やがて主人公たちは西へ旅してフラッグの帝国へ到着し、捕まって処刑されようとした時にとんでもないハプニングが起きて事態に決着がつく。ネタバレになるので書かないが、はっきりいって全然盛り上がらない、ご都合主義丸出しのクライマックスだ。処刑会場でフラッグ帝国の連中が「おれたちは間違ってた!」なんて言い出すのも興ざめだし、フラッグの言動はまるでショッカーの首領みたいだ。さすがのキングもついに息切れしたか?
つまらないクライマックスのあとで、主要人物のうちのふたりが一緒にフリーゾーンへ戻るエピローグ的な旅が長々と描写されるが、こっちの方がまだ生彩がある。その後の帰還場面は結構感動的で、長い旅を経て帰還したという感慨がある。そしてその感慨はそのまま本書の読後感へと繋がる。これだけ長いと、なんだか読み終えただけである種の感動を覚えてしまうなあ。
本書には色んなキャラクターが登場するが、印象的だったのはハロルドである。悪役には違いないのだが、善か悪かにはっきり分かれるキャラが多いキングにしては珍しい、複雑なキャラだ。オタクっぽく子供じみたキャラとして登場し、途中から嫉妬に狂いアブナイ奴になるが、同時に一貫して有能な人物として描かれる。そして時折、ひょっとして改心してイイ奴になるのでは、と思わせる瞬間がある。途中で死んでしまうのが惜しいキャラだった。
とりあえず『『呪われた町』『シャイニング』『デッド・ゾーン』『ファイアスターター』『ペット・セメタリー』あたりの傑作長編を一通り読み、キング中毒になり、「おれはもっと長いのもいけるぞ!」という人はチャレンジしてはいかがだろうか。
再読。長い。とにかく長い。
これは人によってはキングの最高傑作とも言う超大作で、書かれたのは『シャイニング』『デッド・ゾーン』の頃。飛ぶ鳥を落とす勢いでベストセラーを連発していた時期で、その勢いみたいなものは確かに伝わってくる。話のスケールもでかく、登場人物も多く、とにかく細かく書き込むというキングの力技が行き着くところまで行った感じだ。読んでも読んでも終わらない。最初に出版された時は長すぎるというのであちこちカットされたらしいが、後に完全版が出た。その完全版がつまりこれである。そういうわけでキング・ファンの思い入れが強くなりがちな作品であるらしく、キングもこれがファンの間で一番人気のようだと書いている(ちなみにキング自身の自己ベストは『デッド・ゾーン』)。私的には力作であることは認めるが、傑作とは言えないと思う。
テーマは「滅亡後の世界」である。『ザ・ロード』のところで書いたが古典的なSFのテーマであり、同じテーマで数多くの作品が存在する。本書もその一つということになる。田舎町をまるごと崩壊させるのはキングの得意技だが、この作品ではとうとう世界全部を崩壊させてしまった。そういう意味では確かにキングの集大成かも知れない。全体は大きく三部に分かれていて、最初はスーパー・フルが蔓延して世界が滅ぶ過程=主要登場人物たちがバラバラに動き回る部分、二つ目が生き残った人々が集結してあらたなコミュニティ=フリーゾーンを建設していく過程、そして三つ目が邪悪な男との戦い、である。
そう、本書で世界を滅ぼすのはインフルエンザなのである。自然発生したものではなく、アメリカの軍が細菌兵器として開発した感染率、致死率ともに97%だか99%だかという恐ろしいシロモノだ。これが漏れてすべてがアジャパーとなってしまう。最初は軍の施設から逃げ出した一人とその家族、それが車で小さな町に辿り着いて死に、バーにたむろしていた連中へと感染し、それが警官へ感染し、警官がパトロールした先の人々へ感染し、とだんだん広がっていく。この過程を例によって微に入り細をうがつ文体で、しつこくしつこく描いていく。私はこの部分が一番面白かった。
後に集結するキャラクター達はまだあちこちに散らばって自分たちの生活を持っているわけだが、妊娠した若い娘とかブレークしたばかりのロック・シンガーとか工場労働者とか旅をする聾唖の青年とか、彼らがそれぞれに生きている人生のドラマも多彩で面白く、それがスーパー・フルの蔓延という黙示録的なイベントに呑み込まれ押し流されていくさまは圧巻である。
そして生き残った人々は、なぜかギターを弾く黒人の老婆と黒マントを来た邪悪な男を夢に見るようになり、そのどちらかに集結して、滅亡後の世界に善と悪二つの集団が形成される。ここらへんからファンタジー的になってくる。私の嫌いな「邪悪な存在」が出てくる。
もちろん、これまで登場した主要人物たちは(悪役を除き)善の側であるフリーゾーンに集結する。そして邪悪な男フラッグが西の方に形成しつつある悪の集団がだんだん大きくなるのを神秘的な力で感知し、(まだ攻められたわけでもないのに)彼らとの対決を決意する。しかしキングの世界ではなぜこのように、先験的に悪と善が明快に区別されているのか。自分は善の側であり、敵が悪であるというこの絶対的な確信はどこから来るのか。やはりこれがアメリカ人のメンタリティなのか。イラク戦争の時に、テレビの街頭インタビューでお題目のように「自由と民主主義のために」と言って爆撃を支持した大勢のアメリカ人たち。「だってフセインはバッド・ガイじゃない、どうしてやっつけちゃいけないの?」などと脳天気に言い放った女もいて、胸糞悪くなったものだが、それと似たような違和感を感じる。
要するに、アメリカ人にとって正義とは自分たちのことなのである。自分たちが望むことがすなわち正義。従って敵対者は自動的に悪と断定される。私を含め大部分の日本人は、多分こういう思考にはついていけないだろう。なんせ私ら、子供の頃に観た『ウルトラセブン』なんてヒーロー番組の中でさえ、「実は我々こそが侵略者ではないのか、我々こそが悪なのではないか」という懐疑主義を植えつけられてますから(『ノンマルトの使者』『ダーク・ゾーン』など)。
やがて主人公たちは西へ旅してフラッグの帝国へ到着し、捕まって処刑されようとした時にとんでもないハプニングが起きて事態に決着がつく。ネタバレになるので書かないが、はっきりいって全然盛り上がらない、ご都合主義丸出しのクライマックスだ。処刑会場でフラッグ帝国の連中が「おれたちは間違ってた!」なんて言い出すのも興ざめだし、フラッグの言動はまるでショッカーの首領みたいだ。さすがのキングもついに息切れしたか?
つまらないクライマックスのあとで、主要人物のうちのふたりが一緒にフリーゾーンへ戻るエピローグ的な旅が長々と描写されるが、こっちの方がまだ生彩がある。その後の帰還場面は結構感動的で、長い旅を経て帰還したという感慨がある。そしてその感慨はそのまま本書の読後感へと繋がる。これだけ長いと、なんだか読み終えただけである種の感動を覚えてしまうなあ。
本書には色んなキャラクターが登場するが、印象的だったのはハロルドである。悪役には違いないのだが、善か悪かにはっきり分かれるキャラが多いキングにしては珍しい、複雑なキャラだ。オタクっぽく子供じみたキャラとして登場し、途中から嫉妬に狂いアブナイ奴になるが、同時に一貫して有能な人物として描かれる。そして時折、ひょっとして改心してイイ奴になるのでは、と思わせる瞬間がある。途中で死んでしまうのが惜しいキャラだった。
とりあえず『『呪われた町』『シャイニング』『デッド・ゾーン』『ファイアスターター』『ペット・セメタリー』あたりの傑作長編を一通り読み、キング中毒になり、「おれはもっと長いのもいけるぞ!」という人はチャレンジしてはいかがだろうか。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます