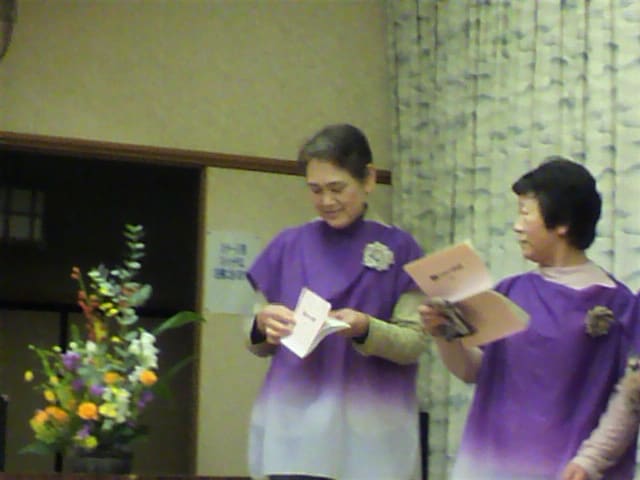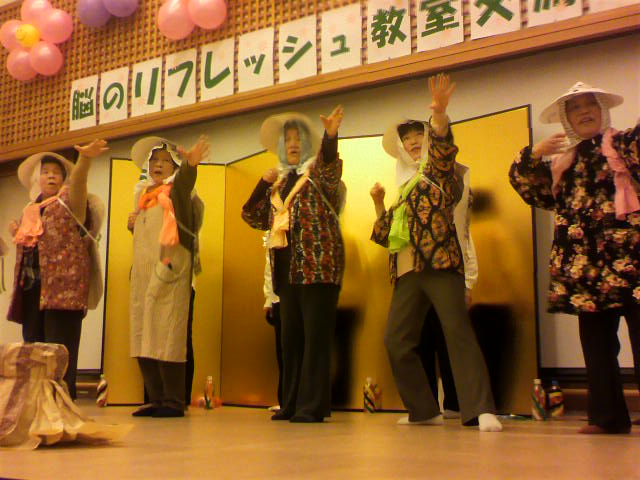平泉町の「脳いきいき発表会」に行ってきました。
旧観自在王院庭園となりにあるホテル武蔵坊が会場でした。
当日朝になってみると、大雨強風注意報が出ているという状態で
「一応180人くらいはいらっしゃると思うのですが・・・」
「今朝になって、参加したいという電話が入ったりもしていますけど・・・」
と、心配そうな雰囲気が漂っていました。
蓋を開けたら、200席用意した椅子が足りなくなって、ホテル手持ちの椅子を全部出してもらって、さらに足りない。
あわてて保健センターに取りに行き、結局のところ
「270人までは数えましたから、それ以上来て下さったのは確実です」と、保健センターの皆さんはとてもうれしそうでした。
実は2008年にも「脳いきいき発表会」が開催されていたのです。クリックしてくださるとその時の様子がわかりますが、今回はさらにバージョンアップ!
楽しくて、大笑いしながら私はこみあげてくるものを噛みしめていました。
よくもここまで。
教室ごとに工夫がきらりと光ってます。
衣装が洗練されたこと!徹底的に衣装で楽しむ教室もありました。
小道具にまで心配りが利いていました。
どの教室も個性を出そうしています。
4区脳いきいき教室(歌)楽譜が素敵
皆さん、ステージ上ではほとんどがまじめな顔をしていましたが、300人を前にすれば緊張するのも当然でしょう。
終わって席に戻られるときの緊張感がとけた満足そうなお顔が対照的でした。
それから会場からの楽しい掛け合いや
励ましの手拍子も、印象的でした。
菅原町長さんも交流会終了後に、
「これはなかなかすごいですね。こんなに元気にやってくださってるとは!」と喜ばれていましたが、導入したH積保健師さんから今の担当のM山保健師さん。皆さんの生活指導、脳の健康教育、努力のたまものです。
ただ歌って踊ってるだけではないのですから。
あくまでも脳の健康を維持し、ボケないためにというはっきりとした目標を持っているところが、普通のお楽しみ会と違うところです。(そのためには脳機能テストを実施しなくてはいけませんが、人員的にそろそろいっぱいのようにも聞きました)
数年前の一番最初の発表会の時、皆さんが戸惑って楽しんでいいのかどうかわからないという風情だったことを、私は知っていますから、「平泉の皆さんの生き方が変わったのかもしれない!」と感動したのです。
「今日の皆さんのように、楽しめる人が勝ち。楽しめる人がボケないのです」とつい講演の冒頭で強調してしまいました。
10区脳いきいき教室(風呂敷踊り) 椅子での参加もいいですね。この迫力!
椅子での参加もいいですね。この迫力!
エイジングライフ研究所は、生き方、つまり脳の使い方がボケるかボケないかを決めると主張しています。
認知症のうちもっとも多くを占めるアルツハイマー型認知症の予防は、可能です。
高齢になって、生活上の変化や大きな出来事をきっかけにして何もしない生活を続けるうちに次第にトラブルを起こしてきて、最終的には徘徊や不潔行為や見当識障害などいわゆる世間で言われる「ボケてしまった」状態に至るのが、アルツハイマー型認知症ですから、過去に遡ればさかのぼるほど必ず正常な社会人であった所に行きつきます。
その正常であった時に近いところほど、改善が可能であるといっているのです。サボらせた脳を右脳を使ったり運動をしたりして活性化するのですね。
14区楽友会(踊り)帽子は編まれたんでしょうね。カラフルでかわいい。
さらにいえば、元気な高齢者を正常のままに保つことを目的にした予防こそが、住民のみなさんが望み、経済的にも効率がいいことは自明のことでしょう。
今回は聴衆の皆さんがとてもよく話を聞いてくださったので、経済的な話もかなりしました。
「一関地区広域行政組合で介護保険の給付金はいくらでしょう?」
まさか100億円も使われていると思っていた方はいなかったようでした。
「平泉町は?」
それでも6.2憶円!
正常の方々への予防活動の費用は、平泉町では年間700万円足らず。
この金額をどのように考えるか?
ボケが予防できるとしたら、実に効果的なお金の使い方ですよね。
(ボケ予防に関して主観的にはスタッフの皆さんや教室参加者は納得しているでしょうが、客観的に主張するなら、脳機能テストという物差しが必要でしょうね。そのためや教室運営には、ボケ予防に特化したスタッフが必要なのかもわかりません。その際に必要な人件費をどのように考えるか?出ずるを制するための必要な経費という考え方は無理でしょうか)
私の住んでいる伊東市での話もしました。
平成16年に高齢者と児童に使われたお金は112億/39億
平成20年に高齢者と児童に使われたお金は132億/34億
12区さわやかクラブ(体操)
 ダンベルまでマッチさせてシックの一言。
ダンベルまでマッチさせてシックの一言。
「高齢者の皆さんの努力や尊厳は十分に納得しているけれども、この高齢者と児童に対する費用比はおかしい。伊東市の場合は平成16年はそれでも児童費用が1/3あったのに、20年には1/4になってしまってます」こういう強い言い方にも、会場は納得のムードで答えてくださいました。
19区脳いきいき教室(踊り)法被とうちわをコーディネート
実は、交流会前に、菅原町長さんとお話をしました。
「福祉をどう考えるかはその町の存続がかかるほど大切な分野だと思います。
福祉を求める人たちは、身体障害の方々、精神障害の方々、知的障害の方々、そして認知症の人たちですが、前の三つの方々は、予防というより生まれつきであったり、病気やけがで避けえないものとしてその障害とともに生きるのですから、手厚い福祉を要求されても当然でしょう。
でもボケだけは違います。手厚い福祉が必要になるまでには、3年から8年もの期間があるのです。早い方が効率的。経済的。つまり認知症は予防的な福祉の対象となりえます。さらに言えば、正常者へのボケ予防こそが、住民からは最も求められているものだと思います」
戸河内お楽しみ会(踊り)
M山保健師さんに「全部用意してあるから一緒に踊ってね」
M山さんは「全部みなさんがやってくれたんです!」と大感激。男性も参加してます。すごいスリットでした。百均で使えるものはないか、いつもチェック。

菅原町長さんは開会のあいさつの中で
「健康は自分で守らなければなりません。しかもそれは自分だけでなく、家族ひいては地域の健康までも守ることが大切です」と明言され、私は心中大拍手。講演にも120点の考え方と引用させていただきました。
19区ニコニコクラブ(歌)指揮者は「地区の美容院の息子が結婚式に着たタキシード」でかっこよく決めたうえで役者ぶりを発揮し会場大笑い。ご祝儀まで!手作り楽譜のニコニコマークと紅葉にも注目(曲は紅葉の輪唱)

 千葉ミズさんからのプレゼント
千葉ミズさんからのプレゼント
ボケの予防には
①一人一人に「脳の健康を守る」という考え方を教える
②脳の健康相談の窓口を開く
③正常者を中心にした認知症予防教室を開催する
何を行政がやり、何を住民がやるかということをはっきりさせて、ボケのない町を実現させて下さい。
「栄華を誇った藤原三代の頃、平泉はある意味で日本の先進地であったのですね。ボケ予防でもモデルになれるように頑張ってください」と講演を締めくくったのでした。
 エイジングライフ研究所は、
エイジングライフ研究所は、 保健師さんの存在を知った時に
保健師さんの存在を知った時に