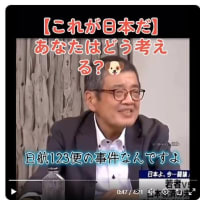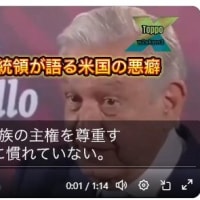事件発生から64年も経過した1996年、平頂山事件訴訟が中国人戦後補償問題の一つとして東京地方裁判所に提訴された。「平頂山事件とはなんだったのか──裁判が紡いだ日本と中国の市民のきずな」平頂山事件訴訟弁護団(高文研)には、弁護団の結成から提訴に至までの経緯やその後の裁判の取り組みが詳しく綴られている。
平頂山事件訴訟に対する東京地裁や東京高裁の「国家無答責」の判決および最高裁の上告棄却の決定は、日本のあらゆる戦後補償問題に対する姿勢を象徴するものではないかと思う。
敗戦後の日本は、表面上の民主化とは裏腹に、アメリカとの取り引きによって、様々なかたちで戦前の体制を温存させた。アメリカも事実上「国体護持」を認め、天皇の戦争責任を免責することによって、戦争責任の追求を曖昧にしただけではなく、米ソ対立の激化に合わせて、日本の再軍備を急ぎ旧軍関係者を甦らせた。ポツダム宣言で永久に公職追放されたはずの旧軍将校が、再軍備が進むと追放を解除され、自衛隊に入隊したり、国会議員となったりして活動を再開したのである。
旧日本軍細菌戦部隊(731部隊)関係者などは、その極秘情報のアメリカ軍への提供によって免責され、全く訴追されることなく、戦後も要職に復帰し、アメリカ占領軍に従属しながら、旧支配体制温存の一翼を担った。すなわち、敗戦後の日本は、天皇や皇族、旧軍関係者、旧中央官僚などが、アメリカ占領軍に従属するかたちで、その支配力を相当程度維持したと考えてよい。
日本が、戦争責任の追及を有耶無耶にし、戦後補償の問題にきちんと取り組まないのは、そうした旧支配層が今も変わらず力を持ち続けているからではないかと思うのである。残念ながら、平頂山事件の一審・二審の判決や最高裁の決定は、裁判所も決して旧支配層と無縁ではないことを示したものといえるのではないかと思いつつ、同書から抜粋した。
---------------------------------
第3章 手探りで始まった裁判──「国家無答責」の壁に挑む
一審判決「国家無答責」で敗訴──2002年6月28日
判決の勝利を信じて、原告を代表し楊宝山さんが来日した。2006年6月28日に出された東京地方裁判所民事第10部(裁判長菊地洋一)判決は、弁護団が提出した証拠に基づき、「この(撫順炭鉱)攻撃事件の直後、日本側守備隊は、中国側自衛軍の進軍経路上にあった平頂山村の住民が自衛軍と通じていたとして、同村の住民を掃討することを決定し、同日朝、独立守備隊第2大隊第2中隊等の部隊が平頂山村に侵入した。旧日本兵らは、同村住民のほぼ全員を同村南西側の崖下に集めて包囲し、周囲から機関銃などで一斉に銃撃して殺傷した後、生存者を銃剣で刺突するなどして、その大半を殺害し、同時に村の住家に放火して焼き払った」などとして、1932年9月16日の平頂山事件の日本軍による住民虐殺の事実をほぼ、原告の主張どおりの内容で認めた。
しかし、原告らの求めていた損害賠償請求については、国家賠償法が制定施行される以前におけるわが国の法制度は、「権力作用に基づく損害について国又は公共団体は賠償責任を負わないとする国家無答責の法理が採用されていた」として「本件加害行為(住民虐殺行為)は、旧日本軍の中国における戦争行為・作戦活動に付随する行為であり、これらの行為はわが国の公権力の行使にあたる事実上の行為」であるから、「いわゆる国家無答責の法理により損害賠償責任を負わない」として、原告らの請求を棄却した。
判決は、国家無答責の法理とは、「(国の)損害賠償の根拠となる法律が存在しなかったから、損害賠償責任を負わない」とする法理であると判示した。しかし、戦前においても民法の不法行為の規定は存在しており、国の権力行為について、なぜ民法が適用されないのかについては、判決は直接的に理由を述べなかった。
・・・(以下略)
--------------------------------
第4章 信頼と和解──裁判が結びつけた人びとの絆
二審判決「国家無答責」で敗訴──2005年5月13日
事件から73年、最後の望みを裁判に託した原告たちの痛切な願いと、これを支援した日中の人びとの期待は、2005年5月13日、東京高等裁判所第10民事部の下した判決により、木っ端微塵に打ち砕かれた。またしても敗訴。またしても国家無答責の法理であった。
判決は、「当該行為(本件の日本軍による平頂山住民虐殺行為)は、旧日本軍の戦争行為、作戦活動として行われたものであることは否定しがたい」「軍事力の行使は、国家の権力作用の最たるものであり」、それゆえ「責任の有無の判断は、国家主権の正当性の存否にもかかわる」から、「市民社会に共通して適用される私法の規律にかからしめることができないことは明らか」と断じた。
これは「軍隊の行為についてはその当否を問えない」とする戦前の明治憲法体制下の司法判断となんら変わらない考え方であった。個人の人権を最高価値とする現行憲法は、人権の最後の守り手としての裁判所の任務を定めている。東京高等裁判所の判決は、憲法の規定する司法の任務を放棄することを高々と宣言したに等しく、まさに司法の自殺行為といえる判決であった。
・・・(以下略)
--------------------------------
第4章 信頼と和解──裁判が結びつけた人びとの絆
最高裁上告棄却──2006年5月16日
2006年5月16日、最高裁判所第三小法廷(上田豊三裁判長)は、平頂山事件で日本軍に肉親を虐殺された楊さん、方さん、故莫さんら原告の、日本政府に対する損害賠償請求につき、原告らの上告を棄却し、上告審として受理しないとの決定を行った。
平頂山事件弁護団は、全体弁護団と協力し、「国家無答責の法理」の適用を否定した戦後補償裁判の判決の到達点と、行政法、民法などの学者による最新の研究成果に基づき、詳細かつ最先端の理論を展開して不当な高裁判決を覆すべく争った。しかし、最高裁は、上告理由書等の提出からわずか4ヶ月足らずで、まともな審理も行わず、何らの根拠を示すことなく、上告を棄却し、上告を受理しないとの三行半の決定を下した。
・・・(以下略)
http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/ に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に換えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。
平頂山事件訴訟に対する東京地裁や東京高裁の「国家無答責」の判決および最高裁の上告棄却の決定は、日本のあらゆる戦後補償問題に対する姿勢を象徴するものではないかと思う。
敗戦後の日本は、表面上の民主化とは裏腹に、アメリカとの取り引きによって、様々なかたちで戦前の体制を温存させた。アメリカも事実上「国体護持」を認め、天皇の戦争責任を免責することによって、戦争責任の追求を曖昧にしただけではなく、米ソ対立の激化に合わせて、日本の再軍備を急ぎ旧軍関係者を甦らせた。ポツダム宣言で永久に公職追放されたはずの旧軍将校が、再軍備が進むと追放を解除され、自衛隊に入隊したり、国会議員となったりして活動を再開したのである。
旧日本軍細菌戦部隊(731部隊)関係者などは、その極秘情報のアメリカ軍への提供によって免責され、全く訴追されることなく、戦後も要職に復帰し、アメリカ占領軍に従属しながら、旧支配体制温存の一翼を担った。すなわち、敗戦後の日本は、天皇や皇族、旧軍関係者、旧中央官僚などが、アメリカ占領軍に従属するかたちで、その支配力を相当程度維持したと考えてよい。
日本が、戦争責任の追及を有耶無耶にし、戦後補償の問題にきちんと取り組まないのは、そうした旧支配層が今も変わらず力を持ち続けているからではないかと思うのである。残念ながら、平頂山事件の一審・二審の判決や最高裁の決定は、裁判所も決して旧支配層と無縁ではないことを示したものといえるのではないかと思いつつ、同書から抜粋した。
---------------------------------
第3章 手探りで始まった裁判──「国家無答責」の壁に挑む
一審判決「国家無答責」で敗訴──2002年6月28日
判決の勝利を信じて、原告を代表し楊宝山さんが来日した。2006年6月28日に出された東京地方裁判所民事第10部(裁判長菊地洋一)判決は、弁護団が提出した証拠に基づき、「この(撫順炭鉱)攻撃事件の直後、日本側守備隊は、中国側自衛軍の進軍経路上にあった平頂山村の住民が自衛軍と通じていたとして、同村の住民を掃討することを決定し、同日朝、独立守備隊第2大隊第2中隊等の部隊が平頂山村に侵入した。旧日本兵らは、同村住民のほぼ全員を同村南西側の崖下に集めて包囲し、周囲から機関銃などで一斉に銃撃して殺傷した後、生存者を銃剣で刺突するなどして、その大半を殺害し、同時に村の住家に放火して焼き払った」などとして、1932年9月16日の平頂山事件の日本軍による住民虐殺の事実をほぼ、原告の主張どおりの内容で認めた。
しかし、原告らの求めていた損害賠償請求については、国家賠償法が制定施行される以前におけるわが国の法制度は、「権力作用に基づく損害について国又は公共団体は賠償責任を負わないとする国家無答責の法理が採用されていた」として「本件加害行為(住民虐殺行為)は、旧日本軍の中国における戦争行為・作戦活動に付随する行為であり、これらの行為はわが国の公権力の行使にあたる事実上の行為」であるから、「いわゆる国家無答責の法理により損害賠償責任を負わない」として、原告らの請求を棄却した。
判決は、国家無答責の法理とは、「(国の)損害賠償の根拠となる法律が存在しなかったから、損害賠償責任を負わない」とする法理であると判示した。しかし、戦前においても民法の不法行為の規定は存在しており、国の権力行為について、なぜ民法が適用されないのかについては、判決は直接的に理由を述べなかった。
・・・(以下略)
--------------------------------
第4章 信頼と和解──裁判が結びつけた人びとの絆
二審判決「国家無答責」で敗訴──2005年5月13日
事件から73年、最後の望みを裁判に託した原告たちの痛切な願いと、これを支援した日中の人びとの期待は、2005年5月13日、東京高等裁判所第10民事部の下した判決により、木っ端微塵に打ち砕かれた。またしても敗訴。またしても国家無答責の法理であった。
判決は、「当該行為(本件の日本軍による平頂山住民虐殺行為)は、旧日本軍の戦争行為、作戦活動として行われたものであることは否定しがたい」「軍事力の行使は、国家の権力作用の最たるものであり」、それゆえ「責任の有無の判断は、国家主権の正当性の存否にもかかわる」から、「市民社会に共通して適用される私法の規律にかからしめることができないことは明らか」と断じた。
これは「軍隊の行為についてはその当否を問えない」とする戦前の明治憲法体制下の司法判断となんら変わらない考え方であった。個人の人権を最高価値とする現行憲法は、人権の最後の守り手としての裁判所の任務を定めている。東京高等裁判所の判決は、憲法の規定する司法の任務を放棄することを高々と宣言したに等しく、まさに司法の自殺行為といえる判決であった。
・・・(以下略)
--------------------------------
第4章 信頼と和解──裁判が結びつけた人びとの絆
最高裁上告棄却──2006年5月16日
2006年5月16日、最高裁判所第三小法廷(上田豊三裁判長)は、平頂山事件で日本軍に肉親を虐殺された楊さん、方さん、故莫さんら原告の、日本政府に対する損害賠償請求につき、原告らの上告を棄却し、上告審として受理しないとの決定を行った。
平頂山事件弁護団は、全体弁護団と協力し、「国家無答責の法理」の適用を否定した戦後補償裁判の判決の到達点と、行政法、民法などの学者による最新の研究成果に基づき、詳細かつ最先端の理論を展開して不当な高裁判決を覆すべく争った。しかし、最高裁は、上告理由書等の提出からわずか4ヶ月足らずで、まともな審理も行わず、何らの根拠を示すことなく、上告を棄却し、上告を受理しないとの三行半の決定を下した。
・・・(以下略)
http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/ に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に換えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。