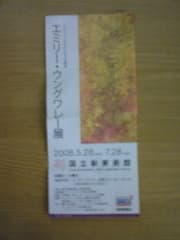今朝、NHKの日曜美術館で英一蝶(はなぶさ いっちょう)という元禄期の絵師をとリ上げていました。
私は浅学にも、この絵師の存在を今日まで知りませんでした。
吉原通いを毎晩続け、幇間として旦那衆のご機嫌をうかがいながら、画材を取材していた、とのことです。
その作風は諧謔にして豪華。遊び人の片鱗がうかがえます。若冲などの糞真面目な画風と違い、遊び心に満ちています。
47歳にして生類憐れみの令を笑い飛ばす絵を描き、三宅島に流されますが、11年後、ご赦免舟で江戸に帰還。74歳でその生涯を閉じるまで、精力的に画業と句作に徹します。
肖像を見ると鬼のような恐ろしい顔ですが、絵は、優れて洒落ていました。
現在板橋区立美術館で展覧会を開催しているとのこと、ぜひ出かけてみようと思います。
英一蝶
昨日はNHKで能公演「三井寺」を観ました。
「三井寺」はわが子をさらわれ、狂った女が、清水寺でわが子の無事を祈ったところ、近江の三井寺に行くように、とのお告げがあり、三井寺に行く話です。
三井寺に着くと、月見の最中で多くの坊主が並んでいるなかに、一人、幼子が混じっています。狂女と幼子が互いに名乗りあい、親子だと知って、抱き合い、終わります。
狂女の話としては、春の「隅田川」と並ぶ、秋の名作です。
遠近法なのか、わざとちいさくしつらわれた三井寺の名鐘が、秋を連想させます。
狂女が三井寺に着き、坊主どもが騒ぎ出してから、鐘をつき、わが子を抱くまでが、一気に魅せて、圧倒的迫力をもって迫ってきます。
それにしても、能の衣装は美しいですね。
演劇のファッションとしては、世界一です。
堪能しました。
先日、新装なった東京都現代美術館に行ってきました。
リニューアルして、大幅に企画展示のコーナーを増やし、常設展示を減らしていました。現代美術というのは、見る者を挑発するようなところがあった、圧倒されました。
先日NHKで、別府市で行われている現代アートのお祭りが紹介されていました。
別府市の民家と言わず、公園と言わず、路地までも、展示場にして、ありとあらゆる現代アートを展示しているのです。
現代アートというと、ピカソやダリに代表されるような、シュールリアリズムから出発して、独特の世界を築いた美術家たち、という印象がありましたが、今はさらに進んで、もっと自由というか勝手気ままに、創作を行っているのですね。
全身黒づくめの格好をしてただ地を這い回り、それを撮影したものや、木に本をくくりつけただけのものや。
正直言って、なんだかわかりません。
美術というくらいだから、「美」を感じさせないといけないんじゃないかな、と思います。
あれは美術というより自己顕示のパフォーマンスですね。
変わったことをすれば良い、というような風潮は戒めるべきですね。
きっと近代にいたるまで、美術という概念は希薄だったんじゃないでしょうか。
仏師にしても絵師にしても、基本は注文に応じて創作します。
ヨーロッパのキリスト教芸術も、布教や、キリスト教の素晴らしさを称揚するためのものです。
いわば、主持ち。職人に近かったのではないでしょうか。
その反動がパフォーマンス的現代アートのような気がします。
しかし、仏像や、クラシック音楽や、定型詩や、能のように、約束事に縛られながら、その範疇で高い芸術性を追求することの方が、私には魅力的に思えます。
昨日は江戸東京博物館に「手塚治虫展」を見に行きました。1,300円は高いと思いましたが、内容は充実していました。
子どもの頃、「ブラックジャック」や「三つ目がとおる」などを夢中で読んだものです。
「火の鳥」は完結を見ず、残念でしたね。
その後、両国界隈を散歩しました。
ちょうど夏場所中とあって、多くのお相撲さんが歩いていました。鬢付けの香りが良かったです。
国技館周辺は人だかりができていて、外国人が多いことにびっくりしました。
その後安田庭園でのんびりしてから帰りました。
良い休日だったと思います。
千葉市美術館に「八犬伝」展を観にいきました。
「八犬伝」は、小学生の頃、子供向けのダイジェスト版を夢中で読んだ記憶があります。今で言えば、山田風太郎の伝奇小説のような感じでしょうか。
その後、中学生になって、芥川龍之介の「戯作三昧」を読みました。これは滝沢馬琴が「八犬伝」を執筆しながら、三昧境に陥るさまを描いた、芸術至上主義の作品と読みました。
今日観た展示は、錦絵あり、和綴本あり、歌舞伎あり、映画あり、人形ありの、賑やかなものでした。
それにしても、晩年、馬琴は視力を失い、妻に口述筆記させて、29年もの歳月をかけてこの大長編を完成させたことは知りませんでした。
その執念には、恐怖すら感じます。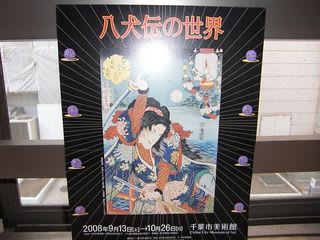
千葉市美術館に、「ブラスティスラヴァ世界絵本原画展」を観に行きました。
絵本の原画ということで、素朴な絵が多いのかなと思っていたら、案外グロテスクな絵も多くありました。元来、絵本というのはグロテスクなものかもしれません。
よい気分転換になりました。ドグマチールが増えて、少し元気になってきたようです。
インターネットで購入した、やなぎみわの写真文集「老少女綺譚」を見ました。
やなぎみわは、現在、神戸芸術工科大学先端芸術学部メディア表現学科准教授のかたわら、積極的に作品を発表している現代アートの芸術家です。
作風は、グロテスクと言っていいほど幻想的で、なんともいえない魅力があります。
昨年12月に品川の原美術館でその作品に接してから、奇妙な魅力に取り付かれています。美と醜の垣根を軽々と越えてしまう芸術は、見る者を圧倒します。
 |
Fairly Tale 老少女綺譚 |
| やなぎ みわ | |
| 青幻舎 |
 |
やなぎみわ―マイ・グランドマザーズ |
| 東京都写真美術館 | |
| 淡交社 |
東京国立博物館に、「対決 巨匠たちの日本美術」展を観に行きました。日本美術の歴史を俯瞰するには、良い展示だと思います。
しかし、平成館で行う企画展示はいつもそうですが、ひどく混んでいます。私は人ごみが弱いので、げんなりしました。
本館・東洋館はほどほどの人出でした。本館では、国宝「風信帖」が展示されていました。空海が最澄に送った書簡です。私には、それがどれほど良いものなのか、不明でした。
少し動く気になったので、新国立美術館に、「エミリー・ウングワレー展」を観に行きました。
彼女はアボリジニの抽象画家です。
抽象画にも関わらず、観る者を挑発するような点がなく、むしろ癒しの効果さえあります。
作品を発表し始めたのが80歳ちかくになってから、というせいもあるかもしれません。
亡くなるまでの8年間に、3000点もの絵画を残し、オーストラリアを代表する画家になったとのことです。
私は展示されていた120点余の絵のなかでも、「ビッグ・ヤム・ドリーミング」・「大地の創造」・「カーメ」の3点が気に入り、絵葉書を購入しました。
昨夜、NHKの新日曜美術館で、モディリアーニの特集がありました。
私はその作品から感じられる、強い退行欲求に、吐き気を催しながら、
観ることをやめられませんでした。
彼の絵は自殺願望をそそる、危険な絵です。