ヒュームの観点に関する個人的見解を示したときに触れた,スピノザがオルデンブルクHeinrich Ordenburgに宛てた書簡七十八のうち,スピノザが聖書をどのように解釈しているのかがよく分かる部分を示しておきます。
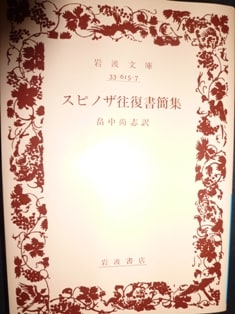
神Deusが罪人に対して怒るということ,あるいは神は人間の行動を認識し,判定し,裁きを与えるという意味のことが聖書には書いてあります。スピノザによればそれは,聖書が人間的ないい方に倣い,民衆の伝統的な見解opinioに順応するように語っているからだとされています。したがって,実際に神が怒ったり裁いたりすることはないというのがスピノザの考え方であることが分かります。ただしスピノザは,だからそのような記述についてそれを批判しているのではありません。むしろそれは聖書の目的に適合するものであるといっています。なぜなら,スピノザの考え方によれば,聖書が意図するのは哲学を教えること,いい換えれば真理veritasを教えるという点にあるのではないし,人びとを賢明にするという点にあるのでもなく,ただ人間を従順にするという点にのみあるからです。
イエスの受難と死と埋葬については,スピノザは文字通りに解するといっています。つまりそれに関しては聖書に記述されてあることを真理,実際にあった出来事として解するという意味です。ただし復活に関しては比喩的に解するといっています。つまり復活に関しては史実とは解さないという意味です。ただし福音史家,これはマタイ,ルカ,マルコ,ヨハネのことを指していると思われますが,かれらがイエスが復活したと信じたことは疑い得ないとしています。同時にかれらは,その点については間違い得た,要するに間違えたのです。とはいえこうした間違いのゆえに福音書の教説自体が損なわれるというものではないと主張している点は,やはり聖書の意図をスピノザがどのように把握しているのかということから説明することができるでしょう。
スピノザの著作としては『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』と関連した議論になっています。この時代のオルデンブルクとの書簡のやり取りは,『神学・政治論』の理解のために有益だと思います。
人間が自然権jus naturaleの一部を譲渡することによって自然権naturale jusの拡張を果たすがゆえに,自由の人homo liberはその自然権が最大限に拡大された国家Imperiumで生活することを欲望することになります。したがって,自身が自然権の一部を譲渡することで自然権が拡大されることを知らず,それがために自身の自然権だけを行使することを欲望する人は,自由の人とは反対の意味で無知の人といわれなければなりません。しかしながら,僕の考えでいえば,拡大された自然権を保守するために,共同の決定に従わない人間のことを非難するのは,同じように無知の人がすることであって,自由の人がすることではないのです。これはそうした非難が憎しみodiumの連鎖を産出してしまうからという理由もありますが,別の理由もあります。それは,すべての人間が自然権を譲渡し合って理性ratioに従うということは,理想ではあるけれどもあくまでも理想にすぎないのであって,現実的有actuale esseではなくて理性の有entia rationisにすぎないからです。よって最大限に拡大された自然権を人間が実際に有することができるわけではありません。これと同じように自然状態status naturalisも理性の有ですが,そこでは各人の自然権については各人が最大限に行使しているといえるでしょう。ですから国家における自然的権利を侵害して個人の自然の権利を行使するのは愚かなことですが,個人の自然の権利を侵害して国家における自然的権利を擁護するのも愚かなことなのです。
私見ではこのことはスピノザが『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』で,懐疑論者scepticiと独断論者dogmaticiの双方を批判したということに似ています。すなわち自然の権利を最大限に行使しようとするのは,理想の国家像を有することができない懐疑論者であり,人間が最大限に自然的権利を行使できるための理想なしに狂っているのです。これに対して自然的権利を最大限に行使しようとするために自然の権利を行使しようとする者を非難する人は,人間が最大限に自然的権利を行使することができるための理想と共に狂っているのです。
自然的権利の拡大は人間にとって有益ですが,だから自然の権利を譲渡するように要求することはあってはならないと僕は考えます。
明日よりまた日記に戻ることにします。
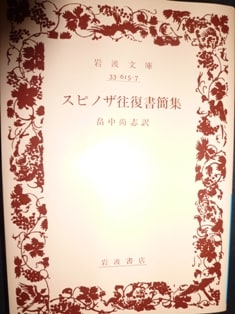
神Deusが罪人に対して怒るということ,あるいは神は人間の行動を認識し,判定し,裁きを与えるという意味のことが聖書には書いてあります。スピノザによればそれは,聖書が人間的ないい方に倣い,民衆の伝統的な見解opinioに順応するように語っているからだとされています。したがって,実際に神が怒ったり裁いたりすることはないというのがスピノザの考え方であることが分かります。ただしスピノザは,だからそのような記述についてそれを批判しているのではありません。むしろそれは聖書の目的に適合するものであるといっています。なぜなら,スピノザの考え方によれば,聖書が意図するのは哲学を教えること,いい換えれば真理veritasを教えるという点にあるのではないし,人びとを賢明にするという点にあるのでもなく,ただ人間を従順にするという点にのみあるからです。
イエスの受難と死と埋葬については,スピノザは文字通りに解するといっています。つまりそれに関しては聖書に記述されてあることを真理,実際にあった出来事として解するという意味です。ただし復活に関しては比喩的に解するといっています。つまり復活に関しては史実とは解さないという意味です。ただし福音史家,これはマタイ,ルカ,マルコ,ヨハネのことを指していると思われますが,かれらがイエスが復活したと信じたことは疑い得ないとしています。同時にかれらは,その点については間違い得た,要するに間違えたのです。とはいえこうした間違いのゆえに福音書の教説自体が損なわれるというものではないと主張している点は,やはり聖書の意図をスピノザがどのように把握しているのかということから説明することができるでしょう。
スピノザの著作としては『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』と関連した議論になっています。この時代のオルデンブルクとの書簡のやり取りは,『神学・政治論』の理解のために有益だと思います。
人間が自然権jus naturaleの一部を譲渡することによって自然権naturale jusの拡張を果たすがゆえに,自由の人homo liberはその自然権が最大限に拡大された国家Imperiumで生活することを欲望することになります。したがって,自身が自然権の一部を譲渡することで自然権が拡大されることを知らず,それがために自身の自然権だけを行使することを欲望する人は,自由の人とは反対の意味で無知の人といわれなければなりません。しかしながら,僕の考えでいえば,拡大された自然権を保守するために,共同の決定に従わない人間のことを非難するのは,同じように無知の人がすることであって,自由の人がすることではないのです。これはそうした非難が憎しみodiumの連鎖を産出してしまうからという理由もありますが,別の理由もあります。それは,すべての人間が自然権を譲渡し合って理性ratioに従うということは,理想ではあるけれどもあくまでも理想にすぎないのであって,現実的有actuale esseではなくて理性の有entia rationisにすぎないからです。よって最大限に拡大された自然権を人間が実際に有することができるわけではありません。これと同じように自然状態status naturalisも理性の有ですが,そこでは各人の自然権については各人が最大限に行使しているといえるでしょう。ですから国家における自然的権利を侵害して個人の自然の権利を行使するのは愚かなことですが,個人の自然の権利を侵害して国家における自然的権利を擁護するのも愚かなことなのです。
私見ではこのことはスピノザが『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』で,懐疑論者scepticiと独断論者dogmaticiの双方を批判したということに似ています。すなわち自然の権利を最大限に行使しようとするのは,理想の国家像を有することができない懐疑論者であり,人間が最大限に自然的権利を行使できるための理想なしに狂っているのです。これに対して自然的権利を最大限に行使しようとするために自然の権利を行使しようとする者を非難する人は,人間が最大限に自然的権利を行使することができるための理想と共に狂っているのです。
自然的権利の拡大は人間にとって有益ですが,だから自然の権利を譲渡するように要求することはあってはならないと僕は考えます。
明日よりまた日記に戻ることにします。













