古い本 その27 化石採集の開始
私が初めて化石見学に行ったのは小学校5年生の頃。父が岐阜県の金生山に連れて行ってくれた。採集はあまりできなかったが今でもその時の標本を持っている。以前このブログで出したことがあるが、再録しておく。

27-1 そのころの金生山 1958.8.27 父が撮影
中学生になって、理科のS先生に瑞浪の戸狩に友人たちと一緒に案内していただいた。その時の標本が次の写真。高校生になると、自分たちで何度も土岐市などの化石産地を訪問した。

27-2 初めて瑞浪に行った時の標本 Culutellus izumoensis Yokoyama 1959.8.24採集、その直後撮影

27-3 同じ標本の現在の姿
化石に関する本で、実際の採集とつながりのあった本はほとんどなく、次の本だけだろうか。

27-4 1963年発行「愛知県とその周辺 地学案内」郷土地学教育研究会・編 浜島書店
縦18.2センチ、幅10.2センチのポケットサイズの本で、125ページまでのノンブルが打ってあるが、111ページから後は方眼紙があるだけだから、内容のあるのは110ページ、それに奥付の後ろに綴じ込みの2枚がある。綴じ込み1枚目は「瑞浪化石一覧表」として地域別に産出するところに印をつけた表である。二枚貝40種、巻貝35種、その他ツノ貝類・フジツボ類・カニ類・・・と長い表である。哺乳類は4種類がリストアップされていて、Desmostylus japonicas, Cornwallius sp., Rhinoceros pugnator, Cetacea indet. となっている。デスモスチルスは、1914年に日本で最初の絶滅哺乳類として命名されているが、そのホロタイプが瑞浪市産出の標本だからもちろんここに挙げられている。次のものは、土岐市の隠居山産のパレオパラドキシアで、1950年の発見。すでに1961年にはIziri and Kameiがこの標本(の頭部)をPaleoparadoxia tabatai として記載したから、その学名で書かれてもいいはずだが。次のサイについても、1921年にMatsumotoがChilotherium pugnator として記載しているからその名前でリストアップして欲しかった。しかも他にゾウ・シカ・バクなどを記録し、新種名をつけているから、リストはさらに賑やかになっているはず。最後の鯨は、この時点ではこれしか書けないはず。私は後に瑞浪層群の哺乳類化石研究のレビューを行ったから、この本と出会ったのが大きなきっかけとなったのは間違いない。もう一枚の綴じ込みは「愛知県周辺地質略図」(40万分の一)である。
最初の方に「執筆者」のリストがあって、愛知学芸大学名古屋分校の三人の先生が中心となり、県内の小中学校・高等学校の教師のみなさんが執筆されていたことがわかる。筆頭は吉田新二先生で、私は後に可児町の調査で大変お世話になることになる。他に3人ほどの先生がたを存知あげているが、もちろんこの本を買った時点ではお二人ほどしか知らないでいたようだ。入手したのは、たぶん高校卒業前後のことだろう。だからこの本を見て現地を訪れた、という地点は少なかったが、採集に行ったところのことを後になって確認したという形である。
本文の内容は、各地点ごとにアクセスや見学すべきことなどがまとめてある。

27-5 土岐市の見学地
上のページには地図と化石の例とともに見学の要点が書かれている。地図を見ると、土岐津駅(現・土岐市駅:1965年改称)から北に隠居山などに行く経路が書かれているが、その間は水田の記号があって、現在との違いが大きい。

27-6 5万分の一地形図「美濃加茂」1960年発行
この地形図が、高校生の頃初めて入手したもので、これを持って採集に行った。上の方のやや左寄りにある×印が隠居山。当時は行ったところに赤い線を記入したのだが、バスは使わなかったから中央本線以外は歩いたところ。ずいぶん遠くまで行った。この図の中にほかの化石産地も入っている。定林寺(少し図の外に外れる)や中肥田など。駅の西にある踏切を渡って北に向かう隠居山までの道は高校生の頃何度も通った。当時は名古屋市北区の黒川近くにあった自宅から、バスまたは自転車(約4kmもある)で大曽根駅(現在の南口)に行き、中央本線の蒸気機関車の牽く客車列車に乗って土岐津に行った。

27-7 2万5千分の一地形図「土岐」1975年発行
後に買った地形図で、隠居山の位置に黒丸を付けた。前の地形図とずいぶん違う。駅名は「ときし」になっている。中央道ができている。水田は西南の部分に少しだけ残っている。などなど。
私が初めて化石見学に行ったのは小学校5年生の頃。父が岐阜県の金生山に連れて行ってくれた。採集はあまりできなかったが今でもその時の標本を持っている。以前このブログで出したことがあるが、再録しておく。

27-1 そのころの金生山 1958.8.27 父が撮影
中学生になって、理科のS先生に瑞浪の戸狩に友人たちと一緒に案内していただいた。その時の標本が次の写真。高校生になると、自分たちで何度も土岐市などの化石産地を訪問した。

27-2 初めて瑞浪に行った時の標本 Culutellus izumoensis Yokoyama 1959.8.24採集、その直後撮影

27-3 同じ標本の現在の姿
化石に関する本で、実際の採集とつながりのあった本はほとんどなく、次の本だけだろうか。

27-4 1963年発行「愛知県とその周辺 地学案内」郷土地学教育研究会・編 浜島書店
縦18.2センチ、幅10.2センチのポケットサイズの本で、125ページまでのノンブルが打ってあるが、111ページから後は方眼紙があるだけだから、内容のあるのは110ページ、それに奥付の後ろに綴じ込みの2枚がある。綴じ込み1枚目は「瑞浪化石一覧表」として地域別に産出するところに印をつけた表である。二枚貝40種、巻貝35種、その他ツノ貝類・フジツボ類・カニ類・・・と長い表である。哺乳類は4種類がリストアップされていて、Desmostylus japonicas, Cornwallius sp., Rhinoceros pugnator, Cetacea indet. となっている。デスモスチルスは、1914年に日本で最初の絶滅哺乳類として命名されているが、そのホロタイプが瑞浪市産出の標本だからもちろんここに挙げられている。次のものは、土岐市の隠居山産のパレオパラドキシアで、1950年の発見。すでに1961年にはIziri and Kameiがこの標本(の頭部)をPaleoparadoxia tabatai として記載したから、その学名で書かれてもいいはずだが。次のサイについても、1921年にMatsumotoがChilotherium pugnator として記載しているからその名前でリストアップして欲しかった。しかも他にゾウ・シカ・バクなどを記録し、新種名をつけているから、リストはさらに賑やかになっているはず。最後の鯨は、この時点ではこれしか書けないはず。私は後に瑞浪層群の哺乳類化石研究のレビューを行ったから、この本と出会ったのが大きなきっかけとなったのは間違いない。もう一枚の綴じ込みは「愛知県周辺地質略図」(40万分の一)である。
最初の方に「執筆者」のリストがあって、愛知学芸大学名古屋分校の三人の先生が中心となり、県内の小中学校・高等学校の教師のみなさんが執筆されていたことがわかる。筆頭は吉田新二先生で、私は後に可児町の調査で大変お世話になることになる。他に3人ほどの先生がたを存知あげているが、もちろんこの本を買った時点ではお二人ほどしか知らないでいたようだ。入手したのは、たぶん高校卒業前後のことだろう。だからこの本を見て現地を訪れた、という地点は少なかったが、採集に行ったところのことを後になって確認したという形である。
本文の内容は、各地点ごとにアクセスや見学すべきことなどがまとめてある。

27-5 土岐市の見学地
上のページには地図と化石の例とともに見学の要点が書かれている。地図を見ると、土岐津駅(現・土岐市駅:1965年改称)から北に隠居山などに行く経路が書かれているが、その間は水田の記号があって、現在との違いが大きい。

27-6 5万分の一地形図「美濃加茂」1960年発行
この地形図が、高校生の頃初めて入手したもので、これを持って採集に行った。上の方のやや左寄りにある×印が隠居山。当時は行ったところに赤い線を記入したのだが、バスは使わなかったから中央本線以外は歩いたところ。ずいぶん遠くまで行った。この図の中にほかの化石産地も入っている。定林寺(少し図の外に外れる)や中肥田など。駅の西にある踏切を渡って北に向かう隠居山までの道は高校生の頃何度も通った。当時は名古屋市北区の黒川近くにあった自宅から、バスまたは自転車(約4kmもある)で大曽根駅(現在の南口)に行き、中央本線の蒸気機関車の牽く客車列車に乗って土岐津に行った。

27-7 2万5千分の一地形図「土岐」1975年発行
後に買った地形図で、隠居山の位置に黒丸を付けた。前の地形図とずいぶん違う。駅名は「ときし」になっている。中央道ができている。水田は西南の部分に少しだけ残っている。などなど。










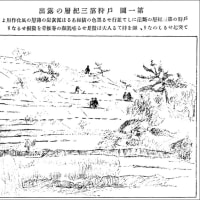









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます