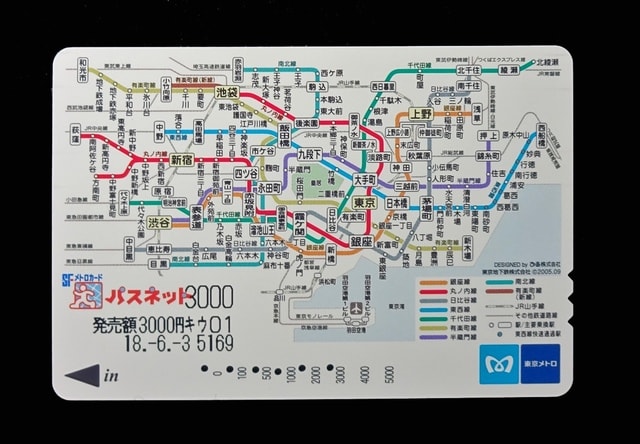小学生のころの写真 その4 三年生
三年の遠足の写真は保存されていない。担任の先生はガリ版刷り・わら半紙の「きぼう」という父兄向けの連絡紙を毎週児童に渡してくれた(年間40枚!)が、それだけではなくもう一セット印刷・保管しておいて、学年末に一年分を製本して下さっていた。

4-1 製本した連絡紙 3号と4号
写真の三年と四年のものが手元にあるから、この2年間については行事が分かっている。4月28日に遠足があって、行き先は「大井」となっている。大井というのはたぶん岐阜県の大井ダムだろう。集合も解散も名古屋駅だから中央本線の恵那駅で下車し、バスで向かったのだろうか。写真はない。
5月24日には滋賀県の醒ヶ井の養鱒場に行っている。

4-2 醒ヶ井の養鱒場 1961.11.21 父の撮影
これは「学級遠足」となっている。卒業アルバムに写真がある。バックにバスが写っているから、貸切バスで行ったらしい。さらに11月2日にも名鉄電車で岐阜に遠足を行っている。
学芸会の写真は8枚あるが、3枚はいわゆる「サービス版」で、観客席の下手やや高いところから撮ってある。ここではその内2枚を紹介する。

4-3 三年学芸会1 1956年2月29日

4-4 三年学芸会2 1956年2月29日
内容はかすかに覚えていて、古代の火の使用の起源のことだったようだ。ろうそくを持った9人がイントロの朗読をし、その後古代人の姿の演劇があった。私はイントロの一人だったと思う。
残り5枚の写真は、その半分のサイズで、客席から撮影しているから視点が低い。撮影者が二人いたことになる。ここではそのうちの1枚だけ紹介する。

4-5 三年学芸会3 1956年2月29日
三年の遠足の写真は保存されていない。担任の先生はガリ版刷り・わら半紙の「きぼう」という父兄向けの連絡紙を毎週児童に渡してくれた(年間40枚!)が、それだけではなくもう一セット印刷・保管しておいて、学年末に一年分を製本して下さっていた。

4-1 製本した連絡紙 3号と4号
写真の三年と四年のものが手元にあるから、この2年間については行事が分かっている。4月28日に遠足があって、行き先は「大井」となっている。大井というのはたぶん岐阜県の大井ダムだろう。集合も解散も名古屋駅だから中央本線の恵那駅で下車し、バスで向かったのだろうか。写真はない。
5月24日には滋賀県の醒ヶ井の養鱒場に行っている。

4-2 醒ヶ井の養鱒場 1961.11.21 父の撮影
これは「学級遠足」となっている。卒業アルバムに写真がある。バックにバスが写っているから、貸切バスで行ったらしい。さらに11月2日にも名鉄電車で岐阜に遠足を行っている。
学芸会の写真は8枚あるが、3枚はいわゆる「サービス版」で、観客席の下手やや高いところから撮ってある。ここではその内2枚を紹介する。

4-3 三年学芸会1 1956年2月29日

4-4 三年学芸会2 1956年2月29日
内容はかすかに覚えていて、古代の火の使用の起源のことだったようだ。ろうそくを持った9人がイントロの朗読をし、その後古代人の姿の演劇があった。私はイントロの一人だったと思う。
残り5枚の写真は、その半分のサイズで、客席から撮影しているから視点が低い。撮影者が二人いたことになる。ここではそのうちの1枚だけ紹介する。

4-5 三年学芸会3 1956年2月29日