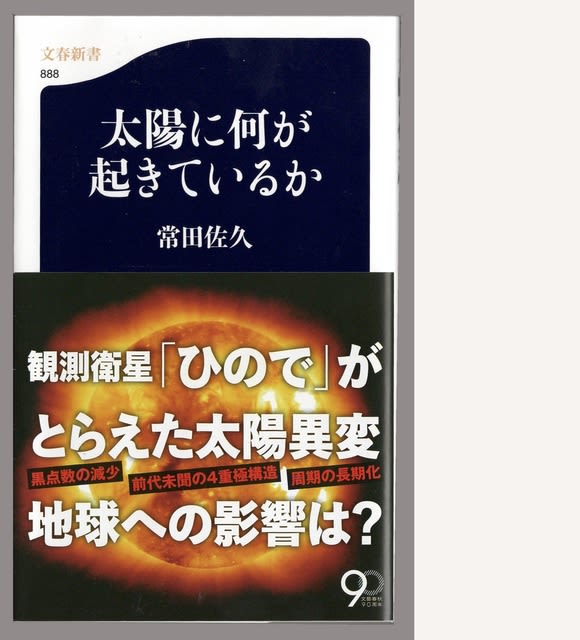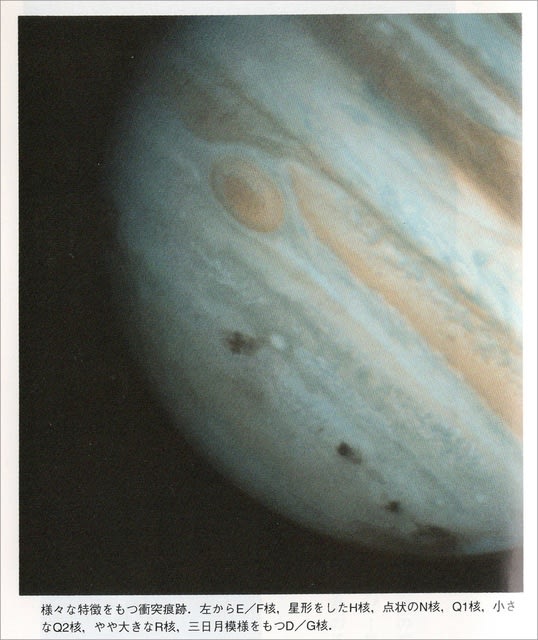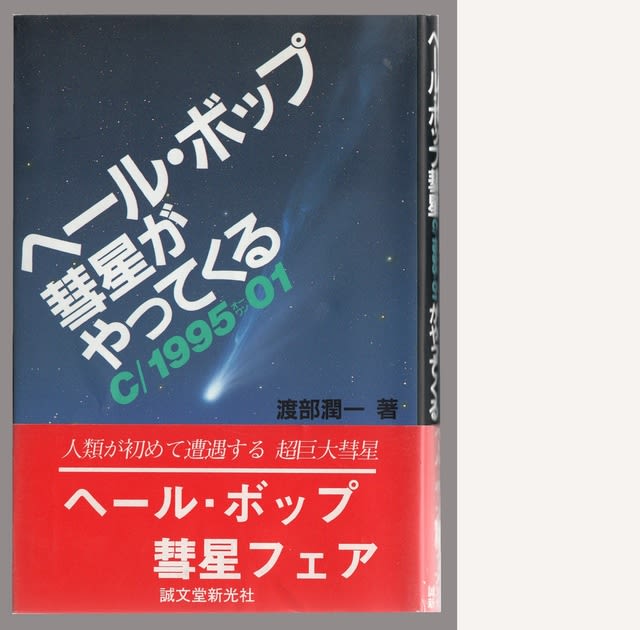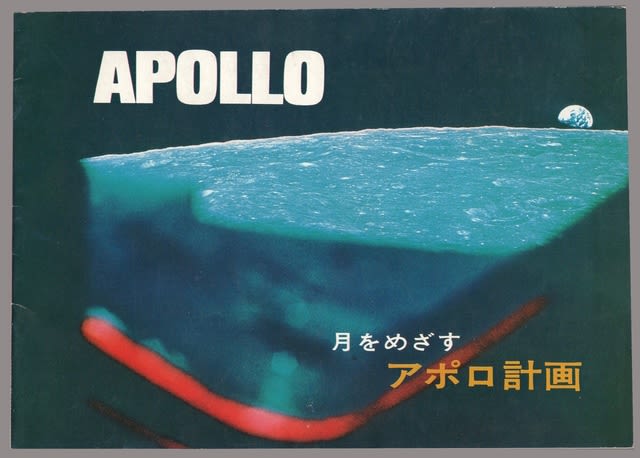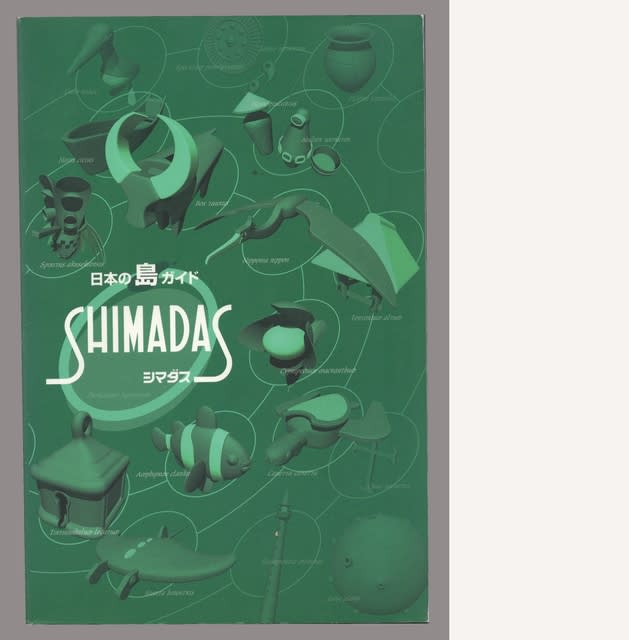ガガーリン(臨時投稿)
この投稿が数日遅れてしまったが、60年前の1962年5月25日に私はガガーリン氏と握手(といってもこちらから勝手に手を伸ばしたのだが)した。その前年に人工衛星で人類最初の地球周回をした彼は、世界各地を回ってパレードや集会に参加してソビエトの国威発揚に努めた。
日本でも東京ばかりではなく幾つかの都市を訪れた。私が見たのはそのうちの名古屋・金山体育館で行われたものだった。私は当時親しくしていた同窓生のM君とともに行った。M君は物理・天文・宇宙といったところに詳しく、その影響は現在の私にも強く働いている。観客席の中央に前後方向の赤絨毯が敷かれ、彼は後ろの出入り口から入って中央を通って壇上に上る手順だった。警備はゆるくて、絨毯を歩く彼に多くの人たちが手を差し伸べていた。私はその一人。握った手はやや湿っていて暖かく、分厚かった。意外にも巨漢ではなく、軍服に包まれた体は筋肉質の印象があったが、記憶はあいまい。
会場は政治的色彩が強くて、私はそういう場に慣れていなかったから戸惑った。ガガーリン氏は数年後に戦闘機の事故で亡くなった。
記憶しているのはこの程度。後に私は日本の宇宙飛行士の毛利 衛氏とお話しする機会があった。この時、ガガーリン氏と「握手」したことを告げると、大変に羨ましがられた。「ガガーリンの手のぬくもりをお伝えします。」などと、柄にもあわないことを言って毛利氏と握手させていただいた。こんどは双方の意識があっての握手であった。毛利氏は、「私はアームストロング氏と握手をしたことがあるので、(そのぬくもりを)お返しします。」と答えてくださった。
そんなわけで、「私と握手した人がそれ以前に握手した人」のリストには、たぶん次のような方々が含まれる(敬称略)。宇宙飛行士のチトフ・テレシコワ・アームストロング(ニール)・コリンズ・オルドリン。他ケネディー・フルシチョフを含む当時の各国首脳(今年在位70年のエリザベス女王とガガーリン氏は会っているが握手しただろうか?)。
この投稿が数日遅れてしまったが、60年前の1962年5月25日に私はガガーリン氏と握手(といってもこちらから勝手に手を伸ばしたのだが)した。その前年に人工衛星で人類最初の地球周回をした彼は、世界各地を回ってパレードや集会に参加してソビエトの国威発揚に努めた。
日本でも東京ばかりではなく幾つかの都市を訪れた。私が見たのはそのうちの名古屋・金山体育館で行われたものだった。私は当時親しくしていた同窓生のM君とともに行った。M君は物理・天文・宇宙といったところに詳しく、その影響は現在の私にも強く働いている。観客席の中央に前後方向の赤絨毯が敷かれ、彼は後ろの出入り口から入って中央を通って壇上に上る手順だった。警備はゆるくて、絨毯を歩く彼に多くの人たちが手を差し伸べていた。私はその一人。握った手はやや湿っていて暖かく、分厚かった。意外にも巨漢ではなく、軍服に包まれた体は筋肉質の印象があったが、記憶はあいまい。
会場は政治的色彩が強くて、私はそういう場に慣れていなかったから戸惑った。ガガーリン氏は数年後に戦闘機の事故で亡くなった。
記憶しているのはこの程度。後に私は日本の宇宙飛行士の毛利 衛氏とお話しする機会があった。この時、ガガーリン氏と「握手」したことを告げると、大変に羨ましがられた。「ガガーリンの手のぬくもりをお伝えします。」などと、柄にもあわないことを言って毛利氏と握手させていただいた。こんどは双方の意識があっての握手であった。毛利氏は、「私はアームストロング氏と握手をしたことがあるので、(そのぬくもりを)お返しします。」と答えてくださった。
そんなわけで、「私と握手した人がそれ以前に握手した人」のリストには、たぶん次のような方々が含まれる(敬称略)。宇宙飛行士のチトフ・テレシコワ・アームストロング(ニール)・コリンズ・オルドリン。他ケネディー・フルシチョフを含む当時の各国首脳(今年在位70年のエリザベス女王とガガーリン氏は会っているが握手しただろうか?)。