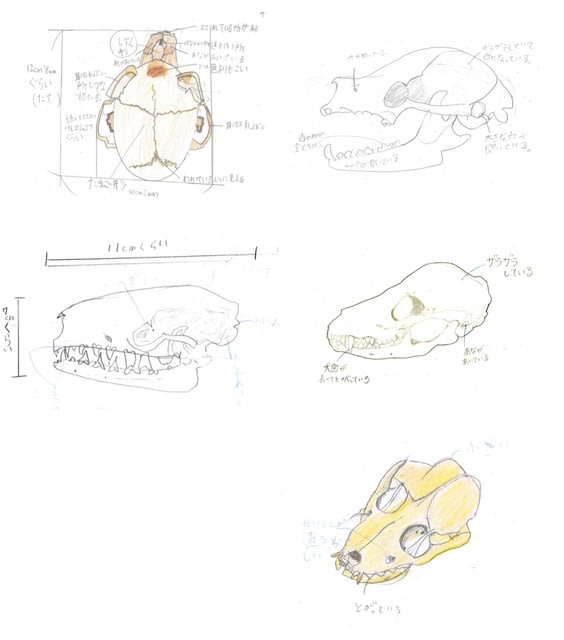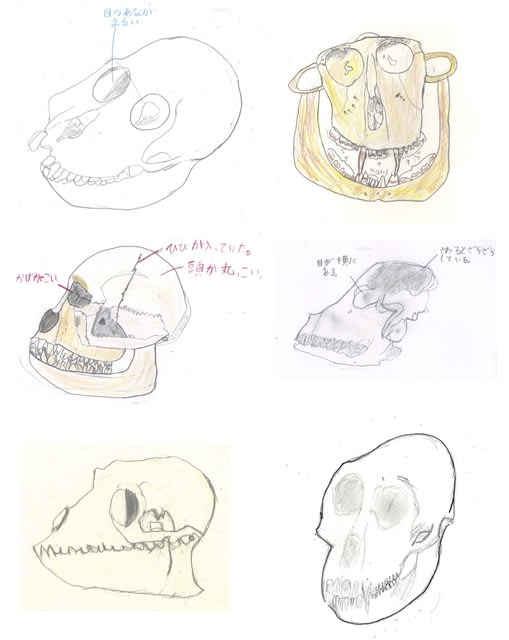それからニワトリも作りました。
こちらは初めの方から撮影しました。ザクザクと形を整えます。かなりいい加減です。

もう少し丁寧に頭や尾の形を整えて行きます。この段階ではハトにも見えます。

羊と違って難しかったのは、足です。なんと言ってもニワトリは2本足ですから、これが立つようにするのはやさしくありません。アルミ針金を3本用意して1本は脚の部分を螺旋状に巻きつけます。それを胴体に差し込んで、粘土をつけます。もちろん実際の足よりも指が長くなっています。そうでないと立ちません。そして胴体の方を動かせて安定する角度を見つけます。
トサカをつけるとどうみてもニワトリ、もうハトには見えません。もっともこの少し前の段階でも胴体に粘土をつけてニワトリらしくなってはいませいたが・・・。やはりハトは胸が大きく、ニワトリはお腹が大きいのです。

それから色をつけますが、まずベースになるオレンジ色を塗ります。

それから茶色、こげ茶色で羽を塗って行きます。

それから足を黄色に塗り、だいたい出来上がりです。
紙粘土は継ぎ足すことも、削ることもできて、やり直しが効くので、気楽さがあります。一日、少しずつ完成に近づくのは楽しいものです。

こちらは初めの方から撮影しました。ザクザクと形を整えます。かなりいい加減です。

もう少し丁寧に頭や尾の形を整えて行きます。この段階ではハトにも見えます。

羊と違って難しかったのは、足です。なんと言ってもニワトリは2本足ですから、これが立つようにするのはやさしくありません。アルミ針金を3本用意して1本は脚の部分を螺旋状に巻きつけます。それを胴体に差し込んで、粘土をつけます。もちろん実際の足よりも指が長くなっています。そうでないと立ちません。そして胴体の方を動かせて安定する角度を見つけます。
トサカをつけるとどうみてもニワトリ、もうハトには見えません。もっともこの少し前の段階でも胴体に粘土をつけてニワトリらしくなってはいませいたが・・・。やはりハトは胸が大きく、ニワトリはお腹が大きいのです。

それから色をつけますが、まずベースになるオレンジ色を塗ります。

それから茶色、こげ茶色で羽を塗って行きます。

それから足を黄色に塗り、だいたい出来上がりです。
紙粘土は継ぎ足すことも、削ることもできて、やり直しが効くので、気楽さがあります。一日、少しずつ完成に近づくのは楽しいものです。