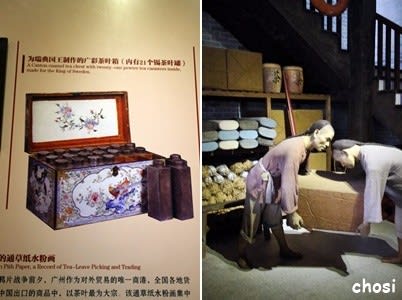広州二日目、茶城でショッピングした後は嶺南古玩城へ。
ご一緒してくださったのはYuiさんの茶友in広州、Kさんです。
Kさんは上海でお茶を学ばれ、その後台湾にもお住まいになり、現在は広州在住、
中国茶も台湾茶もスペシャリストの方です。
骨董は玉石混交?
茶器はそれほどたくさんありませんでしたが、
お手頃価格で少し年代ものの蓋碗をひとつ持ち帰りました。
そのまま広州の古い町並みを散策し、軽く夕食を取ってから向かったのはとある茶館。
出発前にYuiさんからどこか行きたい場所の希望は?と聞かれ、
飲茶のできる茶館以外に、現代的な茶館もご紹介くださいとお願いしていました。
YuiさんとKさんがチョイスしてくださった一軒目は「嘆茶来」茶館。
広州茶文化促進会の副秘書長を務め、茶藝の指導に携わって20年近くのキャリアを持つ鄧婷老師がオーナーの茶空間です。
窓際や仕切りの棚に茶や茶器がディスプレイされ、
中央に長机が置かれた部屋は心地よい広さで、茶館というよりはサロンの趣。
まずはプーアル生茶を飲ませていただき、同席の方々とご挨拶。
続いて鄧老師は日本から来た私たちのために特別に擂茶を用意してくださっていました。
江西省出身の鄧老師は小さい頃から擂茶に親しんでこられたとのこと、
お客様が見えた時には必ず振る舞われるのだそうです。

茶の生葉はあらかじめ細かくすりつぶしておきます。
そこにピーナツ、ゴマ、ミントを加え、湯を適宜足しながらすり鉢ですりつぶしながら混ぜます。

一人一人すりつぶし体験!
出来上がったらお好みで砂糖を加えていただきます。

ゴマとピーナツの香ばしい香り。
ピーナツに塩分があるので、ほんのり塩気と砂糖の甘さで飲みやすく美味しい。
特に決まったレシピはなく、その家庭の味というのがあるというのも面白いですね。
この日は鄧老師のリクエストで表千家茶道をたしなむKさんが茶の湯をその場で点ててくださいました。
これぞ日中お茶交流ですね。

表千家の点て方と裏千家の点て方の違いも体験していただくために、
僭越ながら私も裏千家の方法で茶筅を振らせていただきました。
今、中国では抹茶のお菓子がとても人気だとか。
宋代の点茶に通じる日本の茶の湯にもとても関心が高いようです。
鄧老師のお話を伺っていて、今の中国の茶文化復興の思いの強さを感じます。
茶藝のやり方もしつらえも刻々と変化しています。
今はお茶は健康志向、しつらえはシンプルイズベストに向かっているという印象を受けました。
そして、茶藝館などでの茶藝披露や
茶会での華美な演出よりも
これからは生活の中に茶文化を取り入れ、
茶によって生活に潤いを持たせ、精神的にも余裕を持つ、
という意識にベクトルが向いているのを感じました。
店名の「嘆茶来」ですが、広東では飲茶を「嘆茶」とも呼ぶのだとか。
「嘆」は広州の俗語で、「享受する」という意味。
英語で言えばENJOYに通じる意味でしょうか。
鄧老師の思いが「嘆茶来」の文字に表れているような気がしました。