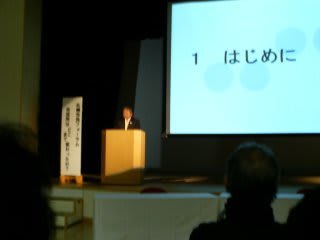なぜか疲れがどっと出て午前中はぐったり。たまにはこういう日もあるのです。
【友引は迷信?】
今日の北海道新聞札幌版に「友引の市営火葬場休業~『迷信だ』NPOが稼働陳情」という記事が載っていました。
内容を要約すると、市内のNPO法人が市営火葬場を「友引」稼働させるように求める陳情を市議会に提出し、議会の厚生委員会で審査されたということなのです。
***(以下、北海道新聞からの引用)***
友引は「葬儀を出すと、他人の死を誘う」とされるが、○○(記事では実名)代表は委員会で、由来は中国の占いで、宗教とは関係のない「迷信」であると指摘。火葬場が休業している現状について、
①葬儀を友引後にするため、遺体を安置する会場の費用や葬儀参列者の宿泊費用がかさむ
②遺体の痛みが進む
などと問題点を挙げた。
これに対して市保健福祉局の大津英三生活衛生担当部長は、友引も稼働していた1978年から82年までの一日の平均火葬数が1.9件と、それ以外の26.5件を大きく下回っていたことから「友引は利用が多いとは思えない」と説明した
***(引用終わり)***
この背景には火葬場の改修に伴う一時的な不足への不安があるようです。現在札幌市には火葬場が二カ所あるのですが、そのうちの一カ所が改修のために二年間閉鎖されることになっていて、改修の始まる来年4月からは集中による混雑が予想されるとのことです。
一部の議員からは「現在と当時の市民の意識には変化があるのではないか」という意見もあったようですが、市側は「稼働すれば人件費などで年間4千万円程度の支出増になり利用料値上げにつながりかねない」と稼働の考えはないと強調した、とも書かれていました。
ところがこのNPOの調べでは全国の15政令都市で友引に休業しているのは札幌市のほか、川崎市など4市で、道内では函館市が稼働している、のだそうです。
私は、迷信や風習、文化が経済とどのように関わるのか、という点で極めて面白い問いかけだと思いました。
風習や文化、伝統的な考え方ということがらは「世間の常識」に由来するものですからもちろん法律や条令などにそのことを根拠として書き込むことは適当ではありません。
世間の常識が変化すれば対応が変化しても構わないわけで、それを伝統の破壊と呼ぶか、時代の変化と見るかは判断の分かれるところです。私はなにか問いかけがあったときには、世間の常識を問いただしてみることは正しいアプローチだと思います。
今回の件では、実際に友引に稼働させたときに収入に見合う利用が見込めるのかどいうことがとりあげられていますが、現実にはそれほどの利用は期待出来ないと思います。
逆に友引も稼働させている他の自治体の例を見て、それらが今現実に友引の日にどれくらいの稼働率であるのかを調べる方が先のような気もします。NPOもそこまで調べたならば、「友引でも利用率は他の日と遜色がない」というくらいのデータを出せるならば力強い意見になるのでしょうが、そういうデータがなかったのでしょうか。
更に言えば、現在稼働している自治体であっても、友引の日の利用率が少なければ稼働をとりやめるくらいの判断があっても良いのかも知れませんね。
今回は、経済的理由を前面に出してその効率性を問うていますが、私自身の生き物としての感覚から言えば、何事につけ「一定の割合で休憩を取ることの自然さ」を大切にしたいものだと思います。
例えその根拠が迷信や風習だとしてもです。
施設の管理を携わる身から言うと、施設には点検や補修などもあるわけで、稼働することだけが行政サービスなのではなくて、稼働すべきときに安定した稼働を約束するということだって質の高いサービスの重要な要素だと思うのです。
短絡的に考えると「伝統的な考えを破壊する不埒なNPO」や「楽をしたい安易な行政運営」という批判もあり得そうですが、一方的な視点ではなく、経済的、道徳的、心情的、伝統的など様々な角度からの合理性を十分に斟酌して総合的に判断していただきたいものです。
私ですか?個人的には稼働しなくてもよいのではないか、と思いますが、皆さんはいかがですか?