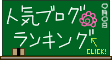●
2010-2011シーズン聴いたコンサート観たオペラはこちらから。
.
2011年3月5日(土)3:00pm
サントリーホール
.
≪オール・ドヴォルザーク・プログラム≫
序曲「謝肉祭」
ヴァイオリン協奏曲
ヴァイオリン、レオニダス・カヴァコス
(アンコール)イザイ
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第4番から「アルマンド」
.
交響曲第7番
(アンコール)
スラヴ舞曲第2番
スラヴ舞曲第7番
.
リッカルド・シャイー指揮
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
.
●
久しぶりにゲヴァントハウスのサウンドを聴いた。
音がでかくてびっくり。昔はこんなでかい音は出さなかった。その昔初めてこのオーケストラを聴いたのは1975年の3回目の来日公演でのマズアの棒による第九その他。
今日の音のでかさに比べたら慎ましやかというか、音も配置も内向きだったような記憶。古くからの格式もあるが、それでもっていたといったところだったのだが。
.
それで今日の演奏ですが、その前にどうしてもいまだに、ゲヴァントハウスとシャイーの組み合わせには違和を感じてしまう。両方ともに別々なイメージが身についてしまっているのかもしれない。ゲヴァントハウスの方は書いた通りで、シャイーの方は、アバドがスカラ座を去ったのちイタオペの権化になるのかと思っていたのだが、そのへんちょっと残念に思っているわけです。
最初の曲の謝肉祭はダイナミックでメリハリが効いており、また細部のデリカシーはまるでイタオペでも聴いているような錯覚。見事なコントロールというしかない。ばねのような飛び跳ねはさすがにもうしないが、それでも体全部で表現していくあたり、アバドのあとスカラ座背負ってもよかったんじゃないか、と思うわけです。ムーティがどうだこうだと言っているわけではありませんよ。
細部のデリカシーと言えば、たとえばサンティがイタオペを全部暗譜で振りまくると、情緒に流される泣き節のあたりめんめんと歌いまくるような気がするのだがそんなことはなくてわりと、サッと切り上げるんですね。インテンポの歌い口とでもいいましょうか。ここらへんトスカニーニなど昔からの流儀なんでしょうか。それで、シャイーのこの謝肉祭なんか聴いているとまさにそんな感じなんです。かなり歌いますがみ切りも早いといった感じです。この雰囲気がイタオペの節回しのコツなのかどうかわかりませんが、イタリア人の棒によるイタオペってわりと時間かからずおわっちまうんです。いいものはさっと。いつまでも浸ってなくてもいいから、次に進もうといった雰囲気。謝肉祭もそんな感じに聴こえてきてしまってドヴォルザークの曲のような気がしなかった。プレイヤーの演奏する喜びのようなものが湧き出てきていい演奏でした。
シャイー自身、華のある指揮者で、オーラが自然に出てきてしまうんですね。前日のブルックナーもおそらくよかったに違いありません。
このオーケストラ、「デラックス」になった。
.
●
プログラム後半の第7番の交響曲でも音のでかさは変わりません。非常にダイナミックでそれでいてしなやか。これは協奏曲の伴奏でも感じたことなんですが、アンサンブルの遠近感が生きて揺れている。そして角のとれた非常に滑らかな弾きっぷり吹きっぷり。ウィンドや弦は、音が出るまでの溜めが独特で、言葉ではうまく表現できないけれど、
「ズシーン」
ズではなくシーンに力がわりとまばらにはいってくる。ちょっとへたをするとマーラー的やにっこさのような響きと間違いかねないところがありますが曲が曲だけに目立つところではない。
音のでかさばっかり言ってますけど、デラックスにはなったのだが、音の粒立ちはドヴォルザークという曲に助けられている。粒立ちは今一つ、また、全奏での音の濁りは、アンサンブルの良さとはまた別の話ではある。ブラス、弦の森のなかでのピッチの濁りは強大なサウンドに隠された一つの弱みではある。
.
それで、この7番は形式感を言われるわけですけれど、シャイーの棒にかかるとアンコールでやったスラヴ舞曲風な散文調になる。交響曲というよりは舞曲を四つ聴いたような感じの交響舞曲みたい。噛みしめる味わいはイタオペのように深く音の響きの饗宴に共感した方向にうまく流れる。それがすべてではない。第2楽章のいかにも素朴極まるようなウィンドのアンサンブルに導入され、うち震えるようなヴァイオリンのアウフタクトからの歌う溜息。何とも言えずいい。えも言われぬ美しさ。ダイナミックというのはこのように曲という構築物全体感のなかでの振幅にも見事に表現されていて、シャイーの棒が一段と光る。ドヴォルザークの音楽が美しく流れていきますね。
音の粒立ちというのは個々人の技術レベルから直結されたものだと思うわけですけれど、第3楽章のような全奏ではない比較的薄い編成の鳴りのあたりでは気持ちよく体感。スタッカート風な響きに魅了されました。
第4楽章は短調の第1楽章と対のようになった楽章でやっぱりダイナミック・デラックス感が素敵です。響きが現代的といっては月並みかもしれませけど時代とともに変化して当然です。何が変わって何が変わらないのか、別に全部変わってしまってもいいと思いますよ。アンサンブルに昔のドライな埃っぽさはなく濡れた響きを感じたのは、音がでかくなった以上に変化を感じた瞬間でした。
.
●
前半2曲目のヴァイオリン協奏曲は、ないがしろにされないオーケストラの陰影が美しく、噛むほどに味が出てくる。それだけで個体となれるような素晴らしい充実度でした。シャイーはそもそも伴奏という行為がわりと好きなのではないのかと思ってしまいます。独奏ヴァイオリンの息をうかがっているのではなくオーケストラを自分の表現で固めていてヴァイオリンの方がついていっているような気がしました。そんな気配があるんです。ですので、ソロは浮くようなところがまるでなくオーケストラとの一体感。表現力が弱いといった裏返しの言葉もあるのかもしれませんがそんな感じはまるでなく、オーケストラと音楽に溶け込んでいった。だから逆にアンコールのイザイの無伴奏があんなに素晴らしかったのもよく理解できる。
ドヴォルザークのこの協奏曲は縦に音が小気味良く響き、うまく揃うと非常にすっきり爽快ですね。粒立ちの良さもここでは味わえました。ソロがヴァイオリンのめんめんといったあたりの特性をあまり強調することなくプレイヤーの一人のように合わせていたと思います。
それにしてもアンコールのイザイは素晴らしかった。力ではなく響き。ヴァイオリンの響きの美しさが多面的にポリフォニックに積み重なるあたりの美しさはなんだか哲学的な様相を呈した。言いすぎかな。
.
とにかくいい演奏会でした。
.
●
ところで、またおさらいですけれど、
ゲヴァントハウスを初めて聴いたのが、1975年の11月、クルト・マズアの棒によるレオノーレ3番と第九でした。
シャイーを初めて見聴きしたのはたしかこれ。
1985年10月29日(火)7:30pm
エイヴリー・フィッシャー・ホール
ニューヨーク・フィルハーモニック
ブゾッティ/フローレンスより(アメリカ初演)
ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第4番
ピアノ、アンドレ・ワッツ
プロコフィエフ/交響曲第3番
シャイーのニューヨーク・フィルハーモニック・デビューでした。
詳細はそのうち。
.
●