 1月度に引き続いて、NHK文化センター梅田教室で開催されたスズケン市民講座「読書の面白さ、大切さ~年間300冊の読書術~」に参加しました。講師は女優・脚本家である中江有里さんです。
1月度に引き続いて、NHK文化センター梅田教室で開催されたスズケン市民講座「読書の面白さ、大切さ~年間300冊の読書術~」に参加しました。講師は女優・脚本家である中江有里さんです。
写真は日経ウーマンオンラインのブログ”本が教えてくれること”より。市民講座のリーフレットにもこの写真が使われていたようです。
~案内のリーフレットより~
読書は、すぐに出来る心の旅行です。日常を豊かにするヒントがつまった
本の魅力について、NHKBS「週刊ブックレビュー」の司会者がお話します。
私も読書は大好きですが、年間に読むのは小説・ノンフィクション・新書を中心に70冊程度です。殆どが大阪(自宅)~京都(会社)間の通勤電車の中で読みます。通勤時間は片道1時間40分~50分ですが、電車を4本乗り継ぐので(地下鉄-地下鉄-京阪-近鉄)、なかなかまとまった時間を確保するのが困難です。唯一40分以上乗る京阪特急では睡魔に負けることが殆どですしね。中江さんの場合、ある程度はお仕事との関係もあるでしょうが、それでも年間300冊は凄いと思います。
今回はどんな話をされるのか興味津々に思っている中、いよいよ中江有里さんの登場です。あら~、想像していたよりもずっと小柄な方でちょっとビックリ!ホームページなどで身長154cmとなっていたのを後から知りました。あまり女優さん女優さんしておられず(? 失礼!)、第一印象は小柄で美しく可愛らしい女性といった感じの方でした。映画では昔、「ふたり」(石田ひかり、中嶋朋子ほか)などに出演されたのを観たことがあります。
女優になる前から何かを書きたいという思いがあったそうで、女優・脚本家・週刊ブックレビューの司会者にはなるべくしてなられたのかもしれません。常に複数の本を併読し、いずれも最後まで読まれるとのこと。併読のポイントはテイストの異なったものを読むことだそうです。
さて、講座は意外にも聴衆参加型でした。
最初にあった1ケ月に何冊くらい本を読むか手を上げたりはよくあると思いますが、講座の途中で、あらかじめ配られていた森鴎外の「牛鍋」という作品を聴衆が一人一文ずつ音読していくのにはビックリ。テキストの難しい漢字にはフリガナも符されていますが、自分に回ってきそうな部分が気になって、そこまでは文章の内容が頭に入りませんでした(汗)。
このテキストを題材に話されたポイント:
・複数で声に出して読む面白さ。
・文章で説明されていない内容が多く、読者は自ずと想像力が膨らむ
/想像力を膨らませることになる。
→多彩な読み方や解釈が可能。色んな疑問点が出てきたりも。
・読者がいて本が成り立つ。
・作者と読者がいて本が成り立つ。
自著「結婚写真」(良い本でした)を含めて何度か本の一節を読まれたのですが、さすがは女優さんです。声が良く、感情移入が見事。セリフとその他の部分の語り方の使い分けも絶妙でした。また、聴衆の音読もあったりしたせいか、美しい先生による(笑)国語の授業を聴いているような感覚もあり、これも面白かったです。
この日紹介された本の中では、荒川洋治「昭和の読書」やマーク・ボイル「僕はお金を使わずに生きることにした」を読んでみたいと思いました。
紹介された本の中の引用も含めて、この日、印象に残った言葉です。
・読書は種のようなもの。蒔かなければ花が咲いて実がつかない。
しかし、どんな実がつくか分からないし、すぐに役立つかどうかも
分からない。けれども、いずれ必ず役に立つ。
・著者が書く/描く海と読者が感じる海は違うはず。
しかし、それで良いし、それが良いと思っている。
→読書の深さ、広さ
・読書はコミュニケーションツール。また、タイムトンネル的でもある。
・他人や世界を俯瞰して見ることができる。
静かに、しかし力強く本や読書の面白さ、大切さ、素晴らしさを語られ、最後は「今は不安の多い時代ですが、不安はパワーに変わります。たくさん本を読んで、たくさんの人と語らってください」という言葉で締めくくられました。
先月の福岡伸一さん(この日、中江さんも「生物と無生物のあいだ」のことを話されました)、今月の中江有里さんとお二方の素晴らしい講演を聴いて、心が豊かになる気がしました。また、中江さんは美しく聡明な方で、読書が(それだけによるものでないにしても)人格や人柄をつくり上げているんだなあとも感じました。
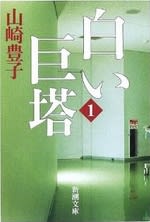
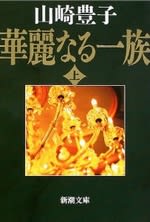




























 1月度
1月度