 シリコンバレーから将棋を観る 羽生善治と現代(中央公論新社)
シリコンバレーから将棋を観る 羽生善治と現代(中央公論新社)
★★★★☆:90点
ウェブ界の稀代の書き手・伝道師として「ウェブ進化論」などの素晴らしい著作があり、私も絶対の信頼を置く梅田望夫氏待望の近著は題材が「将棋」でした。前著でも羽生名人のことが書かれたりしていましたが、あらまー!「将棋」が題材とは!
恥ずかしながら羽生さんの名前は知っていても将棋のことは殆ど知らず&分からず(小学生の頃に駒の動きをちょこっと教えてもらったくらいで、未だかつてきちんと一局を指したことも見たこともなく、今となっては駒の動きすらよく覚えていません・・・)のため、理解できないかもと恐れを抱いて、とりあえず図書館で借りたのですが・・・何とまあ抜群に面白く、ほぼ一気読みで読了しました。さすがは梅田望夫さんです。
「指さない将棋ファン」宣言がありましたが、将棋ファン以前である私でも将棋の素晴らしさ、奥深さ、凄さ、美しさ、タイトル戦の緊迫した空気と想像を絶するギリギリの戦い、棋士たちのもの凄さ(天才たちの絶え間ない研究・研鑽と努力の日々)、高潔さ、人間的な魅力などがひしひしと伝わってきました。細かい指し手のことは分からなくても十分楽しめる傑作で、そのこと自体が凄いです。梅田望夫さんはタイトル戦のリアルタイム観戦記(byネット)と合わせて、また凄い仕事をやってのけたもんだ!
****************************** Amazonより ******************************
「本物の情熱」と「際立った個性」が新しい時代を創っていく
有限の盤上で無限に進化する世界から、我々は何を学び得るか。
トップ棋士と共に真理を探究した一年間の記録!
好きなものがありますか? 極めたいことは何ですか?
――ベストセラー『ウェブ進化論』の著者が「思考(アイディア)の触媒」として見つめ続けてきたものは、将棋における進化の物語だった。
天才の中の天才が集う現代将棋の世界は「社会現象を先取りした実験場」でもある。
羽生善治、佐藤康光、深浦康市、渡辺明ら、超一流プロ棋士との深い対話を軸に、来るべき時代を生き抜く「知のすがた」を探る。
たとえルールがわからなくても、「観る」面白さを知っている、すべての人に。
「私が本当に書きたかったのは、この本でした」――梅田望夫
******************************************************************************
野球ファンやクラシック音楽ファンは自分にはできないことについても感想を述べたり語ったりできるのに、なぜ将棋ファンは「上手くないので(強くないので)」とか「最近は指さないので」といった理由で好きなように語れないのかという疑問からスタートし、見事にその壁をうち破った梅田氏の面目躍如といった感じですね。羽生善治4冠、佐藤康光棋聖、深浦康市王位、渡辺明竜王とガップリ四つに組んでの観戦記と対話・対談がとにもかくにも素晴らしいです。超一流の棋士たちには熱い想いと冷めた&冴えた頭脳が同居しているのでしょうか?もちろん、梅田氏ならではのコンピュータやネットについての洞察も怠りなく、書名にふさわしい内容になっていると思います。
そして、羽生善治のもの凄さ。「盤上に自由がなかった」現代将棋に風穴をあけ、あらゆる戦型に精通したオールラウンドプレイヤーを指向する羽生。この人は将棋の天才であると共に、知情意をそなえた知の巨人でもありますね。既に「ウェブ進化論」で、羽生が語った学習の「高速道路論」とその先にある大渋滞、「けものみち」なども紹介されていたが、羽生は若き日に完成させた(?)「羽生の頭脳」で「情報(IT)革命」の思想を先取りしていた!----”その段階で持っている知識はすべてオープンにする”という「知のオープン化」と「勝つこと」の両立----七冠制覇!「知のオープン化」が成し遂げる凄さは私にも何となく実感できます。現代では、もはや「知」はそれを閉ざしていては「知」ではないということか。「Win-Win」などの考え方とも関係しますね。
竜王戦の第一局で放った渡辺明の心臓をえぐるような一手。「将棋観が根底から覆された・・・」(渡辺)。しかし、渡辺も3連敗の後に巻き返し、遂にタイトル戦では初めての3連敗後の4連勝で初の永世竜王の座を獲得する。その第七局では140手の伝説的な名局を羽生と共に作り出したという。また、渡辺も若くして自分の考えなどをブログ等を通じて伝える、発信するということを行っている。彼が羽生の後継者となるのか・・・。
えー、この本は(この本も)素晴らしいと感じた箇所や印象に残った箇所が非常に多く、以下、それらを少し抜き出してみますと(梅田氏の言葉でないものも含まれています)、
・10年に一度の割合で天才が生まれるという将棋界
加藤一二三、米長邦雄と中原誠、谷川浩司、羽生善治。そして、渡辺明。
・「均衡の美」、終局後の感想戦が「至福の時間」
・人生における「機会の窓」(Windows of opportunity)を生かせるかどうか
・人は、人にこそ、魅せられる
・先駆者・升田幸三の孤独
・量が質に転化する瞬間があるはず----ウェブでは量の制約がない!
・棋士は勝負師と芸術家と研究者の三つの側面を併せ持つ(谷川浩司)
・「超一流」=「才能」X「対象への深い愛情ゆえの没頭」X「際だった個性」
などなど。
よし、遅まきながらちょっと将棋を勉強するか!
◎参考ブログ:
Tetsuro Muranagaさんの”村永: Tetsuro Muranaga’s View”
----支離滅裂な私の感想とは大違いで、もっと高所から語っておられます。











 0マイル ゼロマイル(稲葉なおと)
0マイル ゼロマイル(稲葉なおと) シリコンバレーから将棋を観る 羽生善治と現代(中央公論新社)
シリコンバレーから将棋を観る 羽生善治と現代(中央公論新社)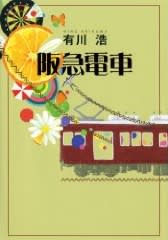 阪急電車(幻冬舎)
阪急電車(幻冬舎) 猫を抱いて象と泳ぐ(文藝春秋)
猫を抱いて象と泳ぐ(文藝春秋)