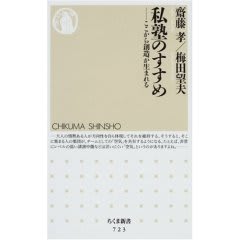「グランド・ミステリー」「鳥類学者のファンタジア」といった問題作・超絶作(?)の作者であり、時空を超えた物語のつむぎ手である奥泉光の作品です。
シンプルorストレートなタイムトラベル、タイムスリップものではなく、ひとひねりもふたひねりも、いや5ひねりくらいあります。最近、時空を超えた物語では梶尾真治の作品をよく読んでいるのですが、味わいは全く異なります。梶尾作品をストレートとすると、奥泉作品はスクリューボール、いや、大リーグ・ボール第2号”消える魔球”かもです。
本作に登場する人物はさほど多くないのですが、途中から誰が誰だか、何が何だか訳が分からなくなります。誰が実在の人物なのか架空の人物なのか、誰が死んだのか、誰が殺したのか、そもそも死んだ人間がいるのかどうかすら分からなくなり、私の頭の中はパニックに。真実、虚構、夢・幻想・幻視、伝説・言い伝え、噂、小説・・・。これらが渾然一体となって読者を混沌と迷走の世界へと誘うその手腕が凄いです。
小説なので何が真実であるかは作者が決める/提示する、あるいは作者が明示しなければ読者が判断すれば良いのでしょうが、判断すらできなくなって放り出されたような不思議な小説でした。作中に”ささいな事実から偉大な結論を導くのがわれわれ哲学者の役割”との一文がありましたが、ささいな事実からとんでもない推論を導き出したりも。これに引っかかったかな?また、解説にあった一文だったでしょうか、”何が真実か。n人の探偵とn人の真実がある”との表現に、おー、それもありかなと思ってしまいました。
しかし、やはり作者の手で何が真実なのかを提示してほしかった気はします。このフラストレーションのたまり方が面白いですね。
奥泉作品には独特のムードがあるのですが、式根や時宗の内省的・思索的な描写がかなり長く続き、ここは正直言って読むのがしんどかったです。普通の描写が出てくるとホッとしたのも事実で、特に中山氏・佐川氏の明るいキャラはgood.
「鳥類学者のファンタジア」は、日本・ドイツを舞台に繰り広げられる壮大なホラ話といったスケール感があり、一方で軽みもあって読みやすかったのですが、本作はそれに比べると小粒でやや難解な気もして70点としました。
【注意:以下、ネタバレあり】
作中、抜群の存在感と魅力を発揮した衛藤有紀子だが・・・タクシー運転手によると、衛藤有紀子は(死んだはずの)岩館小夜子のペンネームで、小夜子は体調を崩したが、今はかなり加減がよくなり、一人で外出もしているという。
有紀子のような人物は私好みやなあと思っていたのですが、えーっ!あれは小夜子だったの?何が真実なのか分からない作品なのですが、これにはぶっ飛びました。うーむ、見事に作者の術中にはまったか。
ラストに出てくる式根のフィアンセの野中百合子という名も絶妙でした。
****************************** Amazonより ******************************
現代文明を捨て、自然との共生をめざしたコミューンの運動「葦の会」。学生時代に参加し、15年ぶりに再訪した医師・式根を待っていたのは、ブナの森深く、荒廃した無人の入植地だった・・・。理想社会を夢見て残ったはずの恋人と友人はどこに消えたのか?そこで起こった怪死事件は果たして事故か。それとも森に潜む「誰か」が殺したのか?ミステリーとメタフィクションの完全なる融合。