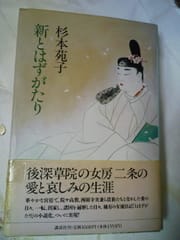
今回は、いつもの平安~源平時代からちょっと時代が下った鎌倉中期の宮廷を舞台にした、歴史小説を紹介します。
☆新とはずがたり
著者=杉本苑子 発行=講談社
内容(「BOOK」データベースより)
華やかな宮廷で、院や高僧、西園寺実兼ら貴族たちと交わした愛の日々。一転、出家し、諸国を遍歴した日々。稀有の女流日記「とはずがたり」の小説化、ついに実現。後深草院の女房二条の愛と哀しみの生涯。
*なお、写真は私が所持している平成2年発行の単行本ですが、現在では単行本・文庫本ともに絶版のようです。本記事を読んで興味を持たれた方、古書店か図書館を当たってみて下さい。
この本を読むのは今回が4回目でした。そのくらい、気に入っている本です。とにかく面白く、哀しく、感動的(ちょっと変な表現ですが)です。絶版なのが本当に惜しいです。
この小説のタイトルのもととなった『とはずがたり』という古典は、鎌倉時代の天皇、後深草院(1243~1304)の女房だった後深草院二条(1258~1306以降)という女性が表した回想記です。
二条は大変、波乱に富んだ人生を送った人でした。彼女の母が後深草院の乳母で、しかも初恋の人だったため、院は忘れ形見の二条を幼いうちから宮廷に引き取り、自ら育てていました。そして、二条が14歳になった正月、まるで『源氏物語』の光源氏と紫の上のように、二人は新枕を交わしたのでした。
しかし、院は二条と他の男の橋渡しをして楽しむ…といった、ちょっと異常ともとれるところがありました。そして二条も、美しいゆえに、後深草院の弟の性如法親王や亀山院、前関白の鷹司兼平といった男たちと交渉を持ちます。また、二条は院と新枕を交わした頃から西園寺実兼(1249~1322)という恋人もいました。その後も色々なこと(母方の祖父の四条隆親に辱められて宮廷を出奔するなど)がありましたが結局、後深草院の中宮、東二条院に憎まれて宮廷を追われ、出家して尼になって諸国を行脚します。こうした華やかな宮廷生活での男性遍歴と、出家してからの諸国行脚の記録を綴ったのが『とはずがたり』です。
この『新とはずがたり』は、この『とはずがたり』の世界を小説化した作品ですが、後書きの著者、杉本苑子さんの言葉を借りれば、内容はだいぶ違っています。
この小説の主人公は二条ではなく、二条の恋人の一人、西園寺実兼です。彼は最終的には太政大臣にまで昇り、関東申次として朝廷と鎌倉幕府の間を取り持ったり、朝廷内部の抗争を仲介するなど、政治的に色々と活躍をした人物でした。『新とはずがたり』は、実兼の目を通して見た鎌倉時代中期の朝廷と幕府、そして二条の生涯を描いたものなのです。
二条は16歳の時に後深草院の皇子を生むのですが、その頃から実兼とも恋仲になり、間もなく彼との子を身ごもってしまいます。このことが露見すると大変なことになりますから、二条が実兼との間に身ごもった子は表向きは院の子とし、院には「流産しました」と届け出て、子供は実兼の腹心の従者の縁者に養子に出されます。
その後間もなく、二条が院との間にもうけた皇子も亡くなってしまいます。二条は十代後半で、子供との生別死別という大きな悲しみを背負ったわけですが、ちょうど二条が悲しみに暮れている頃、九州では大変なことが起こっていました。蒙古襲来…、つまり「文永の役」と言われた戦乱です。
二条の描いた「とはずがたり」には、蒙古襲来については一言も触れられていません。宮廷の女房たちにとっては、「九州の方で何かあったらしい」という意識しかなかったのでしょう。
『新とはずがたり』では、蒙古襲来のいきさつや朝廷と鎌倉幕府の対応について、実兼の目を通してかなり詳細に描かれています。蒙古襲来だけでなく、二月騒動・霜月騒動といった鎌倉幕府側の事件、後深草院と亀山院の対立、その後、天皇家が持明院統と大覚寺等に分かれていく経過などにも触れられていて、大変興味深かったです。
しかし、この小説を読んで一番強烈だったのは、やはり二条という女性の生涯の波瀾万丈さでした。
二条は多くの男性と交渉を持ったのですが、そのうち後深草院、西園寺実兼との間に一人ずつ、性如法親王との間に二人、合計四人の子供をもうけました。しかし、どの子供とも生後間もなく性別あるいは死別し、母親としての喜びをほとんど味わうことができませんでした。おまけに母の大納言典侍(後深草院の乳母)とは2歳の時に死別、父親の久我雅忠とも、十代半ばで死別しています。つまり、肉親との縁が非常に薄い女性だったわけです。
しかも、幼い頃から育ててくれた後深草院は多情で、二条一人に愛情を注いでくれるという男性ではありませんでした。二条を病的に一途に愛し、二条もその激しい愛情を受け入れた性如法親王とも、二十代半ばに死別してしまいます。
そのうえ、宮廷の女あるじとも言うべき東二条院に嫉妬され、いじめ抜かれ、その結果憎まれて、宮廷を追放されてしまいます。そして、11歳も年上の東二条院に頭が上がらない後深草院は、二条を見捨ててしまいます。そんな中、彼女に温かい手をさしのべていたのが実兼だったのでした。
実兼は何とか、二条を宮廷に復帰させようと力を尽くすのですが、結局は失敗に終わります。そこで実兼は、「私の北山の別荘に住んで、私一人を待つという身になりませんか?」と二条を誘うのです。本当に優しい人なのですよね、実兼って…。
私は、この小説ですっかり実兼のファンになってしまいました。物事をてきぱきと進めていくところは格好良いし、情にもろいところがあるのもなかなか素敵です。何よりも、二条をいつでも温かく見守っているところがいいですね。
私が二条だったら多分、「はい、実兼さま、そうさせていただきます。」と言ったと思いますが…。二条はそうしませんでした。
二条はすべてを捨てて出家し、諸国を行脚します。二条が放浪の歌人、西行の書を愛読しており、出家遁世に影響を与えたというのは通説のようで、この小説でも二条が西行の書を読んでいる場面があります。しかし、この小説では二条は当時踊り念仏で庶民から圧倒的な支持を集めていた一遍上人に浸水しており、「すべてを捨て去る」という一遍の教えが二条の出家に大きな影響を与えたと描かれていました。諸国行脚のおかげで二条は身も心もたくましくなり、人間としても成長していきます。
しかし、どうしても捨てきれなかったのは幼いときから育ててくれ、その後夫となった後深草院の面影でした。この小説のラストシーンでは、後深草院の葬送の行列を遠くから見送る二条と、その二条をやはり遠くから暖かいまなざしで見守る実兼の姿が描かれていますが、読む者の心に深く迫ってきて感動的です。
☆トップページに戻る
。
☆新とはずがたり
著者=杉本苑子 発行=講談社
内容(「BOOK」データベースより)
華やかな宮廷で、院や高僧、西園寺実兼ら貴族たちと交わした愛の日々。一転、出家し、諸国を遍歴した日々。稀有の女流日記「とはずがたり」の小説化、ついに実現。後深草院の女房二条の愛と哀しみの生涯。
*なお、写真は私が所持している平成2年発行の単行本ですが、現在では単行本・文庫本ともに絶版のようです。本記事を読んで興味を持たれた方、古書店か図書館を当たってみて下さい。
この本を読むのは今回が4回目でした。そのくらい、気に入っている本です。とにかく面白く、哀しく、感動的(ちょっと変な表現ですが)です。絶版なのが本当に惜しいです。
この小説のタイトルのもととなった『とはずがたり』という古典は、鎌倉時代の天皇、後深草院(1243~1304)の女房だった後深草院二条(1258~1306以降)という女性が表した回想記です。
二条は大変、波乱に富んだ人生を送った人でした。彼女の母が後深草院の乳母で、しかも初恋の人だったため、院は忘れ形見の二条を幼いうちから宮廷に引き取り、自ら育てていました。そして、二条が14歳になった正月、まるで『源氏物語』の光源氏と紫の上のように、二人は新枕を交わしたのでした。
しかし、院は二条と他の男の橋渡しをして楽しむ…といった、ちょっと異常ともとれるところがありました。そして二条も、美しいゆえに、後深草院の弟の性如法親王や亀山院、前関白の鷹司兼平といった男たちと交渉を持ちます。また、二条は院と新枕を交わした頃から西園寺実兼(1249~1322)という恋人もいました。その後も色々なこと(母方の祖父の四条隆親に辱められて宮廷を出奔するなど)がありましたが結局、後深草院の中宮、東二条院に憎まれて宮廷を追われ、出家して尼になって諸国を行脚します。こうした華やかな宮廷生活での男性遍歴と、出家してからの諸国行脚の記録を綴ったのが『とはずがたり』です。
この『新とはずがたり』は、この『とはずがたり』の世界を小説化した作品ですが、後書きの著者、杉本苑子さんの言葉を借りれば、内容はだいぶ違っています。
この小説の主人公は二条ではなく、二条の恋人の一人、西園寺実兼です。彼は最終的には太政大臣にまで昇り、関東申次として朝廷と鎌倉幕府の間を取り持ったり、朝廷内部の抗争を仲介するなど、政治的に色々と活躍をした人物でした。『新とはずがたり』は、実兼の目を通して見た鎌倉時代中期の朝廷と幕府、そして二条の生涯を描いたものなのです。
二条は16歳の時に後深草院の皇子を生むのですが、その頃から実兼とも恋仲になり、間もなく彼との子を身ごもってしまいます。このことが露見すると大変なことになりますから、二条が実兼との間に身ごもった子は表向きは院の子とし、院には「流産しました」と届け出て、子供は実兼の腹心の従者の縁者に養子に出されます。
その後間もなく、二条が院との間にもうけた皇子も亡くなってしまいます。二条は十代後半で、子供との生別死別という大きな悲しみを背負ったわけですが、ちょうど二条が悲しみに暮れている頃、九州では大変なことが起こっていました。蒙古襲来…、つまり「文永の役」と言われた戦乱です。
二条の描いた「とはずがたり」には、蒙古襲来については一言も触れられていません。宮廷の女房たちにとっては、「九州の方で何かあったらしい」という意識しかなかったのでしょう。
『新とはずがたり』では、蒙古襲来のいきさつや朝廷と鎌倉幕府の対応について、実兼の目を通してかなり詳細に描かれています。蒙古襲来だけでなく、二月騒動・霜月騒動といった鎌倉幕府側の事件、後深草院と亀山院の対立、その後、天皇家が持明院統と大覚寺等に分かれていく経過などにも触れられていて、大変興味深かったです。
しかし、この小説を読んで一番強烈だったのは、やはり二条という女性の生涯の波瀾万丈さでした。
二条は多くの男性と交渉を持ったのですが、そのうち後深草院、西園寺実兼との間に一人ずつ、性如法親王との間に二人、合計四人の子供をもうけました。しかし、どの子供とも生後間もなく性別あるいは死別し、母親としての喜びをほとんど味わうことができませんでした。おまけに母の大納言典侍(後深草院の乳母)とは2歳の時に死別、父親の久我雅忠とも、十代半ばで死別しています。つまり、肉親との縁が非常に薄い女性だったわけです。
しかも、幼い頃から育ててくれた後深草院は多情で、二条一人に愛情を注いでくれるという男性ではありませんでした。二条を病的に一途に愛し、二条もその激しい愛情を受け入れた性如法親王とも、二十代半ばに死別してしまいます。
そのうえ、宮廷の女あるじとも言うべき東二条院に嫉妬され、いじめ抜かれ、その結果憎まれて、宮廷を追放されてしまいます。そして、11歳も年上の東二条院に頭が上がらない後深草院は、二条を見捨ててしまいます。そんな中、彼女に温かい手をさしのべていたのが実兼だったのでした。
実兼は何とか、二条を宮廷に復帰させようと力を尽くすのですが、結局は失敗に終わります。そこで実兼は、「私の北山の別荘に住んで、私一人を待つという身になりませんか?」と二条を誘うのです。本当に優しい人なのですよね、実兼って…。
私は、この小説ですっかり実兼のファンになってしまいました。物事をてきぱきと進めていくところは格好良いし、情にもろいところがあるのもなかなか素敵です。何よりも、二条をいつでも温かく見守っているところがいいですね。
私が二条だったら多分、「はい、実兼さま、そうさせていただきます。」と言ったと思いますが…。二条はそうしませんでした。
二条はすべてを捨てて出家し、諸国を行脚します。二条が放浪の歌人、西行の書を愛読しており、出家遁世に影響を与えたというのは通説のようで、この小説でも二条が西行の書を読んでいる場面があります。しかし、この小説では二条は当時踊り念仏で庶民から圧倒的な支持を集めていた一遍上人に浸水しており、「すべてを捨て去る」という一遍の教えが二条の出家に大きな影響を与えたと描かれていました。諸国行脚のおかげで二条は身も心もたくましくなり、人間としても成長していきます。
しかし、どうしても捨てきれなかったのは幼いときから育ててくれ、その後夫となった後深草院の面影でした。この小説のラストシーンでは、後深草院の葬送の行列を遠くから見送る二条と、その二条をやはり遠くから暖かいまなざしで見守る実兼の姿が描かれていますが、読む者の心に深く迫ってきて感動的です。
☆トップページに戻る
。

























