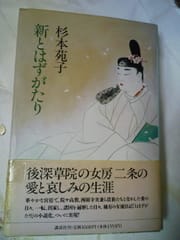今回は、以前
「こちら」の記事で少し紹介したことのある藤原為光の同母兄に当たる藤原高光と、その子孫のお話です。この高光、ちょっと異色の人生を歩んだ人でもあり、子孫も思いがけないところとつながっていますので、私なりにまとめてみることにしました。
では最初に、藤原高光の生涯について紹介しますね。
☆藤原高光(939~994)
右大臣藤原師輔の八男。母は雅子内親王(醍醐天皇皇女)。同母弟妹に為光、天台座主尋禅、源高明室となった愛宮、異母兄弟姉妹に伊尹・兼通・兼家・公季・村上天皇皇后の安子などがいます。
高光は、童名を「まちおさ君」といい、父師輔に大変可愛がられたと伝えられています。(『栄花物語』)。
天暦九年(955)に叙爵。侍従、左衛門佐、右近衛少将、備後権介等を歴任します。また、文才・歌才に優れ、村上天皇を感嘆させたり、天徳内裏歌合わせに出詠したりしています。
このように順調に出世していたのですが、高光は応和元年(961)十二月に突然、出家をしてしまいます。(出家当時の官位は従五位上右近衛少将)
彼の出家の原因については、その前年に、かわいがってくれた父師輔が薨去したためであるとか、藤原氏の政治姿勢、特に長兄伊尹のふるまいに飽き足らなかったなど、色々諸説があるようですが、はっきりした理由はよくわかりません。しかし高光は、紅葉が散るのが哀しいといった歌を詠むなど、早くから世の無常を感じ、出家願望もあったようです。
高光は比叡山横川において出家をし、法名を「如覚」と号したのですが、翌年多武峯に移ります。これは、世俗化した叡山を離れ、俗化されていない天台の新天地を求めてのことであり、しかも、祖廟が祀られる地であったとの理由によると考えられます。彼が本気になって仏教を極めようとした意気込みが感じられます。彼は多武峯にて厳しい修行を行い、承暦五年に世を去りました。
高光は歌人としても知られ、三十六歌仙の1人にも選ばれています。家集に「高光集」もあり、『拾遺』以下の勅撰集に二十数首入集しています。
ところで、高光について書かれたものに「多武峯少将物語」があるのですが、これは、出家をして比叡山に入った彼が多武峯に移るまでと、その周囲の人たちの心情を綴ったものです。
高光は、叔父である藤原師氏の女、つまりいとこに当たる女性を妻にしていました。師氏は、他の兄弟(実頼・師輔・師尹)と違ってあまり政治的な野心がなく、従って娘を入内させるのではなく、「気心の知れた高光殿と幸せな人生を送って欲しい」と願い、愛娘と高光を結婚させたのかもしれません。しかし、高光の出家でその願いは打ち砕かれてしまったのですが…。
「多武峯少将物語」によると、高光が出家したことによって妻が嘆き悲しみ、「私も出家したい」と思うものの、高光殿と同じ山に入れるわけではないので泣く泣く断念する様子や、高光と妻の長歌の贈答なども綴られています。
また、二人の間には、当時2、3歳くらいのかわいい盛りの娘もいました。高光と妻の贈答歌には、幼い娘を思いやる心情も綴られています。
このように、「私が出家をしてしまったら、一人残されたこの子はどうなるのかしら?」と思ったことも、妻が出家を断念した理由だったのかもしれません。
それでは、この高光の娘はその後どうなったのでしょうか?
彼女は長じて村上天皇の皇子、昭平親王と結婚します。
昭平親王(954~1013)村上天皇第九皇子。母は左大臣藤原在衡女。
彼は天徳四年(960)、七歳の時に臣籍に降下し、源姓を賜ります。しかし、右兵衛督を勤めていた貞元二年(977)、左大臣源兼明(醍醐天皇皇子)とともに親王に復帰するのです。親王復帰というと一見優遇措置に見えますが、ある程度出世した右兵衛督から実権のない四品の親王へ……、これは官界追放に等しいものでした。
昭平親王と高光女がいつ結婚したかは不明ですが、多分、彼が親王に復帰する以前のことだったのではないかと思います。
その後、昭平親王は常陸太守を勤めるのですが、永観二年(984)に三井寺に入って出家をしてしまいます。そして、彼が出家したとき、高光女はまだ二十代半ばであり彼女の手許には娘が一人残されました。まるで、かつての母と全く同じ運命を歩むことになってしまった事実を、高光女はどのように受け止めていたのでしょうか。
こうなってみると、昭平親王と高光女の間に生まれた娘のことも気になります。
この娘はその後、どういう事情かは定かではないのですが藤原道兼の養女となり、承暦元年(990)十二月二十五日に藤原公任と結婚することとなるのです。(『小右記』)
藤原公任(966~1041) 父は関白太政大臣藤原頼忠、母は代明親王女厳子女王。四納言の一人。有能で多才な官人でした。歌人・歌学者としても有名です。
昭平親王女は、公任との間に藤原定頼(995~1045)・後に藤原道長の子息教通室となる女・他、数人の子をもうけました。
つまり、今まで長々と述べてきた系譜を簡単に書きますと、
高光→高光女(昭平親王の妻)→昭平親王女(藤原公任の妻)→定頼 となります。
そうです、和泉式部の娘小式部の「大江山」の歌でやりこめられてしまった歌人の定頼さん、高光さんの曾孫だったのですね。このようなところが、女系の系譜の面白いところです。。
定頼は父の公任さんから和歌の才能を受け継いだと思っていたのですが、母方の高光さんを通じてもしっかり、歌才のDNAを受け継いでいるわけです。実際、昭平親王女も歌の才があったらしく、勅撰集に四首入集しているそうです。
一方、藤原教通に嫁いだ定頼の娘は、教通との間に信長(後の太政大臣)・歓子(後冷泉天皇皇后 小野皇太后)・生子(後朱雀天皇女御)といった子女をもうけています。これら教通の子供たちも、高光の子孫というわけです。
さて、こうして高光の血を公任の子供たちに伝えた昭平親王女の晩年ですが…。
彼女がいつ亡くなったかについてははっきりしないのですが、晩年は子供たちの何人かに先立たれ、尼になってしまったようです。万寿三年(1026)、夫の公任が解脱寺にて出家していますので、彼女もそれに殉じたのかもしれません。
彼女は多分、先立たれた子供たちや、不遇だった父、若くして夫に出家されてしまった母や祖母、そして、右近衛少将という将来を保証されている身分を捨てて多武峯に入ってしまった祖父の菩提を弔うことも日課にしていたのでしょう。出家後の彼女が心安らかであったことを祈りたいです。
☆参考文献
『平安時代史事典 CD-ROM版』 角田文衞監修 角川学芸出版
『王朝千年記 ー王朝日誌九九〇年代』 槙野廣造 思文閣出版
☆トップページに戻る