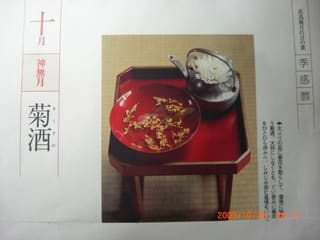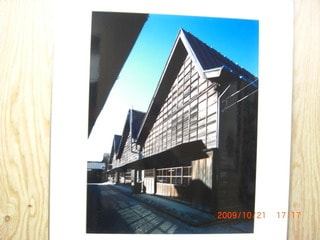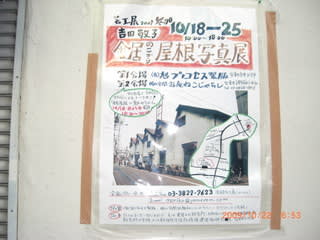(宝島社文庫表紙)
”3人はいったい何処に消えたのか?”この難問を解く為に泉さん達は情報収集に奔走します。この厳冬期、槍ヶ岳を目指したパーティは17。行動中にのらくろ岳友会の3名を見かけなかったかを文書で問い合わせ、直接に話を聞きにも出かけます。より重要な証言が得られそうと思えれば、遠く長崎までも足を延ばします。そうやって作り上げたのが「北アルプス証言地図」。更に「のらくろパーティの足跡」をも完成させます。そのパンフレットを基に捜索メンバー達の討論が延々と続きます。
槍ヶ岳へ突っ込んで行ったのか?エスケープルートの常念コースに変更したのか?はたまた途中から引き返してきたのか?雪解け開始前に遭難地点を特定しておかねばならないのです。
「大村労山パーティ」の証言の重要性を感じた泉さんは長崎に飛び、直接話を聞きます。常念山頂を目指し大村労山パーティの二人は、猛吹雪吹きつのる稜線をラッセル中に、常念岳方面から下ってくる3名と遭遇。先頭の”赤いヤッケ”の人間と握手をし、言葉も交わしたとも語るのです。総合的に判断し、この3名こそのらくろ岳友会の3名だろうと推定します。
槍ヶ岳を目指したにも拘わらず、猛烈な悪天候の為か、槍ヶ岳突入を断念した3名は、エスケープルートの常念に向ったものの、何故か常念からも撤退したと判断せざるを得なくなります。その撤退の尾根上に彼らの足跡を発見出来ない以上、最後に残された可能性は唯一つ「常念乗越」から下る「一の沢」ルートしかありません。積雪期決して下ってはいけないと言われる沢コースです。この一の沢は特に雪崩多発の最も危険な沢なのです。
あの3人が山の鉄則を犯すはずがない、犯していて欲しくない、岳友たちの偽らざる心境です。しかし泉さんはこの沢に彼ら3名は眠っているとして、捜索地点を一の沢に特定するのです。
捜索活動開始前に挿入された一章「男たちの残像」で、彼ら3名の生い立ちと素顔が語られます。遭難数年の後、3名の生まれ故郷の北海道滝川市や高知県まで出向き、肉親の方々から聞き取った生の声。実在したとは思えないほどの個性的で魅力的なキャラクターがそこには書かれていました。
捜索再開から3ヶ月、6月27日と28日に、一の沢で漸く2遺体発見。6月30日に最後の遺体も。遭難原因は雪崩でした。遺族が遺体に接する場面では涙無しには読み進めません。
どうして3人は鉄則に反してまで一の沢を下ったのか。山仲間が、一の沢を遭難地点と推定し入山するたびに抱き続けた疑問は最後まで解かれないまま、ドキュメントは終わります。
最終ページで、遭難現場に雪の墓標を立て終えた遺族の一人が急な斜面をあえぎながら登り、稜線に出て、広大な谷の向こう側に、槍ヶ岳から穂高連峰へと続く稜線を眺めたときの描写を、著者はこう語ります。
『兄はたしかに、弟の足跡を求めてやってきた。しかしそのとき、兄を捉えていたものは、もう弟ではなかった。
ドーンと土鳴りがする風景
天空にそびえ立つ 白い槍
頂から走り下る あらぶる谷々
そこへ続く 長い尾根の道
人がこの世に現われる前に刻みあげられた地球の貌・・・
一年前、捜索のために登って来たものがそうしたように、兄もまた、声もなく、そこに立ちつくした。』
遭難の物語であり、ミステリーでもあり、人間のドラマでもあるこのドキュメント。「卓越した記録文学」との評もあります。私は更に、基底通音として流れるのは自然賛歌なのだと思いながら物語を読み終えました。