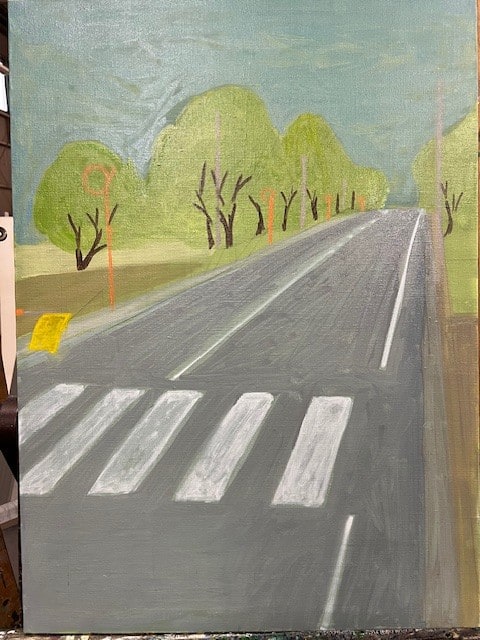文春新書の「ピークアウトする中国」梶谷懐・高口康太を読んだ。何故かというと断片的でなく断言的でない中国の実情を知りたいと考えていたからだ。中国や韓国を嫌うユーチューバーが多く?(そうした人の実際の数は分からない)、誇張して悪く書くので今にも滅びてしまいそうな印象を受けるが、現地の映像を見ると人々は裕福ではないが普通の日常を生きているようで、実際はどうなんだろうと疑問を持っていた。
できれば三冊、少なくとも一冊は文庫本程度の分量内容の本(情報)を頭に入れなければ、物事の実際は理解できないと考える。
ピークアウトするという題名はどうかと思うが、人の眼を引き読んでもらうにはこうした題名が良いらしい。確かに内容の一部を的確に表現しているが、週刊誌的ではなくどちらかと言えば学術的な噛み応えのある内容の本だ。確かに中国は厳しい状態にあるようだが、世界にそうした国は多い。日本は危機感が乏しく、安閑としていられないと教えられた。