教室のまとめが届きました。
19年7月から11月まで計6回。参加実人員30人。延べ人員134人。
成績比較できた人は23人で、その内訳は
改善13人(56.5%)
維持 6人(26.1%)
低下 4人(17.4%)
多くの教室では、改善60%維持30%低下10%という割合が多いので、やや低下群が多いといえます。(今日の写真は横浜市内 開港記念館・日本初の水道蛇口・神奈川県庁)
教室の効果が今ひとつ、低下群が多いときや改善群より維持群が多いときの教室に共通する条件をまとめて見ました。
まず、期間が短いことがあげられるでしょう。
次に、教室のプログラム内容も検討しなくてはいけません。特に期間が短いときには、意識的に右脳活性化を重視する必要があります。
・勝負がはっきりするゲーム(ただし、笑いを伴うもの。・個人の失敗がはっきりしない集団対抗戦も有効)
・楽しい歌唱指導
・歌と運動を組み合わせたものなどが中心となります。
 ボケ予防教室開催時には「単なるお楽しみ会ではなく、あくまでも脳を活性化してボケ予防をする」という教室の目的をはっきりさせなくてはいけません。
ボケ予防教室開催時には「単なるお楽しみ会ではなく、あくまでも脳を活性化してボケ予防をする」という教室の目的をはっきりさせなくてはいけません。
そのためには脳機能テストを実施することと、それに基づいた生活指導が必須になります。
個別生活指導は効果的ですが、全体に対して、あまり説明的になりすぎる(左脳優位)と、教室があまり面白くなく、お話を聞いて勉強するということになってしまいます。
また、硬い世話役の「子供っぽいものはちょっと・・・。~さんから~について解説してもらおう」という意見を重視して、講話中心のプログラムになってしまわないように気をつける必要があります。 教室では、「仕事ばかりでなく、楽しむことも脳の健康には必要で、脳の健康を保つためには教室で体験したような楽しいことがもっとも有効なのだ」ということを実感してもらうのです。
教室では、「仕事ばかりでなく、楽しむことも脳の健康には必要で、脳の健康を保つためには教室で体験したような楽しいことがもっとも有効なのだ」ということを実感してもらうのです。
教室終了時に、楽しかったという思いと脳機能の改善という客観的データが、確実な自信につながり、「遊び」が日常生活の中で実践され続けるという生活変容が行われることになります。
この教室のプログラムを見ていきましょう。
歌にあわせて体操 (富士山・星影のワルツ)
(富士山・星影のワルツ)
掛け声だけの体操に比べ参加者の笑顔が見えるようです。
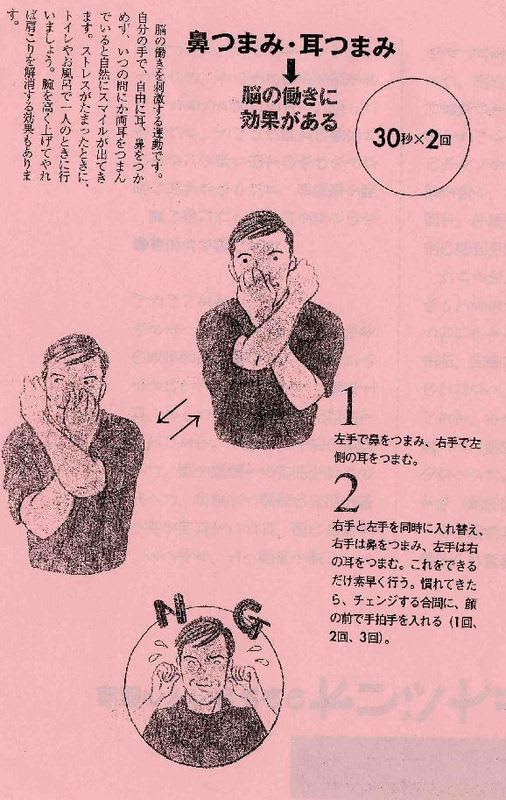 これはどうでしょうか?
これはどうでしょうか?
みんなと一緒なら、笑いもでるでしょうが、家で一人でやっている姿を想像してみてください。あんまり楽しくないと思いませんか。これをやって生活面で何か意欲的になれるでしょうか?
体の動きも脳が支配しているという体験にはなると思います。
 さて次はどうですか?
さて次はどうですか?
教室では多くの人が考えている「脳を使う=読み書きそろばん」という常識を覆さなくてはいけません。
・体を動かすのも脳
・楽しく遊ぶのも脳
・ものづくりも脳
・歌うのも脳
・人付き合いも脳
趣味・遊び・人付き合いは、右脳のアナログ情報を処理する機能を駆使して行われます。そして多くの人たちは、この右脳の機能を軽視していますから、そこに気づいてもらうのが教室の目的です。もちろん常に前頭葉は司令塔として関与し続けていますよね。
教室を動かす皆さんは、右脳と前頭葉の連携プレイの体験こそ教室のテーマということを忘れないようにしてください。 今いくつか問題点をあぶりだしましたが、教室はうまくいったことを忘れないでください。
今いくつか問題点をあぶりだしましたが、教室はうまくいったことを忘れないでください。
教室の有効率は82.6%です!
左は感動的な「感想集」です。
プログラムには、上記のほか花瓶つくりやその他工夫がされていたことがわかりますね。
そして何より「人と一緒に楽しいひと時を過ごせてうれしかった」というこの感想こそ、教室の求めているものなのです。それがボケ予防の鍵ですから。
わずか3ヵ月半、6回の教室で、このような感想を持たれた皆さんは、生活の見直し・改善ができそうですね。
 さて、脳機能改善ができなかった低下群にはどのような共通項があったと思いますか?
さて、脳機能改善ができなかった低下群にはどのような共通項があったと思いますか?
全員が小ボケレベルだったのです。
80歳代でもはっきり改善できた人もいれば、小ボケレベルでも改善された方たちもいましたが、低下群はすべて小ボケ。
小ボケ群のなかでの改善・低下の差については、重症度や家族関係や身体状況などが影響していると思いますが、いずれにしても、教室の目的である「脳のために健康的な生活を知る」には早いほど効果的ということがいえますね。
教室開始時に正常群だった人たちはすべて改善していましたから。
うれしい報告をありがとうございました。














