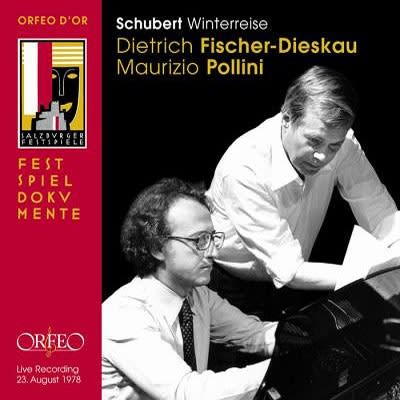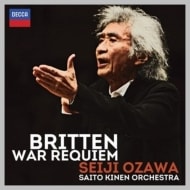スクリャービン ピアノ協奏曲 嬰へ長調 作品24
ギャリック・オールソン(ピアノ)リボル・ペシェック指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団(1985年録音 SUPPAPHON盤)
フィギュアスケートの演技をテレビで演技を見ていると、必ず毎シーズン、1曲は「この曲はまだCDを持っていないぞ」と慌てCDを購入することがあります。
今シーズンはスクリャービンのピアノ協奏曲。
アイスダンスのテッサ・ヴァーチュ&スコット・モイアのフリーダンスのプログラムに含まれている。
初期の作品と言うことで、後年の独自性より、どちらかと言うとロシア独特のの愁いを感じました。
CDを購入するに当たって最初はウラデミール・アシュケナージのピアノ独奏、ロリン・マゼール指揮フィルハーモニア管弦楽団の録音(デッカ盤)にしようと思っていましたが、いろいろ調べてみて気が変わりチェコフィルの演奏の録音があるのを知り、こちらにしました。
ピアノ協奏曲をピアニストよりオーケストラで選ぶとは私はやはり変ですなあ。
チェコフィルの魅力には勝てなかったというのが本音でしょう。
最初に収録されているのは交響曲第4番「法悦の詩」
チェコフィルの響きは聴きものでした。
考えてみるとロシア音楽は好きなのですが、まだスクリャービンの作品のCDは、きちんと揃っていない。
今回は、スクリャービンに入って行く、いいきっかけになりました。
以前、中野友加里さんの「ジゼル」を見てクラシックバレエのCDやDVDが増えた時と同様、フィギュアスケートの影響でクラシック音楽を聴く方向が、思いもつかない方に向いてしまうことがあります。
今回のスクリャービンも、そんな気配かな?
交響曲全集は誰のが良いのだろうか?また、いろいろ調べなくてはいけません。

 にほんブログ村
にほんブログ村
ギャリック・オールソン(ピアノ)リボル・ペシェック指揮チェコ・フィルハーモニー管弦楽団(1985年録音 SUPPAPHON盤)
フィギュアスケートの演技をテレビで演技を見ていると、必ず毎シーズン、1曲は「この曲はまだCDを持っていないぞ」と慌てCDを購入することがあります。
今シーズンはスクリャービンのピアノ協奏曲。
アイスダンスのテッサ・ヴァーチュ&スコット・モイアのフリーダンスのプログラムに含まれている。
初期の作品と言うことで、後年の独自性より、どちらかと言うとロシア独特のの愁いを感じました。
CDを購入するに当たって最初はウラデミール・アシュケナージのピアノ独奏、ロリン・マゼール指揮フィルハーモニア管弦楽団の録音(デッカ盤)にしようと思っていましたが、いろいろ調べてみて気が変わりチェコフィルの演奏の録音があるのを知り、こちらにしました。
ピアノ協奏曲をピアニストよりオーケストラで選ぶとは私はやはり変ですなあ。
チェコフィルの魅力には勝てなかったというのが本音でしょう。
最初に収録されているのは交響曲第4番「法悦の詩」
チェコフィルの響きは聴きものでした。
考えてみるとロシア音楽は好きなのですが、まだスクリャービンの作品のCDは、きちんと揃っていない。
今回は、スクリャービンに入って行く、いいきっかけになりました。
以前、中野友加里さんの「ジゼル」を見てクラシックバレエのCDやDVDが増えた時と同様、フィギュアスケートの影響でクラシック音楽を聴く方向が、思いもつかない方に向いてしまうことがあります。
今回のスクリャービンも、そんな気配かな?
交響曲全集は誰のが良いのだろうか?また、いろいろ調べなくてはいけません。