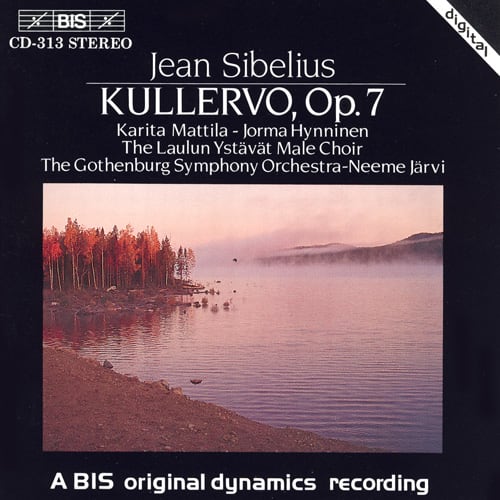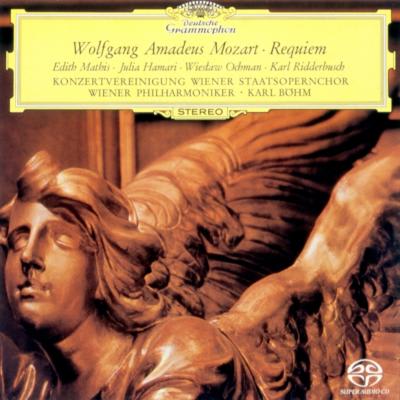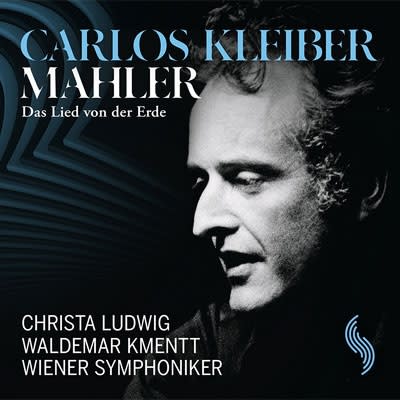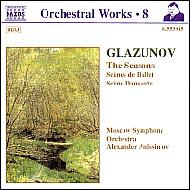シベリウス 交響曲第4番イ短調 作品63、交響曲第5番変ホ長調 作品82
尾高忠明指揮、札幌交響楽団(1914年2月、3月札幌コンサートホールKitaraでのライブ録音。フォンテック盤)
フレンズオンアイスが終わるまで財務大臣閣下よりCD購入禁止令が公布されていたにもかかわらず、禁を破って1枚のCDを購入してしまった。
尾高忠明指揮の札幌交響楽団によるシベリウスの交響曲の録音。
実は私は昨年2月に尾高忠明がNHK交響楽団を指揮しての定期演奏会でのシベリウスの「四つの伝説曲」の演奏が大好きで今も仕事を終えて帰宅してから、今もよく録画を見ています。
それだけに現在進行中の札幌交響楽団とのシベリウス交響曲全集は楽しみにしていました。
既に1番から3番までが発売されていますが、聴いてみてこのコンビだったらもっとやれるのではと思いを強くしています。
それだけに、シベリウスの音楽の神髄と言える今回の4番と5番の録音は期待よりも不安の方が強かったのですが、第4番の第1楽章の冒頭を聴いただけで、そんな不安はどこかへ消し飛んでしまいました。
正にシンと静まりかえった静寂そのものの音楽を見事に演奏している。本当に見事な演奏である。
私は4番と5番の組み合わせが大好きである。
第4番の暗く静寂で孤独感が伝わってくる音楽のあとに第5番の第1楽章を聴くと何か北欧の大自然の雄大な日の出を連想させるものがあり私は大好きである。
今回のCDは私の大好きな組み合わせで素晴らしい演奏を聴かせてくれて本当に嬉しい。
30歳代半ばでヘルシンキ郊外のヤルヴェンバーの「アイノラ荘」にひきこもったシベリウスは北欧の自然を前にして正に宇宙を見据えた音楽を書く。
それが第4番から第7番の交響曲。正に孤高の音楽。
尾高忠明指揮による札幌交響楽団のシベリウス交響曲全集も残すところ6番と7番のみ。
日本人指揮者と日本のオーケストラによる最高のシベリウスの演奏。
おそらくこの組み合わせで次回は発売されるのでしょう。本当に楽しみです。

 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
尾高忠明指揮、札幌交響楽団(1914年2月、3月札幌コンサートホールKitaraでのライブ録音。フォンテック盤)
フレンズオンアイスが終わるまで財務大臣閣下よりCD購入禁止令が公布されていたにもかかわらず、禁を破って1枚のCDを購入してしまった。
尾高忠明指揮の札幌交響楽団によるシベリウスの交響曲の録音。
実は私は昨年2月に尾高忠明がNHK交響楽団を指揮しての定期演奏会でのシベリウスの「四つの伝説曲」の演奏が大好きで今も仕事を終えて帰宅してから、今もよく録画を見ています。
それだけに現在進行中の札幌交響楽団とのシベリウス交響曲全集は楽しみにしていました。
既に1番から3番までが発売されていますが、聴いてみてこのコンビだったらもっとやれるのではと思いを強くしています。
それだけに、シベリウスの音楽の神髄と言える今回の4番と5番の録音は期待よりも不安の方が強かったのですが、第4番の第1楽章の冒頭を聴いただけで、そんな不安はどこかへ消し飛んでしまいました。
正にシンと静まりかえった静寂そのものの音楽を見事に演奏している。本当に見事な演奏である。
私は4番と5番の組み合わせが大好きである。
第4番の暗く静寂で孤独感が伝わってくる音楽のあとに第5番の第1楽章を聴くと何か北欧の大自然の雄大な日の出を連想させるものがあり私は大好きである。
今回のCDは私の大好きな組み合わせで素晴らしい演奏を聴かせてくれて本当に嬉しい。
30歳代半ばでヘルシンキ郊外のヤルヴェンバーの「アイノラ荘」にひきこもったシベリウスは北欧の自然を前にして正に宇宙を見据えた音楽を書く。
それが第4番から第7番の交響曲。正に孤高の音楽。
尾高忠明指揮による札幌交響楽団のシベリウス交響曲全集も残すところ6番と7番のみ。
日本人指揮者と日本のオーケストラによる最高のシベリウスの演奏。
おそらくこの組み合わせで次回は発売されるのでしょう。本当に楽しみです。