『ある哲学者の人生』によれば講読会の初期のメンバーにはピーテル・バリングもいました。熱心な参加者で,スピノザの哲学についての論文も執筆しました。これは『燭台の上の光』というタイトルで1662年に匿名でリューウェルツによって出版されています。日本語訳がないので僕は未読ですが,ナドラーによれば光とは理性のこと。理性を光で喩えるのはこの時代には一般的なことだったかもしれませんが,スピノザも同じような比喩を用いていて,共通性があるのは間違いありません。
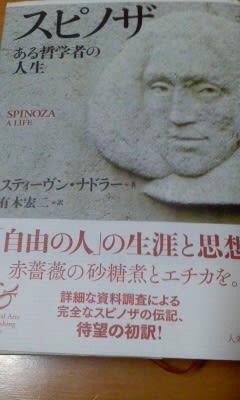
スピノザと知り合ったのはコレギアント派の人脈によるものとナドラーは想定しています。『デカルトの哲学原理』は1663年に出版されましたが,翌年にオランダ語訳も出版されています。この翻訳者がバリングでした。すでにその時点でスピノザの親友のひとりになっていたと解してよいでしょう。スピノザより先に死んだので遺稿集の編集者にはなっていませんが,生きていれば間違いなくその役を担うべきひとりであったと思います。
バリングはスピノザの親友やおそらくそこまでいかない友人たちの中で,特別な点がありました。バリングはかつてオランダ商館の代表者としてイベリア半島にいたことがあり,そちらの言語に習熟していたのです。『ある哲学者の人生』や『スピノザの生涯と精神』ではスペイン語,『スピノザ往復書簡集』ではポルトガル語とされていて,両方ともできたのかもしれません。仮に一方だけであったとしても,スピノザと言語で示したように,スピノザが幼少期に使っていた言語ができたことになります。
スピノザとブレイエンベルフの文通はオランダ語で交わされましたが,スピノザが送った最初の書簡の最後に,幼い頃から親しんでいた言語で書ければもっとよく自分の思想を表現できたと書かれています。これはポルトガル語かスペイン語を意味する筈です。ですからバリングがその言語でスピノザと会話することができたということは,あまり軽く見積もってはいけないことだろうと僕は考えています。
現実的に存在する,すなわち持続する限りで存在している人間の精神が,何らかの事柄を永遠の相の下に認識することが可能であるということは,確かに証明を要することであったと僕は考えます。とくに第二部定理四四系二のように,理性による認識が観念されたものideatumを永遠の相の下に認識すると主張する場合には,なおさらそれを示す必要があったと僕は思います。
理性による認識の基礎になっているのが共通概念です。ところがすでに示したように,人間の精神は現実的に存在する限りにおいて,他面からいえば現実的に存在している人間の身体が外部の物体によって刺激される限りにおいて,共通概念を認識することができるというように解読できます。第二部定理三八も第二部定理三九も,その論証のために現実的に存在する人間の身体と人間の精神について言及している第二部定理一三に訴求しているからです。ですからこれだけだと,共通概念による認識も,ただ持続的なものとしての認識と理解されかねません。第二部定理四四系二の証明で,事物を永遠に認識するとはいかなることかを示すために,第一部定理一六を援用する必要があったと,十分に考え得ることになります。
観念対象が個物である場合,それを永遠の相の下に認識することが可能なのは,第二部定理八系の意味が論拠になります。個物は持続していようといまいと,永遠のうちに存在しているからです。ですが共通概念の場合にはこのことはそれが永遠の相の下での認識であるということの根拠ではあり得ません。いうまでもなく第二部定理三七により,共通概念の認識は個物の認識ではないからです。
ここでは第五部定理二二および第五部定理二三と関連性をもたせるために,共通概念も神の無限知性の一部を構成するという観点から,僕はそれを永遠の相の下に認識することは可能であると説明しました。しかし,もしもこのことだけを眼中において説明しようとするなら,神との関連付けは必ずしも必要ではないのです。第二部定理四四系二補足で説明したように,共通概念は個物の本性を説明しないので,そこからこれが永遠の相の下での認識であると帰結するからです。
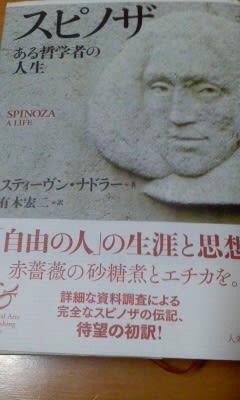
スピノザと知り合ったのはコレギアント派の人脈によるものとナドラーは想定しています。『デカルトの哲学原理』は1663年に出版されましたが,翌年にオランダ語訳も出版されています。この翻訳者がバリングでした。すでにその時点でスピノザの親友のひとりになっていたと解してよいでしょう。スピノザより先に死んだので遺稿集の編集者にはなっていませんが,生きていれば間違いなくその役を担うべきひとりであったと思います。
バリングはスピノザの親友やおそらくそこまでいかない友人たちの中で,特別な点がありました。バリングはかつてオランダ商館の代表者としてイベリア半島にいたことがあり,そちらの言語に習熟していたのです。『ある哲学者の人生』や『スピノザの生涯と精神』ではスペイン語,『スピノザ往復書簡集』ではポルトガル語とされていて,両方ともできたのかもしれません。仮に一方だけであったとしても,スピノザと言語で示したように,スピノザが幼少期に使っていた言語ができたことになります。
スピノザとブレイエンベルフの文通はオランダ語で交わされましたが,スピノザが送った最初の書簡の最後に,幼い頃から親しんでいた言語で書ければもっとよく自分の思想を表現できたと書かれています。これはポルトガル語かスペイン語を意味する筈です。ですからバリングがその言語でスピノザと会話することができたということは,あまり軽く見積もってはいけないことだろうと僕は考えています。
現実的に存在する,すなわち持続する限りで存在している人間の精神が,何らかの事柄を永遠の相の下に認識することが可能であるということは,確かに証明を要することであったと僕は考えます。とくに第二部定理四四系二のように,理性による認識が観念されたものideatumを永遠の相の下に認識すると主張する場合には,なおさらそれを示す必要があったと僕は思います。
理性による認識の基礎になっているのが共通概念です。ところがすでに示したように,人間の精神は現実的に存在する限りにおいて,他面からいえば現実的に存在している人間の身体が外部の物体によって刺激される限りにおいて,共通概念を認識することができるというように解読できます。第二部定理三八も第二部定理三九も,その論証のために現実的に存在する人間の身体と人間の精神について言及している第二部定理一三に訴求しているからです。ですからこれだけだと,共通概念による認識も,ただ持続的なものとしての認識と理解されかねません。第二部定理四四系二の証明で,事物を永遠に認識するとはいかなることかを示すために,第一部定理一六を援用する必要があったと,十分に考え得ることになります。
観念対象が個物である場合,それを永遠の相の下に認識することが可能なのは,第二部定理八系の意味が論拠になります。個物は持続していようといまいと,永遠のうちに存在しているからです。ですが共通概念の場合にはこのことはそれが永遠の相の下での認識であるということの根拠ではあり得ません。いうまでもなく第二部定理三七により,共通概念の認識は個物の認識ではないからです。
ここでは第五部定理二二および第五部定理二三と関連性をもたせるために,共通概念も神の無限知性の一部を構成するという観点から,僕はそれを永遠の相の下に認識することは可能であると説明しました。しかし,もしもこのことだけを眼中において説明しようとするなら,神との関連付けは必ずしも必要ではないのです。第二部定理四四系二補足で説明したように,共通概念は個物の本性を説明しないので,そこからこれが永遠の相の下での認識であると帰結するからです。













