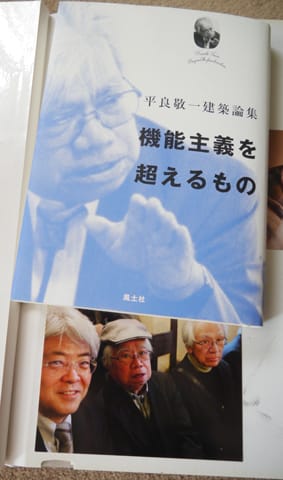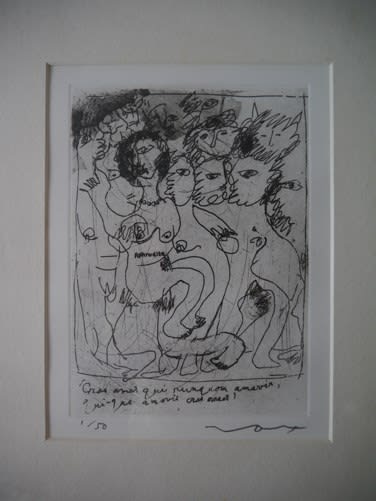今日は7月の末、友引でもある。明日から八月、葉月と言うそうな!晴天、猛暑。新宿中央公園の蝉、ここを先途と・・・鳴き喚く・・・
先週末、建築雑誌に連載している「建築家模様」の原稿UP。先々週、長野に赴いて二人の建築家にヒヤリング、建てた建築に身を浸して建築家冥利に尽きる!との一言を内に秘めた。一人を起稿してしまうと肩の力が抜けてさて次を、と思いながらもふと沖縄のこの夏の様を聞きたくなって電話した。ところが目指した建築家根路銘安史、不在。扨ても(さても)と新しい建築構築にトライする若き(と言ってもそれなりの歳ではある)建築家の仕業にふと敬意を表したくなった。
この一文を書き込んでいるPCの左手につつましく立てかけてある白木のフレームの中のカレンダー。聖クララ教会でのコンサートの写真、プレゼントしてくれた盟友新川清則の顔をふと想い起し1月・2月の写真を見遣る。右端には彼が、なんと僕は左端で13人の友人たちと共に微笑んでいる。背の高い根路銘は右奥で・・・更に、3,4月のには聖クララで挨拶を述べている僕の笑顔が・・・この写真はどうもパッとしないが、我が妻君の一言、これがあんたよ!とさらりと躱(かわ)されたこを思い出した。
馬鹿を言っているうちに昼がくる。午後からある新聞の記者が来所、築地市場問題に関してのヒヤリングとのこと。それはさておき、妻君が持ってきた`海苔弁当`が今日の昼飯、この一文を取りまとめてから味わうことにした。税込398円也!
<写真:新宿中央公園から見やる都庁庁舎>