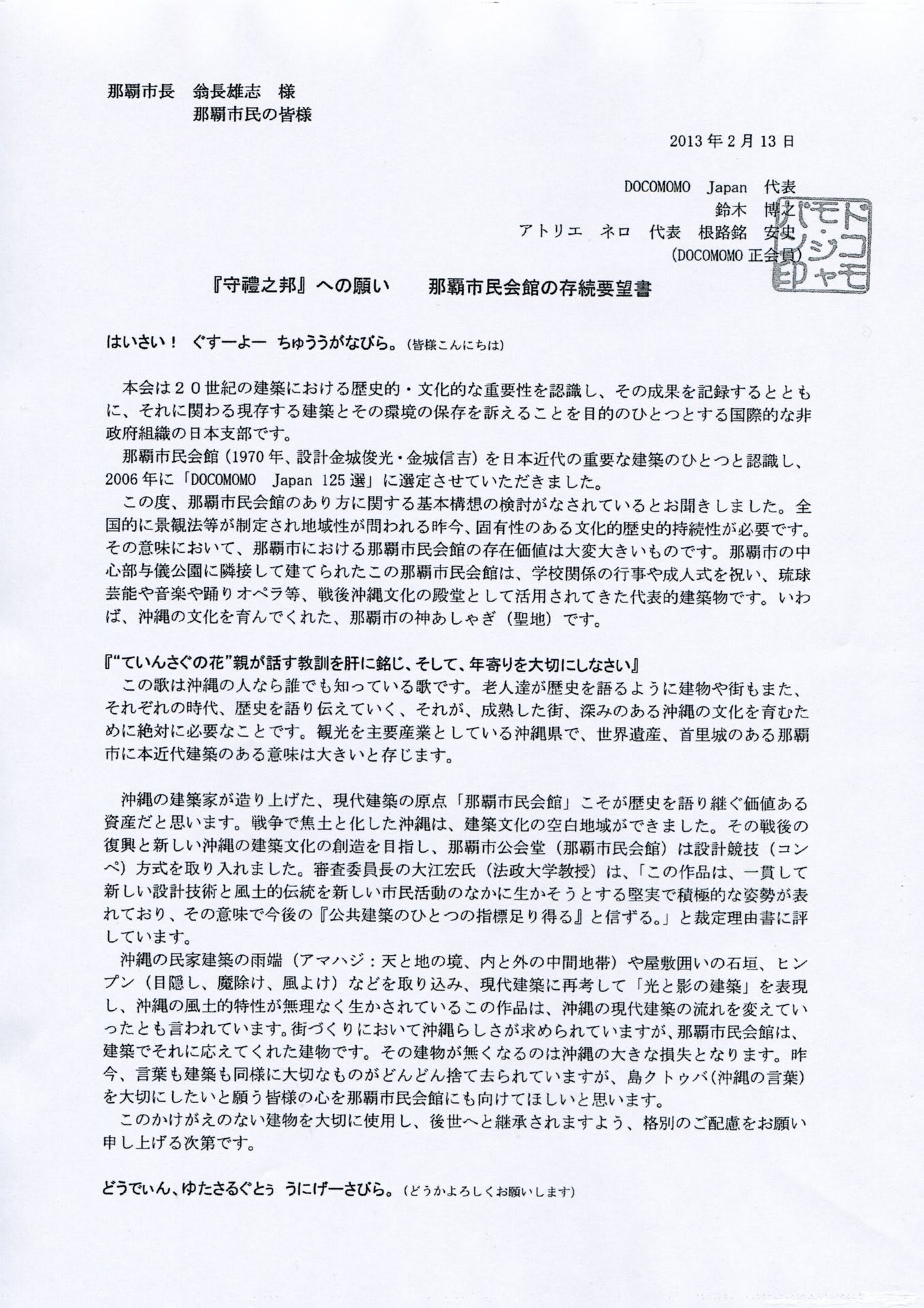小田急線の参宮橋で降り「国立オリンピック記念青少年総合センター」へ向かった。坂倉建築研究所の大阪事務所を率いた建築家太田隆信さんに、設計をしたこの建築群を案内していただいてお話をお聞きし、プロフィールの撮影をさせてもらうのだ。
神宮前のJIA会館で行われる亡くなられた坂倉での嘗ての同僚、戸尾任宏さんの作品集の出版を祝い思い出を語る会に参加する為に來京する(3月29日)この日になった。
建築ジャーナル誌の編集長に僕の描いていた問題認識に共感を頂くことができ、1月号から「建築家模様」と題した写真と文(エッセイ)による連載を始めた。札幌の圓山さん、仙台の針生さん、土佐の高知の山本長水さん、そしてつい最近発行された4月号には早稲田の石山修武教授に登場頂いた。
2月の沖縄行きは、DOCOMOMOで選定した二つの建築、「聖クララ教会」でのコンサートを楽しみ、「那覇市民会館」の存続の要望書の提出と共に、沖縄の、二人の建築家の設計した建築を視てヒヤリングするのが目的でもあった。なんとも嬉しいことに島酒を酌み交わしながら!ということになった。やはり沖縄は沖縄だ!
そして考える。何方と会っても建築がその地の風土や社会と深い関わりがあってつくられることの確認をすることになり、そしてトライしてきた建築家としての軌跡を検証することにもなった。
鬚男太田隆信さんの、人を魅了して放さない滔々たる話振りを僕は密かに`大田節`といっている。でも中村文美編集長も同席したこの日の会話では、オヤ!と思うくらいに真摯、僕も心して話を伺うことになった。
嘗ての代々木練兵場の跡地、そこにあった大木を残すことに腐心し、その桜の大樹と共に敷地内通りの桜並木が満開だ。桜吹雪を浴びながら、トレパン姿の5人の女子高生が高く足を上げてジョギングトレーニングをしている。一列に並んで、点呼をしている若者たちもいる。ここの、武者英二さんが「これは街である」と述べ、太田隆信さんが「建築というのは楽しくなくてはいけないと思う」と述べた賑やかな建築群が理性と知性によって浮かび上がってきて、その姿はこの日の桜吹雪とよく似合っている。
JIAの大会をここで開いたときに泊まった事があるが、時を経て感じ取り方が変わってきたのだろうか。桜吹雪を一緒に浴びながらの今日のこのひと時は「一期一会」。太田ワールドは懐が深い。
神宮前のJIA会館で行われる亡くなられた坂倉での嘗ての同僚、戸尾任宏さんの作品集の出版を祝い思い出を語る会に参加する為に來京する(3月29日)この日になった。
建築ジャーナル誌の編集長に僕の描いていた問題認識に共感を頂くことができ、1月号から「建築家模様」と題した写真と文(エッセイ)による連載を始めた。札幌の圓山さん、仙台の針生さん、土佐の高知の山本長水さん、そしてつい最近発行された4月号には早稲田の石山修武教授に登場頂いた。
2月の沖縄行きは、DOCOMOMOで選定した二つの建築、「聖クララ教会」でのコンサートを楽しみ、「那覇市民会館」の存続の要望書の提出と共に、沖縄の、二人の建築家の設計した建築を視てヒヤリングするのが目的でもあった。なんとも嬉しいことに島酒を酌み交わしながら!ということになった。やはり沖縄は沖縄だ!
そして考える。何方と会っても建築がその地の風土や社会と深い関わりがあってつくられることの確認をすることになり、そしてトライしてきた建築家としての軌跡を検証することにもなった。
鬚男太田隆信さんの、人を魅了して放さない滔々たる話振りを僕は密かに`大田節`といっている。でも中村文美編集長も同席したこの日の会話では、オヤ!と思うくらいに真摯、僕も心して話を伺うことになった。
嘗ての代々木練兵場の跡地、そこにあった大木を残すことに腐心し、その桜の大樹と共に敷地内通りの桜並木が満開だ。桜吹雪を浴びながら、トレパン姿の5人の女子高生が高く足を上げてジョギングトレーニングをしている。一列に並んで、点呼をしている若者たちもいる。ここの、武者英二さんが「これは街である」と述べ、太田隆信さんが「建築というのは楽しくなくてはいけないと思う」と述べた賑やかな建築群が理性と知性によって浮かび上がってきて、その姿はこの日の桜吹雪とよく似合っている。
JIAの大会をここで開いたときに泊まった事があるが、時を経て感じ取り方が変わってきたのだろうか。桜吹雪を一緒に浴びながらの今日のこのひと時は「一期一会」。太田ワールドは懐が深い。