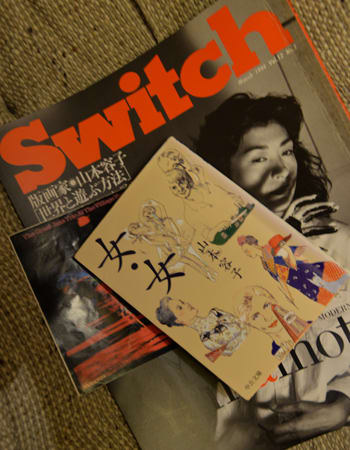2月初旬の訪沖(沖縄)から、ほぼ一月を経てしまった。時の経つのが何とも早い。
特段、何かをしているからだ!という実感がないが、ふと振り返ると、2月はともかく3月早々の`愛知県立芸術大学′の、「新デザイン棟新築工事」に関する委員会への出席(名古屋から地下鉄を経て、モノレールで芸大前行き)。一日置いて、母校・明治大学建築学科「明建会」の(OBと明大卒の教授連による)委員会への参画。僕は数名の後輩連と共に此の委員会の副会長を担っている。そして、その翌日の東海大学病院行き。これは何てこともない傷めている右足脛の様子をチェックしてもらって`湿布`をもらう為。書き記していると何となく情けなくなる。
ところで今日は3月11日。「東日本大震災」に襲われた日。此の日で7年を経たことになる。
僕は例年4月に仙台に赴き、森一郎東北大学教授と、「女川海物語」を書き表した(カタツムリ社刊)写真家 ・小岩勉さんと共に、津浪で被災した女川を訪れ、その変遷を考察してきた。名取市閖上からのスタートが通例になっているが、女川の人々の生活が少しずつ地に着いてきたようでもあるが、この地の人々の思いを受け留め得ているとは言い切れない。
昨年の閖上は、被災後と差して変わらず、そして道中の、海を見遣ることのできない背の高い土手の構築、被災することとは何かという課題を、見せ付けられているような気がしたものだ。
女川の変遷は建築家の一人として、感じ考えるものがあるが、もし今年もお二人と共に女川訪問が出来るとしたら、まちの変遷の見え方が、今までとは異なるのではないかとの予感がある。時を経ることは我が身が時を経るということでもあるから、体力だけではなくて何かが少し変わってきているような気がするのだ、 が!